皆様、こんにちは! ハンズバリュー株式会社の島田です。
メールマガジンの感想、お待ちしております! 「読んでるよ」と言っていただければ励みになります(^_^)
目次
独り言コーナー
❶連休中は大雪予報でしたが大ハズレ!お客様の営業に影響がありますから、あまり脅すような天気予報は辞めてほしいものです。
❷アマゾンで絶版になった本が売っていたりすると、プレミアが付いていることは承知でついつい購入してしまいます。
❸お客様から痛風の発作が始まったとお聞きすると、自分も痛風になったかのように感じてしまい意識してしまいますね。健康のありがたさを改めて考えさせられます。
❹「キャッシュは真実、利益は見解の問題」とは有名な格言ですが、出典がわからずにいました。どうやら 1998年7月24日付の日本経済新聞にフィンランドの通信機器メーカーノキアの財務担当者が”Cash is reality, profit is a matter of opinion.”とプリントしたTシャツを作った記事がもとのようでした。すっきり!
❺坊やがお手紙を書いてくれました。「お父さん、いつも遊んでくれてありがとう」とのこと。そういう認識はなかったので驚きました。こちらこそ、ありがとう。
島田の気になるニュース
❶老化予防に青魚はやはり良いとの認識に立ちました。40歳を過ぎると、この手の話題に敏感に反応してしまいますね。
「オメガ3」だけを3年間毎日飲む→老化抑制に効果 70歳以上の高齢者777人で実験、スイスチームが発表
❷陰謀論かと思ったらマジだった話。なぜにIMFが日本の予算に口出しするのかと思ったら、10年以上財務省出身の人物が副専務理事だったんですね。 “IMFの副専務理事には、古沢満宏氏や篠原尚之氏がいました。古沢満宏氏は2015年3月に就任し、篠原尚之氏はその前任者として5年間務めました。”
IMFが日本財政に警鐘、「明確な健全化計画を」-補正予算に苦言も
❸色々と考えさせられる記事。死があるからこそ種の生存が保たれるとのこと。老兵はただ去るのみですね。僕も若手の邪魔をしないようにしたいです🤔
「老化」は生命の進化において重要な役割を持っている可能性があるとの研究結果
❹社長の年齢が高いのは自然現象ではなく、任せるか任せないかの違いではないでしょうか。なんのために自社があるのか向き合える時間が社長自身に必要なのかもしれませんね。
社長の平均年齢、ついに63歳超え…このままで日本の会社、大丈夫?【東京商工リサーチ調べ】
❺総務チームの仕事のやり甲斐とは?🧐サポート役なので感謝の言葉がやり甲斐に繋がっているようです。島田も当社もお客様のサポート役なので全く同感です。
総務の仕事“やりがい”と“課題”は? 現場のリアルな声を調査【月刊総務調べ】
【今週の経済入門】賃上げだけで本当にデフレ脱却できる?中小企業と日本経済のホンネ
皆様こんにちは、ハンズバリュー株式会社の秘書・勝頼ヒデコです。 いつもメルマガジンをお読みいただき、ありがとうございます。

最近、「賃上げ」の話題をよく耳にしませんか?東京大学の渡辺努教授は「中小企業の賃上げこそが、日本経済をデフレから脱却させるカギだ!」と主張されています。
でも、本当にそれだけで良いのでしょうか?後輩の『ハナコ』も「給料が上がるのは嬉しいけど、それだけで生活が楽になるとは思えない…」と不安げな表情を浮かべていました。当然です!別次元の「デフレ」と「賃上げ」の話題をゴッチャ混ぜにしている点で不信感が募っても仕方ありません。
そこで、本日は「賃上げ」について少し深掘りして考えてみたいと思います。ハナコ、一緒にモヤモヤを解消しましょう!🧐
本日のテーマ『賃上げは万能薬?』
渡辺教授は日本の雇用の約7割を占める中小企業が賃上げをすれば、人々の消費が増え経済が活性化する、と考えています。そのために、中小企業は大企業との間で「フェアな価格交渉」を行い、利益を確保する必要があるとも主張しています。さらに、それでも賃上げできない企業は市場から退場すべきだ、とも…。(清算主義で上手くいった事例があれば聞いてみたいですが…)
確かに、中小企業が適正な価格で製品やサービスを販売でき、その利益を従業員の賃上げに回すことができれば理想的です。
しかし、現実はそう甘くはありません。賃上げ論に5つの視点で反論してみます😌
反論1:賃上げしても、消費が増えるとは限らない!
まず、賃上げされたお金が、必ずしも消費に回るとは限りません。将来への不安や社会保障負担の増大などを考えると人々は貯蓄に回してしまうかもしれません。ハナコも「老後のこととか考えると、なかなかパーッとは使えないよね…」と、現実的な意見を述べていました。
また、賃上げによって物価が上がりすぎると、名目上の賃金は増えても実質的な賃金(=実際に買えるモノやサービスの量)は増えない、という可能性もあります。最近、海外ではインフレ(物価上昇)が問題になっていますが、日本も他人事ではありません。エネルギー価格の高騰や世界情勢の不安定さなど、物価を押し上げる要因はたくさんあります。
反論2:価格転嫁は、そんなに簡単じゃない!
次に、中小企業が「フェアな価格交渉」をすることは言うほど簡単ではありません。大企業との間には(圧倒的な)力関係の差があります。値上げをすることは非常に難しい決断です。
反論3:ゾンビ企業を退場させれば、すべて解決?
渡辺教授は「賃上げできない企業は市場から退場すべき」と主張していますが、これは乱暴な意見です。経営が苦しい企業いわゆる「ゾンビ企業」には、様々な事情があります。借金が多い、事業転換がうまくいかない、などなど…。
それでも、中小企業には地域の雇用を支えている重要な役割があります。そうした企業が単に「生産性が低い」という理由で退場してしまえば、地域経済は大打撃を受けてしまいます。
反論4:人材確保は、お金だけじゃない!
賃上げの目的の一つに「優秀な人材の確保」があります。しかし、最近の若者は、給料だけでなく、働きがい、ワークライフバランス、リモートワークの可否、企業の社会貢献度など、様々な要素を重視して仕事を選びます。ハナコも「給料も大事だけど、働きやすい環境の方がもっと大事!」と力説していました。
反論5:デフレ脱却には、もっと多角的なアプローチが必要!
デフレとは「物価が持続的に下落する状態であり、経済全体の需要が供給を下回ることで発生する現象」であり、賃上げとは別次元のお話しです。日本の物価に直接影響があるのは財政政策、金融政策、エネルギー政策、税制などです。中小企業が賃上げをしたくらいでは、絶対にデフレからの脱却は出来ません。
賃上げは重要、でも…
渡辺教授の主張は、一見すると正論のように聞こえますが現実の経済は、もっと複雑で多面的なものです。賃上げの重要性は認めつつも、それだけに頼るのではなく、様々な角度から日本経済の再生に向けて議論を深めていく必要があるのではないでしょうか。我々のような現役世代が、安心して暮らせる社会を創るために、私も微力ながら貢献していきたいと思っています!
それでは、次回もお楽しみに! 今週もよろしくお願いいたします。
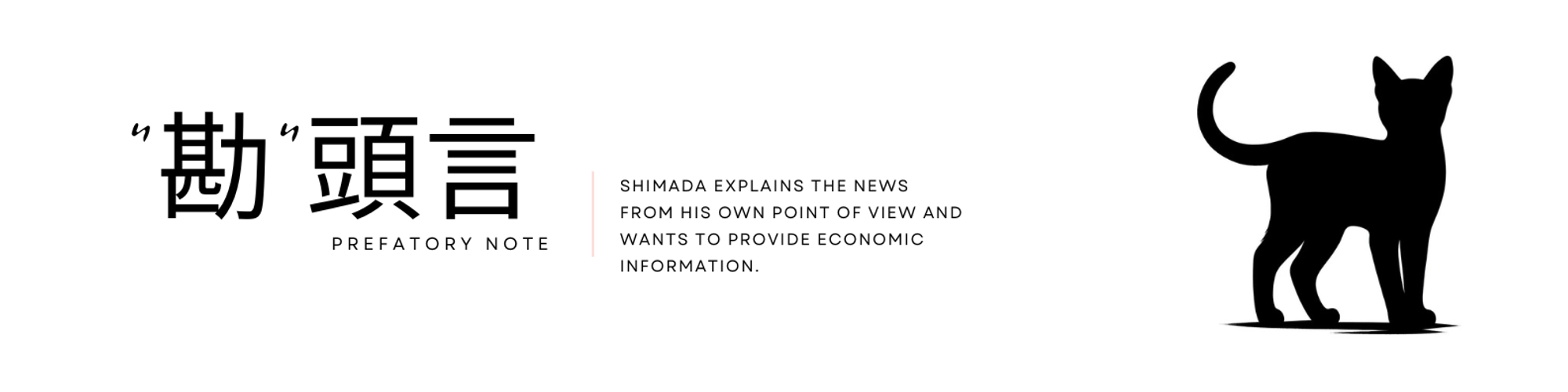 【“勘”頭言】数字を超えた価値――地域とともに生きる中小企業の力
【“勘”頭言】数字を超えた価値――地域とともに生きる中小企業の力
皆様、こんにちは。 ハンズバリュー株式会社の変革者・作家、島田慶資です。
私は日頃、事業再生の支援に携わる中で、数字に表れる「損益」だけでは測れない企業や組織の価値を強く感じています。特に地域の中小企業は、その地域特有の文化やコミュニティを支え、人々の日々の暮らしを成り立たせる大切な存在です。今回は、先日ご相談に伺った温泉旅館での光景を通じて感じた想いを、数字と地域の営みをめぐる視点からお話ししたいと思います。
駐車場で目にした活気ある日常
先日、事業再生を支援している温泉旅館様とのミーティングに伺った際、始業までの時間を旅館の駐車場で過ごしていました。そこでは、業者の営業車が元気よく到着し、従業員の方々が寮から笑顔で出勤し、ちょうどチェックアウトを終えたお客様が満足そうに旅館を後にしていくという、何気ないながらもとても活気に満ちた風景が広がっていました。
「この旅館が赤字か黒字か」という単純な数字の次元だけでは語れない、現場の“人の営み”が確かにここにある──そのことを改めて実感した瞬間でした。数値化された損益だけでは捉えきれない、そこで働く人と訪れる人とが紡ぎ出す生活の風景こそが、地域の中小企業の真の姿ではないでしょうか。
赤字・黒字を超える“人の営み”へのまなざし
企業として“採算”が重要であることは言うまでもありません。事業を継続し、従業員に給与を支払い、地域に貢献するためには、一定の収益を上げなければならないからです。
しかし、もしこの温泉旅館がなくなったらどうなるでしょうか。従業員は職を失い、寮がなくなれば生活する場所を失う人も出てきます。地域に集まるお客様が激減し、その土地が持つ独自の魅力や文化もまた、一緒に失われてしまうかもしれません。
代わりとなる施設をすぐに建てられるわけでもない以上、「赤字だから」「利益が出ないから」という理由だけで“人の営み”を切り捨てていいはずがないのです。
雇用の自由化と地域の現実
一方で、よく「東京には仕事がいくらでもある」「労働市場を自由化すれば流動性が高まる」といった声が聞かれます。確かに大都市には多様な仕事が集まり、流動性を高めることは経済全体の活性化につながる面もあります。
しかし、そこに住む人々全員が大都市に移住できるわけではありません。家族の都合や介護、あるいは個々の価値観・得意分野など、住む場所を容易に変えられない理由は数多く存在します。
仮に解雇要件が緩和され、企業にとっては採用や解雇がしやすくなるかもしれません。しかし、それが地域に根ざす中小企業とそこで働く人々にとって、必ずしもプラスに働くとは限らないのです。むしろ自由化の掛け声だけが先行し、実際には人が動きづらいまま雇用の不安定化が進む──そんな懸念も否めません。多くの人にとって仕事と生活が密接に結びついている以上、自由な移動を選択できる人はごく一部なのです。
政府と大企業の在り方への疑問
最近、石破総理が経団連に対して賃上げを要請しているというニュースを目にしました。もちろん、経済対策として賃上げが重要であることは明白ですが、ただ政府が大企業に頼るだけで解決する問題ではありません。
大企業はビジネスモデルの都合上、利益が出なくなれば拠点を閉鎖し、人員を引き上げる(主に解雇する)可能性が高いのも事実です。そうなれば、地域には“何も残らない”という事態も起こり得ます。だからこそ、政治の大きな役割として、自然に賃上げや雇用拡大が実現できるような経営環境やインフラを整備し、「地域で生きる人たちが働きやすい仕組み」を作っていくことが求められているのではないでしょうか。
地域に根づく中小企業の可能性
大企業が撤退し、地域が空洞化するケースは珍しくありません。その一方で、中小企業は大企業とは異なるかたちで地域とともに歩み、地域の文化や暮らしのなかで息づいてきました。売上が思うように伸びず、厳しい財務状況に陥ることもありますが、だからといってすぐに閉鎖するのではなく、再生の道を模索し、従業員や地域とのつながりを絶やさない努力を続ける企業も多いのです。
私たちのように事業再生をお手伝いする立場から見ても、この「粘り強さ」は大きな魅力です。
企業と地域が一緒に力を合わせ、生き残りの道を探ることで、新しい事業アイデアやサービスが生まれることもあるからです。そうした「人がいるからこそ成立する」営みこそが、中小企業の真の強さだと感じています。
数字だけでは割り切れない「暮らしと仕事の総合的なあり方」
中小企業が生き残ること、そして地域に根付くことは、そのまま地域の雇用や活気を維持することにつながります。ここで働く人たちの生活基盤を支え、また外からのお客様を呼び込むことで、新たな価値を生む土壌を育み続けられるのです。
私自身、これまで多くの企業再生を支援してきましたが、現場を訪れ、一人ひとりの社員や地域の方と話すほどに感じるのは、「数字の向こう側にある人々の物語」の大切さです。損益計算書や貸借対照表には表れにくい部分にこそ、本当に守るべき価値が存在します。
企業の再生とは単なる財務指標の回復ではなく、「暮らしと仕事の総合的なあり方」を模索し、地域の未来をデザインしていく行為だと思っています。
おわりに
これからも私たちは、事業再生をはじめとするあらゆる場面で中小企業の皆様を支援し、ともに悩み、歩み、地域の魅力を高めていくお手伝いをしていく所存です。現場を知り、目の前の人々の営みを理解しようとする姿勢を忘れずに、数字だけでは決して割り切れない側面にも目を向けること──それが、地域に根ざす中小企業の未来を守り、そこに暮らす人々の生活をより豊かにする鍵ではないでしょうか。
このように、“赤字か黒字か”という結果や数字だけでは測りきれない営みが、地域には確かに存在しています。私たちはそのかけがえのない価値を理解し、支え続けるために、これからも現場に足を運び、企業と地域の声に耳を傾けていきたいと思っています。
今週もよろしくお願いします。
 【実店舗に効く話】閑散期対策、焦りは禁物!
【実店舗に効く話】閑散期対策、焦りは禁物!
~お客様の「心」を読み解き、ピンチをチャンスに変える方法~
皆様、ご機嫌いかがでしょうか?ハンズバリュー株式会社の経営コンサルタント、津名久ハナコです。
クリスマス、お正月、新年会、バレンタインデー…と、美味しいイベントが目白押しでしたね!私も、ついつい食べ過ぎてしまい…最近、ズボンが少しきつくなってきたような…?(;^_^A
見て見ぬふりをしてきましたが、そろそろ現実と向き合わなければならないカウントダウンが始まっているようです…(涙)。
さて、今回はお客様からご相談いただく「閑散期対策」について、一緒に考えていきたいと思います!
皆様のご商売には、閑散期と繁忙期がありますでしょうか?繁忙期は、営業成績も良く、嬉しい悲鳴を上げていることでしょう。しかし、閑散期になると途端に売上が落ち込み、焦りを感じてしまう…という方も多いのではないでしょうか?先日も、温泉旅館の女将さんから、こんなご相談をいただきました。「閑散期に、何とかしてお客様を呼ぶ方法はないかしら…?」
閑散期と繁忙期、お客様は「同じ」ではない?!
ここで、まず考えなければならないのは「閑散期と繁忙期では、お客様は同じなのか?」ということです。
繁忙期には、その時期ならではの「お客様が来店する理由」があるはずです。
- 海水浴場の近くにある温泉旅館なら、夏休みは「海水浴を楽しみたい」お客様で賑わう
- スキー場の近くにある旅館なら、冬は「スキーを楽しみたい」お客様が来館
このように考えると、閑散期には繁忙期の「お客様が来店する理由」が、そもそも存在しないことが分かります。つまり、閑散期に繁忙期と同じお客様を呼び込もうとしても、それは難しいのです。
閑散期対策は、「現状の延長線上」にはない!
閑散期対策を考える上で、最も重要なのは「現状の延長線上に、答えはない」ということです。
繁忙期と同じお客様をターゲットに、同じ商品やサービスを提供し、同じような販促活動をしても、閑散期のお客様の心には響きません。
閑散期対策を成功させるためには「新しい客層」のお客様を「新しく獲得する」ことが必要なのです。
閑散期だからこそ、できること~「内部充実」のチャンス!~
「新しいお客様を獲得するなんて、難しい…」そう思われた方も、いらっしゃるかもしれません。しかし、閑散期だからこそ、できることもたくさんあります!
最も確実な対策は、閑散期を「内部充実」の期間と捉え、繁忙期に向けてじっくりと準備を進めることです。
例えば…
- 従業員の教育: 繁忙期にはなかなか時間が取れない、社員教育や研修を実施する
- 新商品・サービスの開発: 新しい客層をターゲットにした、商品やサービスを開発する
- 研究開発: 新しい技術や、ビジネスモデルの研究開発に取り組む
- ホームページやSNSの刷新: 繁忙期に向けて、情報発信力を強化する
- 設備のメンテナンス: 普段、手が回らない設備のメンテナンスを行う
このように、閑散期を「内部充実」の期間とすることで、繁忙期により大きな成果を上げることが可能になります。
「新しいお客様」開拓への挑戦も、視野に入れよう!
もちろん、「内部充実」だけでなく「新しいお客様」開拓に挑戦することも非常に重要です。
閑散期に、どのようなお客様なら自社の商品やサービスに魅力を感じてくれるのか?どんなニーズがあり、何を提供すれば喜んでいただけるのか?徹底的に考え新しい顧客層にアプローチしていく必要があります。
例えば、先の温泉旅館の例で言えば…
- 夏が閑散期なら、「避暑地」としての魅力をアピールし、涼を求めるお客様をターゲットにする
- 冬が閑散期なら、「雪見露天風呂(貸し切り風呂状態)」や「冬の味覚」を前面に打ち出し、冬ならではの魅力を体験したいお客様を呼び込む
など、閑散期ならではの強みを活かした新しい戦略が必要になります。
閑散期を「飛躍のチャンス」に変えよう!
閑散期は、決して「売上が上がらない、我慢の時期」ではありません。閑散期を、どう捉えどう過ごすかで、その後のビジネスの成長は大きく変わってきます。
閑散期を「内部充実」と「新しいお客様開拓」のチャンスと捉え、積極的に行動することで、繁忙期により大きな成果を上げることができるはずです。「閑散期の過ごし方が分からない」「新しいお客様の開拓方法が分からない」という方は、ぜひハンズバリューにご相談ください!私たちと一緒に、閑散期を「飛躍のチャンス」に変えましょう!
ぜひご参考ください。
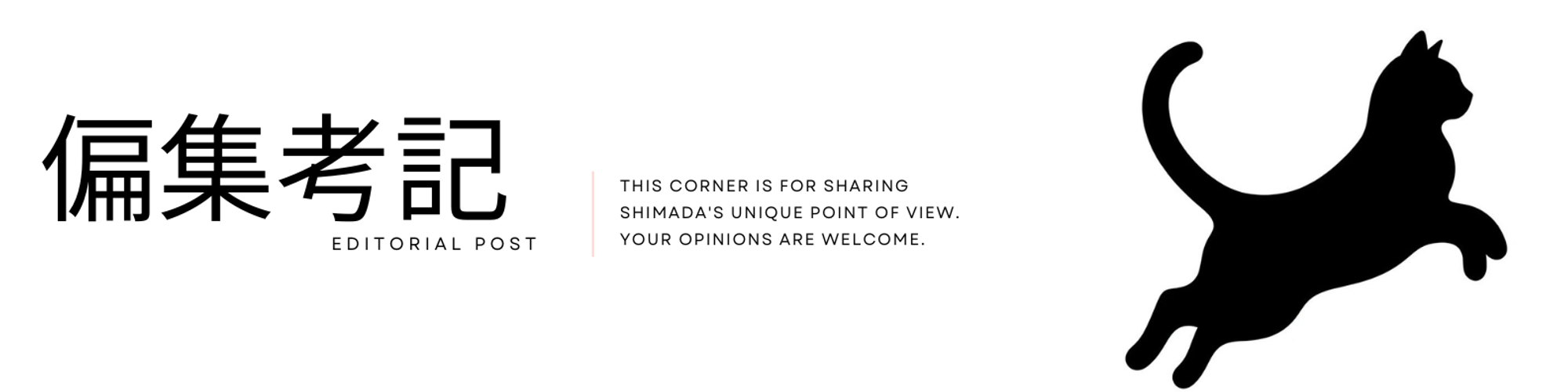 【偏集考記】売上100万円という情報に意味があるのか?
【偏集考記】売上100万円という情報に意味があるのか?
ハンズバリュー株式会社の変革者・作家である島田慶資です。
最近、ある経営者のお客様から「会計事務所に試算表の読み方を教わってはいるものの、まったく理解できない」というご相談をいただく機会がありました。内容を詳しくうかがうと、会計事務所の方は損益計算書や貸借対照表の仕組み、さらには分析方法について、一生懸命に説明はしているようです。
しかしながら経営者の皆様にとっては、「売上が100万円でした」と言われたところで、いったい何を考えどう意思決定すればいいのかが分からない。
「それが分からない」ということこそがご不満の正体であり、目の前の数字の読み方自体をなかなか習得できない大きな要因になっていました。
たとえば売上が100万円、経費が50万円でした、と数字を聞かされただけでは「それで、どうするのか?」「この数字は良いのか悪いのか?」「この先どういう打ち手が必要なのか?」といった部分が見えてきません。事実、数字を表面的に把握しても、そこに至るまでのプロセスや要因が分からなければ、ただの報告レベルで終わってしまい、経営判断に役立つ“本当の情報”として活用することが難しいのです。稲盛和夫先生は「数字を一つ言われたら、その内側から十の問題を見つけ出せ」とおっしゃっていますが、それには売上や経費を枝葉に分解し、それがどのように積み上がっているのかをしっかりと把握する姿勢が求められます。
たとえば多店舗展開をしている企業であれば、各店舗ごとの売上や経費を細かく見られなければ、どの店舗が優良でどの店舗に問題があるのかが分かりません。売上合計が100万円という数字自体に意味がないわけではありませんが、それぞれの店舗や部門の貢献度合いが曖昧なままでは、次の施策に落とし込むことが難しいのです。もし事業部を複数抱えている場合でも同様で、事業部ごとの売上・経費・利益が正確にわからなければ、「どの事業部に強みがあり、どこを改善すべきか」がつかめず、結果として対策もぼやけてしまいます。
実際に中小企業の現場を見ると、部門別・店舗別の管理体制をきちんと整備しているケースはまだ多くありません。これは「管理コストが増えてしまう」「複雑になりすぎて運用が負担になる」といった懸念が大きな理由の一つです。当社(ハンズバリュー株式会社)でも、以前は会社全体の数字だけをざっくり管理し、「全体としてはプラスだから大丈夫だろう」と判断していました。しかし、そうしたやり方では10年後に描いているビジョンに対して、スピード感を持って行動できないことを痛感しました。そこで部門ごとに売上・利益を管理し、何がどこから生まれ、どこにボトルネックが潜んでいるのかを明確に把握できる仕組みを導入しました。
もちろん、部門別管理を徹底するには、データの整備や社内体制の変更にコストや手間がかかります。
しかしその一方で、「実はあの店舗は商品の動きが鈍い」「この事業部は利益率が高い割に販路が少ない」といった具体的な気づきを得やすくなり、スピーディに次の一手を打てるようになります。結果として、経営改善だけでなく、社員の意識向上やモチベーションアップにもつながりました。
結局のところ「数字が分かる」というのは、単に売上高や経費の額面を理解することではなく「その数字がどう積み上がっていて、どこに問題やチャンスが潜んでいるのか」を把握できる状態を指します。そしてそのためには、部門や店舗といった現場に近い単位での分析が欠かせません。今後も当社としては、単なる数字の把握にとどまらず、そこからどのように意思決定や行動につなげていくのか、社員全員が考えられる文化を醸成していきたいと考えています。数字は経営の羅針盤です。その使い方を間違えないためにも、経営者が自ら進んで“数字の内側にある情報”を取りに行く姿勢を持つことが求められているのではないでしょうか。
それでは、またお会いしましょう。 今日も一日、良い学びを。

