皆様、こんにちは! ハンズバリュー株式会社の島田です。
メールマガジンの感想、お待ちしております! 「読んでるよ」と言っていただければ励みになります(^_^)
目次
独り言コーナー
❶事業協同組合を設立しようとしていますが、考えるべき事柄が想定以上に多く出る物でアタフタしております。 挑戦しているからこそ、障害に出会えるのだと前向きに捉えています。ストレスは友達ですね。
❷大雪の被害はないでしょうか?プリウスのフロントワイパーを上げずに一晩雪が積もったところ、運転席側のワイパーが故障しました。 初めての故障で、日々の管理の重要性を学ばせていただきました😂
❸ジョブチューンで紹介されたモスバーガー。翌日にホットチリドックを食べたくなり、訪問すると大行列。 たしかにソーセージは美味しい。価格以上の価値を感じました。マクドも値上がりしているので、今後はモスバーガーも選択肢に上がります。
❹伝説の家政婦さんの料理レシピ本で竜田揚げをつくりました。揚げ焼きでカリッと揚がったのは感動しました。 味付けは、甘酢あん掛けにしたところ、坊やから大クレーム。子供の味覚には合わなかったようです。
❺坊やがお友達のおうちへ初出張。大変楽しかったようで「帰りたくない」と大泣きしながら帰宅しました。 遊んでいただけるお友達がいることがありがたいです。感謝しています。
島田の気になるニュース
❶基礎控除の引き上げについてのド正論。少数与党の政府の発言が二転三転して、本当に信用できません。
財務省は年収の壁引き上げを何とか骨抜きにしたいのか
❷ブロッコリーを摂取すれば白髪が防げるというわけではないのでしょうが興味深いですね。ブロッコリー売れそうです。
名古屋大学が「白髪を防げる」天然の抗酸化物質を発見
❸面白い統計だと思いませんか?人材派遣会社の出現率が圧倒的。人間性が求められますね。
退職代行モームリ、最も“使われた企業”とは? トップ40社の業種・回数を公表
❹確かに納得。オウム騒動が現代にあったらば、同様の炎上していたでしょうね。炎上前になんとかならなかったのか、考えますね。
フジ炎上、TBSオウム騒動から29年 スポンサーの常識は様変わり
❺弱みしかないと思っていたら、価値をわかる人が評価してくださった事例。事実は解釈次第でどうにも見える典型例ですね。 「人が全然来なかった」村の小さなスキー場に長蛇の列 豪雪地のゲレンデはまるでバックカントリー
利用者の少なさ逆手にとった策に「変われば変わる」 職員もビックリ
【今週の経済入門】みんなで節約すると景気が悪くなる?!『節約のパラドックス』って何?
皆様こんにちは、ハンズバリュー株式会社の秘書・勝頼ヒデコです。 いつもメルマガジンをお読みいただき、ありがとうございます。

先日、米沢市で開催された雪まつり、今年は大雪の影響で、来場者数が予想の半分以下だったそうです。ニュースを見て、後輩のハナコも「雪まつり、お宿様が観光客の皆様をもてなそうと考えていたのでに残念…」と肩を落としていました。地域経済への影響も心配です…。景気が悪いと、ついついお財布の紐を固く締めてしまいがちですが、実は、それがさらに景気を悪化させる可能性がある、ということをご存知でしょうか?
今日は、そんな「節約のパラドックス」について、一緒に学んでいきましょう!
本日のテーマ『節約が経済を悪化させる?!』
「節約のパラドックス」とは、経済学の用語で「みんなが節約するとかえって経済全体が悪化し、結果的に個人の貯蓄も増えない」という現象を指します。 「えっ、節約は良いことじゃないの?」と、ハナコ。でも、考えてみれば当たり前のことかもしれません。
例えば、Aさんが「景気が悪いから外食を控えて自炊しよう」と考えたとします。すると、Aさんがいつも行っていたレストランの売り上げは減ってしまいます。レストランの売り上げが減るとレストランの社長様は、従業員の給料を減らしたり、新しい食材の仕入れを控えたりするかもしれません。
そうすると、従業員や食材を納入している業者のお金も減ってしまいます。そして、お金が減った従業員や業者は、さらに消費を抑えるようになります…。
このように、一人ひとりの節約行動が、巡り巡って、経済全体の需要(お金の流れ)を減らし、企業の生産や利益を下げ、最終的には、私たちの給料や雇用にも悪影響を及ぼしてしまうのです。 まさに「お金は天下の回りもの」ということわざの通りですね。ハナコも「なるほど…、節約しすぎると、自分たちの首を絞めることにもなるんですね…」と神妙な面持ちで頷いていました。
特に、厳しい経営環境にある地域では「節約のパラドックス」の影響がより深刻になる可能性があります。みんなが消費を控えてしまうと、地域経済はさらに冷え込み、悪循環から抜け出せなくなってしまいます。
では、どうすれば良いのでしょうか?
もちろん、無駄遣いを推奨するわけではありません。しかし、過度な節約はかえって経済を悪化させる可能性があることを理解しておく必要があります。
大切なのは、「賢くお金を使う」 ことです。例えば
- 地元の商店街で買い物をする
- 地域の特産品を購入する
- 地域のイベントに参加する
など、地域経済にお金が回るような消費行動を心がけることが重要です。
また、当然ながら政府の役割 も重要です。政府は、減税や給付金、公共事業などを通じて、積極的に経済を刺激し、需要を喚起する必要があります。(国民民主党の基礎控除の引き上げは大変期待しております。)
ハナコも、「私も、できることから地域を応援したい!」と、意気込んでいました。まずは、地元の美味しいものを食べに行くことから始めようかな、とのことです😊
私たち一人ひとりの消費行動が、地域経済、ひいては日本経済全体を左右します。 「節約のパラドックス」を理解し、賢くお金を使うことで、より豊かな社会を築いていきましょう!
それでは、次回もお楽しみに! 今週もよろしくお願いいたします。
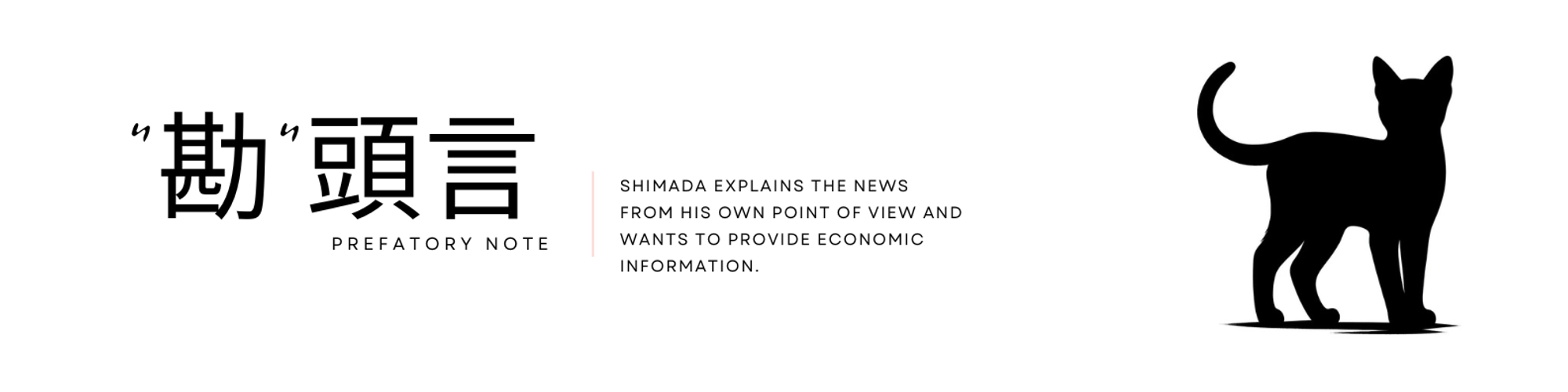 【“勘”頭言】「生きている土俵が違う」―地域を支える中小企業の覚悟―
【“勘”頭言】「生きている土俵が違う」―地域を支える中小企業の覚悟―
皆様、こんにちは。ハンズバリュー株式会社の変革者・作家、島田慶資です。
先日、あるお客様から悲痛なご連絡をいただきました。
お客様は経営改善計画を策定し、まさにその計画を実行している最中でした。にもかかわらず、単月の目標が未達に終わりそうだということで、金融機関からその挽回策について長時間にわたる電話を受けたというのです。
電話口で大声で詰め寄るように話すため、従業員の方々にも聞こえてしまい、現場の士気にも大きく影響が出てしまいます。さらに驚くべきことに、金融機関側は「経営状態が厳しい企業には厳しく対応してもよい」とあからさまに明言していたといいます。
本当に信じられない話です。
中小企業が担う地域への使命
中小企業には、地域の雇用を守り、文化や伝統を継承し、そしてその地域の魅力を未来へとつないでいくという極めて重要な役割があります。大企業にはないきめ細やかさや地域密着性が強みであり、何よりも地域に根ざして共に成長しようという想いが宿っています。
しかしながら、金融機関の方々はあくまでサラリーマン。企業のオーナーシップを持っているわけではなく、組織としての論理や指示に従う立場です。だからこそ、「厳しく対応してもいいんだ」という表現が出てきてしまうのでしょう。彼らは“背負うもの”の質が違います。
私たち経営者や中小企業家が背負うものは、ただの数字や書類の上の話ではありません。そこには家族や従業員の生活、地域に生きる人々の未来まで含まれています。生きる土俵がまったく違うのです。
金融機関との関係とその影響
もちろん、金融機関との良好な関係は事業にとって大切です。
信用や資金調達を円滑に行うためにも、計画の達成度をしっかり示す必要があるでしょう。しかし、その過程であまりにも一方的な対応を取られれば、企業の士気をそぎ、地域の経済基盤を揺るがしかねない深刻なダメージを与えてしまう可能性も否定できません。
このような状況でも、中小企業の経営者には、日々前を向いて問題を解決し、従業員と共により良い未来を築いていく責任があります。
たとえ単月の数字が計画通りにいかなかったとしても、そこで諦めるわけにはいかない。 地域で事業を続ける以上、その土地に育てられた恩を返す覚悟で、粘り強く改善策を講じ、次の行動・取組を起こしていく必要がでているでしょう。
地域の未来を見据えた経営
私たちは、地域の人々の生活を守り、企業を取り巻く関係者と共に、より良い社会を育てていきたいと願っています。
大都市と同じ感覚で“厳しいからといって潰してしまう”ようなやり方では、地域そのものが失われてしまうかもしれない。だからこそ、一企業としてだけではなく、地域全体の未来を見据えた経営が求められるのです。
本当に苦しいときこそ、いかに全社員が協力し合い、前を向いて取り組めるかが試されます。やり方を変えてみる、新たな技術やサービスを模索してみる──さまざまな選択肢があります。
そこに金融機関の方々も理解を示し、応援する姿勢を見せてくれれば、どれほど心強いことでしょう。
おわりに
私たち経営者は、一朝一夕では得られない覚悟と責任を背負っています。
だからこそ、声を大にして言いたい。「生きている土俵が違う」──この言葉には、中小企業経営者の想いや苦労、そして使命がすべて詰まっているのです。今後も、地域を愛する中小企業家の皆様と手を携えながら、この土俵で戦い続けていく覚悟です。
お客様からの悲痛な連絡でより一層、覚悟が固まりました。今週もどうぞよろしくお願いいたします。
 【実店舗に効く話】値上げ成功のカギは、顧客教育にあり!
【実店舗に効く話】値上げ成功のカギは、顧客教育にあり!
~「価値」を可視化し、お客様の「感度」を上げる方法~
皆さん、こんにちは。 ハンズバリュー株式会社のコンサルタント、津名久ハナコです。
先週のバレンタインデー、皆さん、いかがお過ごしでしたか?私は、先輩方から、た~くさんのチョコレートをいただきまして…あっという間に、美味しく消化してしまいました!(笑)
14日に偶然お会いしたお客様からも「いつもありがとう!」と、素敵なチョコレートをいただいて本当にチョコレート三昧の幸せな週末を過ごさせていただきました。皆様、ごちそうさまでした!…って、体重計に乗るのが怖い今日この頃です…。(;^_^A
さて、甘~いチョコレートの余韻はさておき…先日、お客様から「値上げ」に関するご相談をいただきました。今日は、その時に私がお客様と共有した「値上げを成功させるための秘訣」を皆さんに伝授したいと思います!
「価値を上げる」だけでは、不十分?!
「値上げをするなら、同時に価値も上げなければならない」
…これは、よく言われることですよね。もちろん、その通りです!しかし「価値を上げる」だけでは実は不十分なのです。
なぜならお客様がその価値を感じてくれなければ意味がないからです!
例えば、あなたが最高級の素材を使い熟練の職人が手間暇かけて作った素晴らしい商品を提供していたとします。しかし、お客様がその価値を理解できなければ「ただ高いだけの商品」としか認識されません。
つまり、お客様の「感度」が重要なのです。あなたが「10」の価値を提供していても、お客様の感度が「1」しかなければ「1」の価値しか伝わらないのです。
お客様の「感度」を上げるには、「可視化」と「教育」が重要!
では、どうすればお客様の「感度」を上げることができるのでしょうか?
ここで重要なのが「価値の可視化」と「お客様の教育」です!
「可視化」とは、お客様に、自社の商品やサービスの価値を、分かりやすく具体的に示すことです。
「教育」とは、お客様に、自社の商品やサービスの価値を、深く理解していただくことです。
この2つを徹底することで、お客様はあなたの提供する価値を正しく認識し、値上げにも納得してくれる可能性が高まりますよ🥰
飲食店を例に、「可視化」と「教育」を実践!
例えば、飲食店を経営しているとしましょう。あなたは、地元の農家から直接仕入れた、新鮮なお米を使っています。しかも、毎日その日に使う分だけを精米し、つきたてのご飯を提供しています。
これは、非常に素晴らしい取り組みですよね!しかし、この取り組みをお客様に「可視化」し「教育」しなければその価値は十分に伝わりません。
「可視化」の例
- 店内に農家さんの写真やお米の生産過程を紹介するPOPを掲示する
- メニューに「〇〇さんの作ったつきたてコシヒカリを使用」など、具体的な情報を記載する
- 精米機を店内に設置しお客様の目の前で精米する
「教育」の例
- 「つきたてのお米は、なぜ美味しいのか?」をスタッフがお客様に説明する
- お米の品種や農家さんのこだわりをブログやSNSで発信する
- 「美味しいお米の炊き方教室」を開催する
これらの取り組みを通じて、お客様は「このお店のご飯は、特別なんだ!」と、価値を実感することができます。そして、多少の値上げにも納得してくれる可能性が高まるのです。
お客様に「価値」を伝え、共に成長する!
値上げは、企業にとって非常にデリケートな問題。しかし顧客心理を理解し「価値の可視化」と「お客様の教育」を徹底することで値上げを成功させ、さらなる成長へと繋げることができます。
「自社の価値を、どう伝えれば良いか分からない」「お客様の教育方法が分からない」という方は、ぜひハンズバリューにご相談ください!私たちと一緒に、お客様に愛され共に成長できる企業を目指しましょう!
ぜひご参考ください。
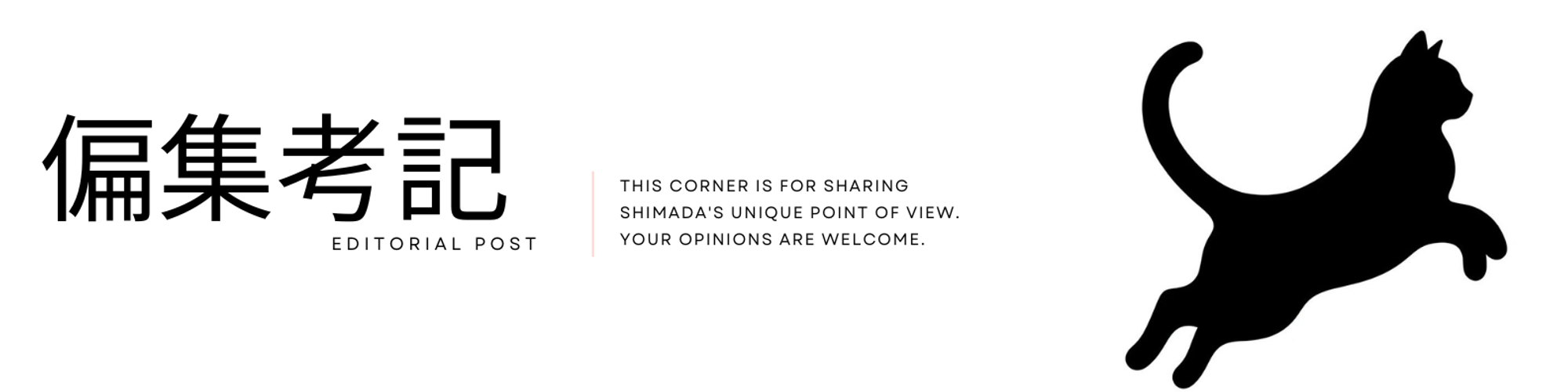 【偏集考記】「DXは企業の存在意義を問い直す変革」
【偏集考記】「DXは企業の存在意義を問い直す変革」
皆様、こんにちは。 ハンズバリュー株式会社の変革者・作家、島田慶資です。
先日、DX推進計画策定支援事業の成果報告会で山新観光様との共同登壇を行い、DXの本質を改めて考える機会を得ました。私が強く感じたのは、DXは単なるシステム導入や業務効率化ではなく、「企業が何のために存在し、どのような価値を社会に提供するのか」を根本から問い直す――つまり、企業理念を確立し、それに沿って全社を変革していく取り組みだということです。
理念がしっかりと定まっていなければ、どれほどデジタル施策を導入しても一貫性が保たれず、結局は部分的な改善にとどまってしまうと痛感しています。
※登壇いただいた山新観光 佐藤課長様の発表内容を引用しながら、ポイントを整理いたします。
DXは経営理念から始まる包括的な変革
山新観光様においては、エクセル管理の手間や旅行予約システムの改善など、どうしても“個別の課題”が先に浮上しがちでした。しかし本来のDXは、会社が提供する価値の大枠を見直すことから始まります。「どのような体験をお客様に届けるか」という根源的な問いに向き合うことで、ビジョンに合った新たな経営理念を明確に掲げられました。
この理念が全社的に共有された結果、旅行部門はもちろん、その他の事業領域でも目指す方向が一本筋で通り、具体的なデジタル施策や業務改革にも一貫性が生まれたのです。企業が何を目指し、どのように社会に貢献したいのか――その原点を明確にしてこそ、システム導入や業務効率化といったDXの取り組みが本来の力を発揮します。
現場と経営者の温度差を丁寧に埋める
経営トップがいかに素晴らしいビジョンを描いたとしても、現場との間に温度差があればDXは進みません。日々の業務に追われる社員にとっては、「新しい取り組みで自分の仕事はどう変わるのか」「お客様にどんな価値が生まれるのか」という具体像が見えにくいと、計画自体が形骸化してしまいます。
そこで大切なのが、全社的な理念を軸にしつつ、実務レベルでのメリットや変化を丁寧に伝えていくプロセスです。私自身もアドバイザーとして伴走する際には、経営者の思いと現場の課題をつなぎ、双方が納得する形で一歩ずつ改革を進められるよう心がけています。
社員・顧客・社会の三方を満たす指標を育てる
DXの成果を「売上」や「利益」のみに求めてしまうと、短期的なコスト削減に走り、社員のモチベーションやお客様への価値提供がおろそかになる恐れがあります。山新観光様が重視していた「労働生産性」という指標は、会社の成長とともに社員の待遇やモチベーション向上も目指すものでした。
社員・顧客・社会の三方を満たす基準を定めることで、DXの取り組みが長期的かつ持続的に機能するようになります。企業理念をベースにこうした指標を設けることで、経営の方向性がブレず、企業文化や価値観を深く掘り下げるDXへとつながっていくのです。
今回のトークセッションを通じて、私自身もDXとは「企業の存在意義を問い直し、それをデジタル技術と結びつけながら、社員・お客様・社会の幸せを同時に追求していく総合的な変革」であると、改めて強く認識しました。理念と現場が噛み合っていなければ、一貫性ある変革を実現することはできません。
今後も私は伴走型の支援を通じて、企業が大切にしている価値観をしっかりと見極めながら、皆様と共により良いDXを実現していきたいと考えています。誰もが存在意義を感じられる企業づくりを目指し、デジタル技術がその力を最大限発揮できるよう、日々研鑽を積んでまいります。
それでは、またお会いしましょう。 今日も一日、良い学びを。


