皆様、こんにちは! ハンズバリュー株式会社の島田です。
メールマガジンの感想、お待ちしております! 「読んでるよ」と言っていただければ励みになります(^_^)
目次
独り言コーナー
❶ITC南とうほく事業協同組合を設立しました。理事長は島田で、副理事は弊社技術顧問の菊地です。 山形・福島のデジタル経営をより一層推進します。ご相談、お待ちしております!🐈
❷家庭のWi-Fiが弱すぎるため、楽天モバイルのテザリングを活用しています。 しかしながら、電波が弱いせいかテザリングでも物足りない。根本的な解決が必要です。スターリンク欲しくなりますね!
❸しかしながら、永遠と雪が降りますね。今年は例年並みと聞いていましたが、集中的に降雪するように感じます。少し前まで小春日和でしたが…。 異常気象は経営環境の変化に組み込むべき何でしょう。そう考えると、大雨や大雪はBCPではなく、通常の経営計画に組み込まれるべきなのでしょう。学びですね!
❹ある事業者様より、会社の実力をどのように評価すれば良いのかというご相談をいただきました。 評価方法はいくつかありますが…利益+役員報酬で図ることも一つの手段でしょう。結局のところ、会社に利益を残すか、個人で取るのかの違いに過ぎませんよね。
❺坊やが「お父さんと一緒のジャケット着たい」「自転車を一緒に乗りたい」と可愛いことを言っていました。 自社やコンサルや社長としての10年ビジョンの策定などはしていましたが、プライベートの未来はまったく意識していませんでした。そういう未来も良いですね。
島田の気になるニュース
❶デフレから脱却できるかどうかの瀬戸際であることは間違いないでしょう。まだまだ景気が回復していると言えません。 積極財政と金融緩和が必要なのですが…。政府の方針に期待が持てないのは島田だけでしょうか。
【25.1.31】DOR152号(2024年10~12月期景況調査)を発表しました
❷少し古い記事で恐縮です。単なる労働力不足の解消を目的に実施。人間性の欠如を感じます。 大学院時代には研究に専念していました。学生の本分は学びを深めること。そうは思っていないんでしょうね。
星野リゾート、大学1年生にも内定 早期採用で人材確保
❸ネットのレシピを見ていると本当かな?と思いながらも試したくなりませんか? 僕が毎日のお料理を続けていられるのも、好奇心があるからだと思います😂
【キユーピー公式】作り方がシンプルすぎるサラダチキン / 漬けてレンジに入れるだけ!!
❹僕の故郷の地銀「四国銀行」の至宝とされる誓約書。万が一、”取引に不正があった場合は私財で弁償し、さらに切腹することを誓ったもの”とのこと。 頭取以下全従業員23人が、連署して血判を押しているってのがすごい!現代では考えられれないですが、覚悟は伝わります。すべての金融機関にコピーを送りたいですね。
誓約書
❺事業再生をわかりやすく解説しているブログ。全体像を抑えるには最適かと思います。 ただ、一行が大変重たい内容になっています。行間を読んで共感できる方は、同業者ですね。
事業再生をドラゴンボールで解説する
【今週の経済入門】友達の輪で変わる未来!?『経済的つながり』のチカラ
皆様こんにちは、ハンズバリュー株式会社の秘書・勝頼ヒデコです。 いつもメルマガジンをお読みいただき、ありがとうございます。

お金持ちとそうでない人の間の「友達の輪」 に所得が大きく関係していたことが研究で判明しました! ちょっと難しいけれど、私たちの未来に大きく関わるかもしれない、そんなお話をわかりやすく解説します🧐
参考: One key to earning a higher income: Rich friends in childhood
本日のテーマ「友達の輪」が格差をなくす?
ハーバード大学やスタンフォード大学などの研究者たちが、Meta社(旧Facebook)と協力して大規模な調査を行った結果、驚くべき事実が明らかになりました。
それは「低所得層の子どもでも高所得層の友達が多いと、将来の収入が高くなる」 ということです。
「えー、そんなことあるの?」と、ハナコも最初は半信半疑でした。 でも、この研究、ただのアンケート調査ではありません。科学雑誌Natureにも掲載された、信頼性の高い研究なんです。
では、なぜ「友達の輪」が、将来の収入に影響を与えるのでしょうか?研究者たちは、そのメカニズムをいくつかのポイントで説明しています。
まず「情報」 です。高所得層の友達が多いと、良い学校や仕事、投資など、将来の成功につながる情報が入ってきやすくなります。 ハナコも、「確かに、成功している友達から、刺激を受けることって多いかも!」と納得していました。
次に「能力」。これは、勉強の習慣やスキルなど、将来の収入を左右する能力のことです。 研究によると、高所得層の子供たちは、低所得層の子供たちよりも、週に平均して約5時間も多く読書をしているそうです。高所得層の友達が多いと学習習慣が自然と身につき、学力向上につながる可能性があります。
さらに「考え方」。社会で生きていく上でのルールやマナー、価値観のこと。 例えば、高所得層の友達が多いと「起業してリスクを取ることは、悪いことではない」という価値観に触れる機会が増えます。 研究によると年収数千万円以上の起業家と交流があるグループでは、起業に対するリスク許容度が42%も上昇するそうです。
上記の要因が複合的に作用することで「経済的つながり」は、将来の収入に大きな影響を与えると考えられています。実際、研究では「学校の質」や「雇用機会」「家族構成」といった従来の要因よりも「経済的つながり」の方が、収入に与える影響が大きいことが示されています。
ハナコの疑問「でも、どうやって『友達の輪』を広げればいいの?」
ハナコの疑問はもっとも!研究者たちは地域ごとの「経済的つながり」の格差についても調べています。
例えば、とある都市部では、低所得層の約半数が高所得層と友達関係にあります。 その結果、低所得層の平均年収は34,000ドルとなっています。
一方、とある地方では、低所得層で高所得層と友達関係にあるのは約3割で平均年収は24,700ドルと都市部よりも低くなっています。
この違いは、どこから生まれるのでしょうか? 研究では「制度的な障壁」に着目しています。具体的には「出会いの機会」 と 「友達になるバイアス」 です。
「出会いの機会」とは、文字通り、異なる所得層の人々が出会う機会のこと。例えば、住宅価格が高い地域では低所得層が住むことが難しく、高所得層との出会いの機会が少なくなります。また、学校選択制を導入している地域では、低所得層が高所得層の多い学校に通うことが難しくなる傾向があるでしょう。
「友達になるバイアス」とは出会ったとしても友達になるかならないか、ということです。例えば、課外活動費が高いと低所得層の子供は参加できず、高所得層の子供との交流が生まれにくくなります。また、学術的な会話の頻度が高いほど、異なる所得層の間で友達関係が生まれやすいという研究結果もあります。
つまり「経済的つながり」を広げるための環境整備が、格差縮小の鍵になり得るということです。 低所得層と高所得層が自然に交流できる場や機会を増やすことが、将来の収入格差を改善する一助になります。
地域コミュニティの活性化などの制度や環境の改善を通じて「出会いの機会」を創出し「友達になるバイアス」を和らげる取り組みが求められます🧐
まとめ
「経済的つながり」は、格差解消の万能薬ではありません。しかし、格差をなくすための重要な手がかりであることは間違いありません。
より公平で、誰もがチャンスをつかめる社会を創るために、何ができるのかを真剣に考える必要があるのではないでしょうか。この研究結果は日本の首都圏と地方の格差が、これまで以上に開いていく可能性を示しているような気がしてなりません。私は経済に明るい政治家が日本のグランドデザインを描き直してくれることを望んでいます😌
それでは、次回もお楽しみに! 今週もよろしくお願いいたします。
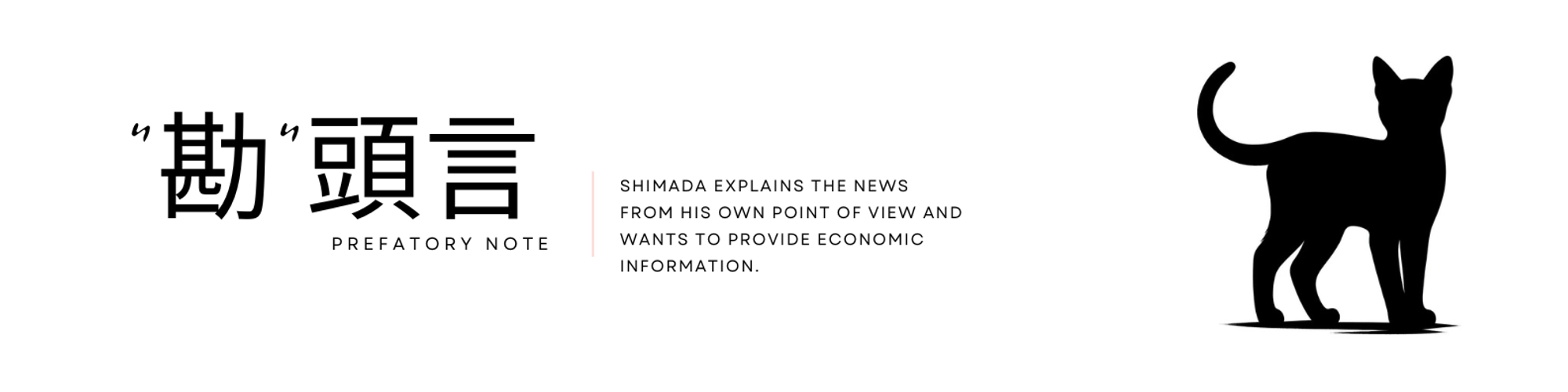 【“勘”頭言】DXは“自社が何者であるか”を問い直すためのきっかけ
【“勘”頭言】DXは“自社が何者であるか”を問い直すためのきっかけ
皆様、こんにちは。
ハンズバリュー株式会社の変革者・作家、島田慶資です。
先日、2月7日(金)に工業技術センターで「DX推進計画策定事業の成果報告会」が開催されました。私は、旅行業を代表して参加されたある企業様とともに登壇し、どのようにDX推進計画を描いたのかを深掘りいたしました。
デジタル導入は“変革”を実現するための一要素
世間一般では「DX(デジタルトランスフォーメーション)」と聞くと、どうしても「最新のITツールを導入すればよい」という印象が先行しがちです。しかし、本質はそこではありません。DXは単なるシステムやアプリの使い方を変えるという話ではなく、「社会やお客様の視点で企業がどう変わるのか」を最初に考える取り組みなのです。
さて企業はなぜ変わらなければならないのでしょうか。その答えは、「お客様が変わっていくから」です。時代の流れとともに、求められる商品やサービスは常に進化します。以前は必要とされていた価値が、ある時期を境に“古い”とみなされることも珍しくありません。そうした移り変わりに対応できなければ、企業は取り残されてしまうでしょう。だからこそ、私たちには“変革し続ける力”が求められるのです。
デジタル技術は、そうした変革を後押しする非常に便利なツールでもあります。スマートフォンやパソコン、インターネット環境が普及したいま、それらを活用しない選択肢は考えにくいでしょう。では具体的に、どのように自社を変革していくのか。そのキャンバスこそがDX推進計画にほかなりません。
“等身大の自分”を知ることが変革を進めるカギ
DXを考えるうえで非常に重要なのが、「自社が何者であるか」を理解することです。言い換えると“等身大の自分自身”をしっかり見つめ直す作業ともいえます。
– 自分たちは何を使命としているのか
– どのような強みや特性を活かしてお客様に貢献したいのか
– これから先、どんな変化を遂げたいのか
これらが曖昧なまま無理に“デジタル化”を進めても、方向性が定まらないまま振り回されるだけで終わってしまうかもしれません。逆に、自社の立ち位置や価値観がはっきりしていれば、その筋に沿った形で変革を起こしやすくなります。
報告会に登壇した企業様も、まずは「私たちのサービスは、お客様にとってどんな意味があるのだろう?」としっかり考えたうえでDXを検討しました。その結果、単なるデータ分析や予約システムの刷新だけでなく、「旅行者が本当に求めている体験は何か」「地域や社会に対してどのような付加価値を提供できるか」という問いに向き合い“企業としてあるべき姿”を描く大きなきっかけとなりました。
変化を楽しむために──DXは“自社らしさ”を活かす舞台
DX推進の最大のポイントは「お客様の変化に対応しながら、自社の軸をどう通すのか?」にあります。世の中がスマートフォンやインターネットで便利になるほど、私たちの働き方やサービス提供の手法も自由度が増してきます。言い換えれば“お客様に喜ばれるサービスを生み出すヒント”がデジタル空間のなかにたくさん詰まっているということでもあるでしょう。
しかし、そのヒントを見つけるためには、自社が大切にする価値観や強みを踏まえたうえで「どのようにデジタルを取り入れるか」を考えなければなりません。ここで企業の根っこにある「基本的な価値観」や「等身大の自分自身」を理解していると、DXをきっかけに「自分たちらしさを最大化するための変化」を楽しめるはずです。
一方で、その“自分らしさ”が曖昧なままでは、目的も手段もあやふやになり、時代の波に振り回される危険性が高まります。結局、DXで大事なのは“自社の本音や軸を持ちながら社会とお客様の声をくみ取り、新しい価値を作り出す”ということです。
おわりに
DXとは、技術の導入そのものがゴールではなく、お客様の変化に合わせて自分たちも変わり続けるための“起爆剤”と言えるでしょう。
そして、その変化を持続的に楽しむためには、「自分たちが何者なのか」を知ることが不可欠です。
2月7日の成果報告会では、まさに「自社の軸」を見つめ直す過程がDX計画の大きなポイントとして語られました。これからの時代、社会やお客様のニーズはますますスピーディーに変化していきます。そのなかで生き残り、さらには飛躍していくためにも、ぜひ自社の存在意義を再確認しながら“等身大の姿”でデジタル技術を取り込み、時代とともに変わっていく喜びを分かち合っていきたいものです。
今週もよろしくお願いします。
 【実店舗に効く話】ちょっと待って!その値引き、本当に必要ですか?
【実店舗に効く話】ちょっと待って!その値引き、本当に必要ですか?
~中小企業が絶対に「安売り」をしてはいけない理由~
皆さん、こんにちは!ハンズバリュー株式会社の経営コンサルタント、津名久ハナコです。
先日、島田さんのDX推進計画策定事業の成果報告会があり、無事に完走したお祝いにコンサルチームみんなでお疲れ様会を開催しました。会場は行きつけの中華料理屋さん。親父さんに「コース料理をどんどん出しちゃってください!」とお願いし、盛大に打ち上げをしたんです。
ところが私、極度の疲労で喉がカラッカラだったせいか、運ばれてきたビールを思わずグビグビ~っと一気に飲み干してしまいました。すると、親父さんから「早すぎるでしょう!」と愛のあるツッコミが(笑)。私たちコンサルチームは意外と体力に自信があるんです。話が少し逸れましたが、美味しい中華料理とお酒ですっかり英気を養うことができました。
さて、本題です。今日は中小企業の経営者様にとって非常に重要なテーマである「値引き」についてお話しします。結論を先にお伝えすると“値引きは絶対にしてはいけない”というのが私の主張です。
なぜなら、中小企業には安売りをしてはいけない3つの理由があるからです😌
理由❶中小企業に「無駄な経費」なんて存在しない!
「無駄な経費を削減して利益を確保しよう」という言葉を耳にしたことがある方は多いと思います。しかし、多くの中小企業では既にあらゆる面で徹底的なコスト削減が行われており、これ以上削れる経費は残っていないのが実情です。加えて、社会貢献活動や従業員の賞与など、将来的には今よりもむしろ多くの経費をかけざるを得ない場面も出てくるでしょう。
より充実した経営を実現するためには、今よりもはるかに多くの利益を確保する必要があるのです。
では、そのお金はいったいどこから生み出せばいいのかというと(当たり前すぎて申し訳ございません…)答えは「売上」です。 売上がなければ企業に入ってくるお金はありませんし、当然ながら利益も確保できません。数字は嘘をつきません。
売上が企業経営のすべての源である以上、値引きによって売上を安易に減らしてしまうのは非常にもったいない行為だといえます。
理由❷「逆選択」の罠にご用心!
「安売りすればお客様がたくさん来てくれる」と考えて値下げ競争に飛び込む企業は少なくありません。
しかし、価格だけを目的に集まってくるお客様は“より安いところ”を見つければあっさりと離れていってしまいます。これはマーケティングで「逆選択」と呼ばれる現象で、価格に釣られて来た顧客は価格に釣られて去るのです。こうした顧客との付き合いを続けても長期的な信頼関係は育ちにくく、企業を疲弊させる結果にもなりかねません。
理由❸中小企業は「手間」を惜しんではいけない!
中小企業は大企業と比べて人的資源や生産能力が限られていることが多く、そもそも「安く商品を作ろう」としても限界があります。たとえ安く販売する商品であっても、高く売る商品と同じだけの工程や手間がかかる場合がほとんどです。品質を下げずに手間をかけているのであれば、むしろ「高く」売るべきですし、それだけの商品価値があるはずです。
「高く売るための努力」は決して卑しいものではありません。
むしろ、中小企業が存続していくうえで不可欠な尊い努力です。商品やサービスの魅力を最大限に引き出し、それをどうやってお客様に効果的に伝えるかを日々追求することで“競合他社との差別化”や“ブランドイメージの向上”が現実のものとなり、結果として適正な価格を設定しやすくなります。
お客様が“納得して購入”してくれる状況をつくり出すことが、経営者の腕の見せどころと信じています。
「安売り」の誘惑に負けず、価値を追求しよう!
中小企業の経営者様、安易な値引きの誘惑に負けないでください😌
減らせる経費はほとんど残っておらず、むしろ企業をより成長させるための投資や社会貢献の観点で、これから先はより多くの利益が必要になります。その利益を生み出すのは売上であり、売上を確保するためにはお客様に十分な価値を感じていただくことが不可欠です。“高く売るための価値”を追求し続けることこそ、高みを目指す経営を実現する原動力になろうかと考えます。
「値引きをしない経営をしたい」「自社の強みをもっと伸ばしたい」と感じている方は、ぜひハンズバリューにご相談ください。
お客様に愛され、選ばれ続ける企業を目指して、一緒に価値を高めていきましょう🥰ご参考ください。
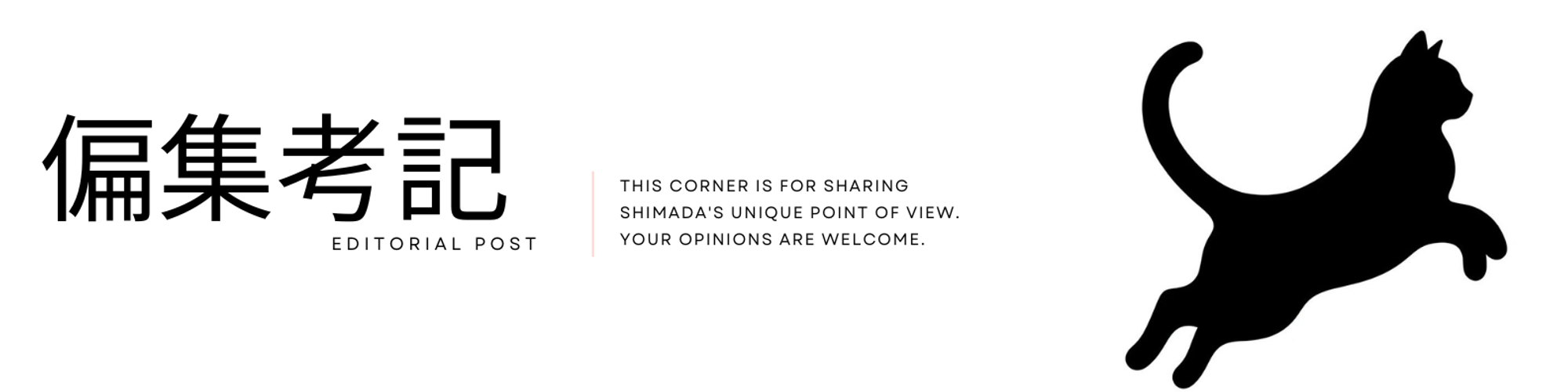 【偏集考記】財務諸表を“旅の計器”にしてみると?
【偏集考記】財務諸表を“旅の計器”にしてみると?
ハンズバリュー株式会社の変革者・作家の島田慶資です。
企業を運営するうえで経営理念を定め、その理念を具体的な形に落とし込むためには、言うまでもなく明確なビジョンが欠かせません。ビジョンとは「自社がどこを目指し、何を実現しようとしているのか」を示すものですが、その実行過程で必ず必要になってくるのが貸借対照表・キャッシュフロー計算書・損益計算書の財務三表です。
これら三つの計算書は、それぞれに大切な役割を担い、ビジョンの達成を下支えしてくれます。
とはいえ、「数字を眺めるだけではピンとこない」という声も少なくありません。そのため、「どうやってわかりやすくイメージすればいいのだろう」と試行錯誤している中で、少し面白いアイディアを思いついたので共有させていただきたいと思います。
財務三表を例えてみると「BSの標高計、CFの燃料計、PLの速度計」
貸借対照表は企業がいまどの高さにいるのかを示す標高計のようなものだと考えると、財務基盤や資産状況がわかるほど視界が広がって投資のチャンスも広がる一方、酸欠になりやすい高所(大きな負債)には転落のリスクも潜んでいることがイメージしやすくなります。
次にキャッシュフロー計算書です。CFは燃料計に例えてみましょう。いくら速度が出ていても、いくら高い標高にいても、手元の燃料が尽きれば先へ進めなくなるという重要性が腑に落ちませんでしょうか?
最後に損益計算書です。PLを速度計に例えてみました。たとえ瞬間風速的に高い売上や利益が出ていても、その速度が持続するかどうかは別問題だという捉え方ができます。
こうした比喩を通じて財務三表意味を考えると、それぞれが連携してはじめてビジョンの実現に向けた航路が見えてくるのだと理解しやすくなるでしょう。
経営理念と財務三表
企業は経営理念を掲げるだけではなく、その理念をどのように社会で具現化していくかを自社のビジョンとして明示する必要があります。
そして、このビジョンを現実のものとするためには、自社が今どの高度にいてどれだけの燃料を持ち、どのくらいの速度で進んでいるのかを正確に把握する必要があるはずです。もし標高計や燃料計、速度計のいずれかが故障して数値を見誤ったら、いくら地図やコンパスがあっても安全に目的地へ到達できなくなってしまうのと同じことです。財務諸表を読むときは、その数字が単なる集計結果ではなく、自分たちが思い描くビジョンとどう結びついているかを意識してみてはいかがでしょうか。
数字をうまく捉えることで、企業が目指す未来に向けてやるべきことが一段と鮮明になるかもしれません。
まとめ
経営理念から生まれたビジョンがどれだけ素晴らしくても、それを実行に移せない企業は多いです。
しかし標高計・燃料計・速度計を兼ねる財務諸表をしっかりと読み解きながら、自社がめざす姿との整合を常にチェックできるのであれば、少しずつでも確実に前進できる可能性は高まります。数字はどうしても敬遠されがちですが、それらが意味するものをイメージ豊かに捉える工夫をすると、財務諸表が単なる帳簿の集まりではなく、企業のビジョンを形にするための羅針盤にもなり得ることを改めて感じられるのではないでしょうか。
それでは、またお会いしましょう。 今日も一日、良い学びを。


