皆様、こんにちは! ハンズバリュー株式会社の島田です。
※社内で回覧していただいているお客さまがいらっしゃいました。ありがとうございます!!著作を明記していただけるのであれば、自由に配布ください。
メールマガジンの感想、お待ちしております! 「読んでるよ」と言っていただければ励みになります(^_^)
目次
独り言コーナー
❶当社の第10期経営指針発表会を開催しました。ケミカル産業玄地社長から学び、全員でつくる経営指針書に作り方を大変革しました。 前年と比べると完成度は落ちたように見えるかもしれませんが、これが当社の等身大の実力。どんな立派な計画も実行できなければ意味がありません。挑戦は続きます。
❷第11期の経営指針発表会には、同友会会員“ではない”方を経営指針発表会にご招待しようかなと考えています。 一緒に学びたいと思える方を招待して共に成長できる関係を願っております。そのためには、当社の成長が欠かせません。
❸本年1月から問題解決に当たっていた案件がすべて無事に着地しました。(一時的とは思いますが…)仕事の負荷が軽くなって土日に時間が出来ました。 坊やと散歩をしながら、仕事の振り返りに時間を当てさせていただきました。反省点もありますが、胸をはってやりきったと言える仕事ばかりでした。
❹12月にもしかしたら新庄支部で体験報告をさせていただけるかも?例会づくりにも参加させていただき、集客からお手伝いしたいと思います。 他の支部からも、ゲストもしっかり自主で集めたいと思います。楽しみです。
❺坊やが自分でシートベルトをつけられるようになりました。シートの差し込み部分をしっかり差し込めるようになったのは大きな成長です。 回数を重ねるごとにどんどん上手になっていて「まずは一度やってみること」「繰り返すことの大切さ」を改めて実感させられました。
島田の気になるニュース
❶減税・減社会保障のみに財源論を持ってくるくせに外国には支出する姿勢が気に食わない。自国が貧しくなる中で、優先順位はいかほどのものでしょうか。
必要性確認しないまま国際機関に4530億円を拠出 会計検査院が指摘
❷ちょっと前の記事ですが、与党の政権幹部の経済音痴が良くわかる発言。不思議なほど経済音痴が政治家に多いです。 自国通貨建ての国債でどうやって信用を失うんでしょう。CDS(クレジットデフォルトスワップ)の利率を説明してほしいです。
日本の国債評価「ぎりぎり」 自民幹事長、財政再建訴え
「国債リスク」はCDSで見るべき/by 原田泰 日本銀行元審議委員
❸ビジネスとして否定はしないのですが、シンプルに迷惑ではないでしょうか?😥…AIは確かに進歩していますが、もうすこし受け答えが自然にならないと売れないと思います。
AIが24時間365日休まず大量架電、「AIテレアポくん」登場 「AIピカソ」の親会社から
❹お客様支援をしていて実感あり。体力の衰えもあるのでしょうが、基本は物価高でしょう。可処分所得を削られているので旅行に行けません。より地方が衰退してしまいます。
70代以上の7割「24年の宿泊旅行0回」、地方は9割が国内客 観光白書
❺遠隔操作でもなく、完全自動ロボットがパワーワード。責任の所在に課題があると思いますが可能性を感じます。腫瘍の検知など部分的には機械に置き換わっている診断もあると聞いています。発展が楽しみですね。
世界初の「全自動ロボット歯科医による人間の虫歯治療」が成功
【今週の経済入門】賃金が上がらない本当の理由は?~「正社員の保護」を巡る大激論~
皆様こんにちは、ハンズバリュー株式会社の秘書・勝頼ヒデコです。 いつもメールマガジンをお読みいただき、ありがとうございます。

先日、インターネットのニュースを読んでおりましたら日本の賃金がなぜ長年上がらないのか、というテーマについて有名な経済評論家の方の記事が目にとまりました。 その内容が非常に刺激的で、後輩のハナコと一緒に読んでいたのですが、私たちの間でも意見が分かれ思わず議論が白熱してしまいました。
本日は「日本の賃金が上がらない本当の理由」について皆様と一緒に勉強したいと思います。
本日のテーマ『賃金停滞の犯人は「正社員の過剰保護」なのか?』
「日本の生産性は上がっているのに、実質賃金はこの20年以上ほとんど上がっていない」。 多くの専門家が指摘する日本経済が抱える大きな課題です。では、なぜこのような状況が続いているのでしょうか。
ある一つの見方「正社員の強すぎる身分保障が原因」という主張
その原因について、先ほど私が目にした記事(有名な経済評論家の主張)では仮説が提示されていました。 それは「正社員が法律で手厚く保護されすぎていることこそが、賃金停滞の元凶だ」というものです。
その主張を要約すると、以下のようになります。
- 企業は、一度雇うと解雇しにくい正社員の採用に慎重になる。
- その結果、賃金の安い非正規雇用が増え、国全体の平均賃金が下がる。
- 正社員の労働組合も、自分たちの雇用を守ることを優先し、会社が苦しくなるような大幅な賃上げを要求しなくなる。
- この「正社員ギルド」とも言える自己防衛が、経済全体の賃金上昇を妨げデフレを長期化させている。
「えっ!?つまり、正社員の身分が安定しているせいで、みんなのお給料が上がらないってことですか?なんだか、にわかには信じがたい話ですね…」と、ハナコも混乱しています。
この考え方に立てば、解決策は「解雇のルールを緩和し、企業がもっと自由に人材を入れ替えられるようにすること(雇用の流動化)」ということになります。
私たちの「問題のすり替え」と「マクロ経済政策の失敗」という反論
しかし、この「正社員犯人説」に対して私たちの反論があります。 それは「問題の本質は個々の企業の雇用ルールではなく、国全体の経済政策の失敗にある」という視点です。
こちらの主張のポイントは以下の通りです。
- 非正規雇用の増加は「原因」ではなく「結果」
そもそも企業が非正規雇用を増やすのは、景気の先行きが不透明で大きな投資(正社員の雇用)に踏み切れないからです。 「正社員の保護」のせいではなく、経済全体の停滞が招いた結果です。 - 賃金が上がらなかった本当の理由
「失われた30年」の間、日本政府は以下のような政策を続けてきました。
- 緊縮財政:
公共投資などを抑え続けたため、国内の仕事(需要)が慢性的に不足しました。仕事がなければ、企業は儲からず賃金を上げる余裕も生まれません。 - デフレ期の金融引き締め:
景気が冷え込んでいるにも関わらず、企業がお金を借りにくい状況が続きました。 - 3度にわたる消費税増税:
国民の消費意欲を冷え込ませ、企業のコスト負担を増やし賃上げの原資を奪ってきました。
- 緊縮財政:
つまり、私たちは国全体の経済という「パイ」が大きくならない中で、パイの分け方(解雇ルール)だけを変えても意味がないという考え方です。 需要不足の経済で解雇を容易にすれば、労働者はより弱い立場に置かれ、かえって賃金は下落圧力にさらされる危険性すらあります。
どちらの議論が私たちの未来につながるか
「正社員の過剰保護が問題だ」という議論は、非常にシンプルで分かりやすく一見もっともらしく聞こえるかもしれません。 しかし、長年の経済政策の失敗から国民の目をそらさせようとする議論のすり替えではないか…私には、そう思えてなりません。
この問題は、誰か特定の労働者を「悪者」にして解決するような、単純な話ではないのです。
本当に必要なのは、まず政府が積極的な財政出動と消費税減税をはじめとする抜本的な政策転換によって「企業が安心して賃上げできる経済環境」を国全体で作ることです。 正社員も非正規社員も、すべての働く人の賃金を引き上げるための、唯一の道ではないでしょうか。
一つのニュースをきっかけに、少し難しい話になってしまいましたが、ハナコも「なるほど…物事の一面だけを見て判断しちゃいけないんですね。勉強になります!」と、真剣な顔で頷いていました。
正しい知識を持つことが、より良い未来を選択する力になる。ハンズバリュー株式会社は、そのお手伝いができるよう、これからも皆様と共に学び続けていきたいと考えております。
それでは、次回もお楽しみに! 今週もどうぞよろしくお願いいたします。
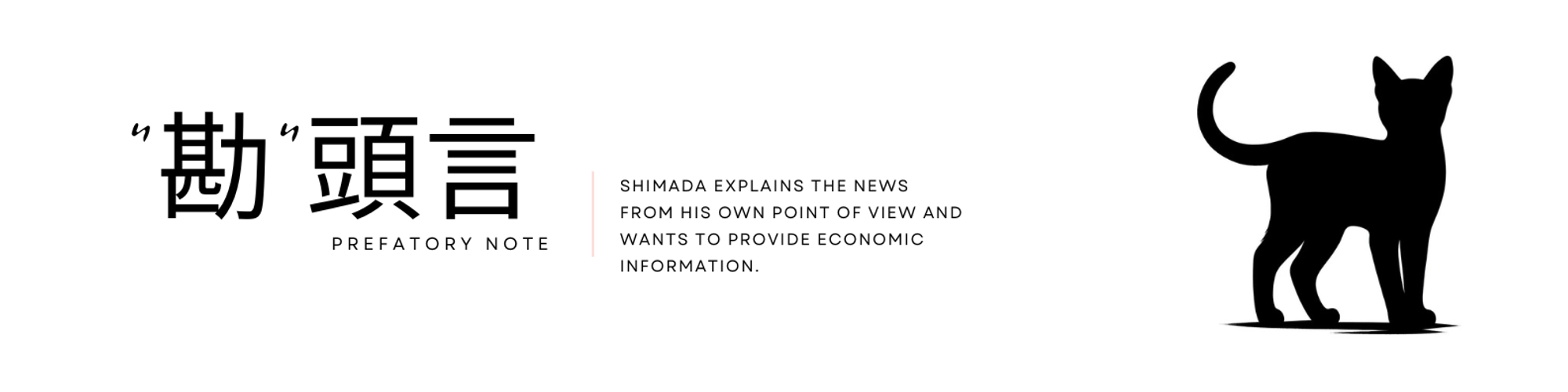 【“勘”頭言】戦略なき撤退は傷を広げるだけ。
【“勘”頭言】戦略なき撤退は傷を広げるだけ。
事業の「正しい終わり方」とは?
皆様、こんにちは。 ハンズバリュー株式会社の変革者・作家、島田慶資です。
先日、事業者様と金融機関との交渉に同席した際、金融機関から「不採算事業からの撤退も視野に入れざるを得ない」という、非常に厳しい言葉がありました。 しかし、私はその場で、単純で場当たり的な撤退はかえって会社の傷を広げる結果になりかねない、というお話をさせていただきました。 本日は「戦略的な撤退」とは一体何なのか、事業の「終わり方」について、どのように考えるべきなのかを皆様と一緒に勉強していきたいと思います。
赤字事業を閉じれば、黒字になるのか?
まず、具体的な状況を想定してみましょう。 ある会社が、4つの事業(仮に、引越・倉庫・便利屋・飲食とします)を展開しており、それぞれに営業拠点があるとします。
分かりやすくするために、各事業の損益を以下のように仮定します。
損益(各事業)
| 項目 | 売上 | 原材料費 | 粗利益 (限界利益) |
人件費 | その他固定費 | 営業利益 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | 100円 | 50円 | 50円 | 35円 | 25円 | ▲10円 |
この場合、各事業が10円の赤字なので会社全体では毎月40円の赤字(▲10円 × 4事業)となります。
さて、ここで金融機関の指摘通り赤字の「飲食事業」を閉鎖したらどうなるでしょうか。 売上と原材料費はゼロになりますが、問題は固定費です。
(解雇規制や道義的責任から)従業員の雇用は守らねばならず、人件費は残り続けます。店舗の家賃もすぐに解約できるとは限りません。
その結果、会社の損益はこうなります。
飲食事業撤退「後」の損益(会社全体)
| 項目 | 売上 | 原材料費 | 粗利益 (限界利益) |
固定費 (人件費など) |
営業利益 |
|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | 300円 (100円 × 3事業) |
150円 (50円 × 3事業) |
150円 | 240円 (60円 × 4事業分) |
▲90円 |
驚くべきことに赤字事業を一つ閉鎖した結果、会社全体の赤字は40円から90円へと倍以上に拡大してしまいました。
なぜ赤字が拡大したのか?「粗利益」という視点
なぜ、こんなことが起きるのでしょうか。 それはたとえ営業赤字であっても、その事業が「粗利益(限界利益)」を生んでいたからです。
飲食事業は、単体で見れば10円の赤字でした。 しかし、50円の粗利益を生み出し60円の固定費のうち50円分を自ら稼いで賄っていたのです。
この事業を単純に閉鎖してしまうと、その「固定費を補う力」が失われ、残った固定費が他の事業の利益をより大きく圧迫することになります。
撤退という判断は、これほどまでに慎重に行わなければならないのです。
本当の「戦略的撤退」とは
では、どうすればよかったのでしょうか。 事業の撤退は、本来、業績が悪化した火急の場面で行うべきものではありません。 会社の事業が成長している過程で、次の一手として計画されるべきものなのです。
全ての事業には、導入期、成長期、成熟期、そして衰退期という「成長曲線(ライフサイクル)」があります。経営者は、自社の事業が今どの段階にあるのかを常に把握し、事業が衰退期に入る前に、次の成長事業を立ち上げ、育てておかなければなりません。
そして、衰退していく事業の人員を、新たに成長する事業へと徐々にスライドさせていく。
これこそが、傷を最小限に抑え、会社の持続的な成長を実現する、真の「戦略的“撤退”」であり、むしろ「戦略的“転換”」と呼ぶべきものなのです。 事業が赤字になった責任は、決して従業員にあるのではなく、経営者の過去の判断ミスにあります。
その責任を負い、会社の存続を第一に考えた時、撤退が選択肢に入ることはあるでしょう。 しかし、その決断は、未来への明確なビジョンと戦略があって初めて、意味を持つのではないでしょうか。
皆様の会社では、事業の成長曲線をどのように描き、未来の人員配置を計画されていますか?
今一度、考えてみる時間を持つことが、未来の会社を守ることに繋がるはずです。 今週も皆様にとって、実り多き一週間となりますように。
 【実店舗に効く話】BtoBの成長が加速する!“認知資産”と“錯覚資産”という2つの強力な武器
【実店舗に効く話】BtoBの成長が加速する!“認知資産”と“錯覚資産”という2つの強力な武器
皆さん、こんにちは。 ハンズバリュー株式会社のコンサルタント、津名久ハナコです。
10月に突入しカレンダーも残り少なくなってきましたね。 ここから年末まで、時間がどんどん加速していくように感じるのは私だけでしょうか?
🍺 ビールが美味しい季節の終わりは少し寂しいですが、これからはホットワインや熱燗が美味しい季節だと思うと、新しい楽しみも湧いてきます😊
さて本日は、会計事務所を経営されている寺島先生からいただいたご相談について、皆様と一緒に考えていきたいと思います。
「もう一歩、成長を加速させたい…次の一手は何だろう?」
- 「ハナコちゃん、いつもありがとう。おかげさまでホームページやSNSは順調に運営できているんだけど、事務所としてもう一歩、成長を加速させていきたいんだ。何か良い方法はないかな?」
- 「はい、あります!原理原則から情報提供させていただきます!」
会計事務所や経営コンサルタント、法律事務所など、BtoB(法人向け)で、かつ「目に見えないサービス」を提供されている方が次の成長戦略を考える上で知っておくべき2つの原理原則があるんです。
それは「認知資産」と「錯覚資産」です。
原則1:知っているか、知らないか。「認知資産」の重要性
BtoBビジネス、特に先生方のような支援業は、よほどの画期的なサービスでも開発しない限りマスコミに大きく取り上げられることは稀です。 そうなると、お客様に選んでいただくための最も重要な分岐点は、非常にシンプル。 「あなたの会社(事務所)を知っているか、知らないか」 これに尽きます。
この「知られている」状態こそが「認知資産」です。 首都圏の大手弁護士事務所や会計事務所が、莫大な費用をかけて駅の広告や新聞、テレビCMを打つのは、まさにこの「認知資産」を積み上げるため。 最近流行りのYouTubeやSNSも、この資産を増やすための強力なツールと言えます。
お金をかけて露出を増やせる企業は、より多くのお客様に知られ、成長しさらに広告宣伝費をかけられる、という「善の循環」に入ることができます。
原則2:「〇〇といえば、あの会社!」と思わせる魔法。「錯覚資産」とは?
もう一つの重要な資産が「錯覚資産」です。 「ある特定の分野やエリアでNo.1の実績があると、他の分野でも優れているに違いない」と、お客様が良い意味で“錯覚”してくれるという強力な心理効果です。
お客様の声をたくさんホームページに掲載したり「〇〇エリアでの実績No.1!」といった強みを打ち出すことで「この会社は、この分野でこれだけ強いのだから他のことも安心して任せられるだろう」と、お客様からの絶大な信頼を得ることができるのです。
さあ、2つの資産を増やす作戦会議を!
このお話をした上で、寺島先生と具体的な作戦会議を行いました。
認知資産を増やすために
- 「先生、まずはYouTubeを始めて、専門知識を分かりやすく発信していきましょう!その動画は、InstagramやTikTokにも展開すれば、一石三鳥ですよ!」
- 「なるほど、YouTubeか!照れくさいから敬遠していたけど、やってみるか!」
- 「それと、先生の事務所は山形市の中心部ですから、市内を走るコミュニティバスの中に広告を出すのも、地域の方々への認知度向上に効果的だと思います!」
錯覚資産を築くために
- 「同時に『相続専門』や『医療機関に強い会計事務所』といった、先生の事務所の“No.1分野”を明確に打ち出し、その実績を集中してアピールしていきましょう!」
- 「なるほどね…!ただ闇雲に頑張るのではなく、“知ってもらう工夫”と“No.1を打ち出す工夫”が必要だったんだね。ありがとう、ハナコちゃん!」
2つの資産を回して、成長のエンジンをかけよう!
皆様の会社はいかがでしょうか?
- お客様に広く知ってもらうための「認知資産」
- 「〇〇ならココ!」と強く記憶してもらうための「錯覚資産」
この2つの資産を意識的に増やし、両輪でうまく回していくことがBtoBビジネスの成長を加速させるための強力なエンジンとなります。
「うちの会社の“No.1”って何だろう?」 「認知度を上げるために、何から始めればいい?」
そんな時は、ぜひ私たちハンズバリューにご相談ください! 皆様の会社の強みを見つけ出し、それを世の中に広めていくための成長戦略を、一緒に描かせていただきます!
ぜひご参考ください。
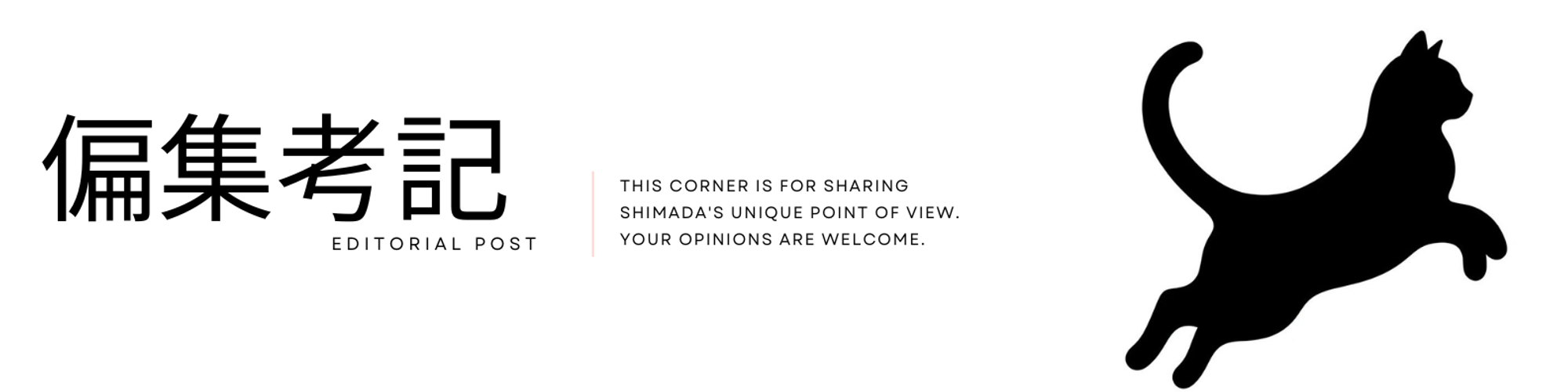 【偏集考記】言葉遊びだと思っていた『共育』が、今こそ必要だと確信する理由
【偏集考記】言葉遊びだと思っていた『共育』が、今こそ必要だと確信する理由
ハンズバリュー株式会社の変革者・作家の島田慶資です。
私たちは無事に「経営指針発表会」を開催することができました。 今回の発表会で島田が大切にしたのは、中小企業家同友会で育まれている「共育(ともそだち)」という考え方です。
十年間、馴染めなかった言葉
正直に告白しますと島田がこの「共育」という言葉を初めて耳にした十数年前、あまり好きな言葉ではありませんでした。「共に育つ」と書いて「共育」。どこか言葉遊びのように聞こえ、また経営は最終的に経営者の責任の下で行われるべきであり、その責任を曖昧にしてしまうような印象を受けて、ずっと馴染めずにいたことを記憶しています。
なぜ、私の考えは変わったのか
そんな島田が、なぜ今になってこの「共育」という考え方を経営の中心に据えようと決意したのか。 それには、いくつかの大きな気づきがありました。
まず、今の経営環境は、決して甘い(ぬるい)時代ではないということ。 この厳しい環境を乗り切るためには、従業員さん一人ひとりの力が不可欠です。
特に私たち中小企業においては、人が余っていることなど絶対にあり得ません。営業、総務、製造、デザイナー…誰もが「主役」であり、会社の未来を担う「主力」です。 そうでなければ、無駄な経費をかけられない中小企業が高収益な事業構造を築くことなど不可能だというただの事実があります。
痛恨の自己矛盾、そして「自分ごと」
コンサルタントとしてお客様をご支援する中で「計画の目標は島田や銀行が作るのではなく、必ずご自身で設定してください」と、口を酸っぱくして申し上げてきました。 なぜなら自分自身で考え、自分自身で決めた目標でなければ人は心の底から「約束」することはできないと信じているからです。
そのことを思い返した時、私は愕然としました。 翻って、自社ではどうだったか。
島田は「上から目標を設定し、みんなで頑張ろうと呼びかける」ことを、この十年間、繰り返してきただけではなかったか。 従業員さん一人ひとりがどう考えているのか、その想いを軽視していたのかもしれない…と反省の念に駆られました。
本当の意味で力が発揮されるのは「なぜこの目標なのか」「どうしてこの道を選ぶのか」を全員で徹底的に議論し、みんなが納得して「よし、その方向で行こう!」と決めた時です。その瞬間、会社の数字ややるべきことが、初めて一人ひとりの「自分ごと」になる。この当たり前の事実に、島田はようやくたどり着いたのです。
「共育」の本当の意味
この気づきを得て初めて、「共育」という言葉が、すとんと腹に落ちました。
共に育ち、共に気づきを得る。 「あなたはそう思うのか」「僕はこう思う」。互いの意見を尊重し合いながらも、会社の理念やビジョンという大きな羅針盤に照らし合わせ「互いの間にある障害は何か?」といった建設的な対話を重ねる。 みんなで同じ方向を向き、同じ高みを目指していく。
これこそが、厳しい時代を乗り越えるための、唯一の道なのだと。
十年という歳月と感謝
この考えに至るまで、十年かかりました。ここの理解に至るまで十年。
この歳月が早かったのか、遅かったのかは分かりません。 しかし、毎年悩みながらも、少しずつでも前進できていること。 その時間を許し、支えてくれている従業員さんたち、そして同友会での学びの時間を作り出してくれている従業員さんたちに、今は感謝しかありません。
今期は既に始まっています。 掲げた高い目標に向かいさらに成長することで、従業員さんの「職業人としての幸せ」と「個人としての幸せ」、その両方を実現できる会社を皆で創り上げていきたいと強く思っています。
今期もどうぞよろしくお願いいたします。 良い学びを。


