皆様、こんにちは! ハンズバリュー株式会社の島田です。
※社内で回覧していただいているお客さまがいらっしゃいました。ありがとうございます!!著作を明記していただけるのであれば、自由に配布ください。
メールマガジンの感想、お待ちしております! 「読んでるよ」と言っていただければ励みになります(^_^)
目次
独り言コーナー
❶高市早苗さんの書籍をアマゾンで全て取り寄せて読破しました。経済認識は正しいです。閉塞感のある日本経済を立て直してくださることを期待しています。
❷ユーチューブチャンネル登録者数が1ヶ月で1,000人を超えました。企画・アシスタント手配・撮影・編集・投稿・運用・集客と一連の流れを学んでおります。お客様の支援に活かしたい!
❸妻が小学校の先生をしています。「教材の作成にGoogleGeminiを活用して感動した」と感想を共有いただきました。生成AIの活用は不可逆的な進化ですね。当社でも議事録作成などに活用して生産性向上に役立っています。
❹Surfaceの新型には、スマホのCPUが組み込まれています。インテルやAMDからARMに変更。生成AIをローカル環境で実行できるようにすること、省電力化を狙うことを目的にしているとのことですが…。正直、魅力的に映りません。当社のコンサル、営業サポートはSurfaceで統一していましたが、今後はどうしようかなぁ。
❺坊やが補助輪なしで自転車を乗れるようになりました。素晴らしい成長。ミニベロを彼にプレゼントすることを約束しているので、一緒にサイクリングすることが将来の楽しみになっています。
島田の気になるニュース
❶ビックリしました。これまで日本経済の停滞の象徴的なキーワードであった「新しい資本主義(緊縮財政)」がきっぱり廃止になりました。高市早苗効果ですね。素晴らしい決断です。
高市政権「新しい資本主義」廃止へ 岸田元総理に伝える
❷責任ある積極財政の議連ってホームページがあるんです。なんとノーベル賞受賞の講演も無料で閲覧できます。その他、講師陣も島田納得の人材ばかり。期待が高まります。
[特別勉強会]「日本経済復活に向けての直言」ノーベル経済学賞受賞・コロンビア大学 ジョセフ・E・スティグリッツ 教授 2023年5月11日
❸日本維新の会が自民党と維新の合意文書をPDFで公開しております。暫定税率を軽油含めて廃止することが明記。片山さつき財務大臣の発言とあわせて考えると、代替財源なしで実行してくださると期待できます。
2025年10月20日(月) 自由民主党・日本維新の会 連立政権合意書
❹生成AIの活用について東京商工会議所が活用方法をPDFで公開しています。大事な視点は「生成AIは考えているわけではない」こと。確率論で文字を綴っているだけです。断言しますが、入力した以上にアイディアは出ません。
中小企業のための「生成AI」活用入門ガイド
❺当社配信のメールマガジン「神原キサコの制作カフェ」は11月から大転換を予定しています。メルマガからユーチューブチャンネル「神原キサコの制作カフェch」へ。ぜひ、チャンネル登録よろしくお願いします。
心をつなぐ仕事、つなぐホームページ公式ch
❻明らかに政治の責任です。なぜに昭和より平成より、令和が貧しくなるのか。子供が貧しくて国が栄えるわけがない。岸田・石破路線は明確な緊縮財政でした。いかに復活できるか高市早苗さんに期待しています。
“子どもの貧困”平均世帯年収207万円 約半数が貯蓄ゼロ…「食事を3回とれなくなった」「消えてしまいたい」リアルな子どもの声「高校進学で母親の負担が増えてしまう」北海道で深刻な状況に
【今週の経済入門】行動経済学の「しっぺ返し戦略」とは?~国際ルールの「相互主義」を考える~
皆様こんにちは、ハンズバリュー株式会社の秘書・勝頼ヒデコです。 いつもメールマガジンをお読みいただき、ありがとうございます。

高市早苗新総理が誕生し、日本にとってまさに歴史的な2週間となりましたね。 日本の行政トップに女性が立つのは、さかのぼれば北条政子、推古天皇、卑弥呼まで行くとも言われ、約800年ぶりとも言える快挙です。
後輩のハナコも「日本で4人目の女性リーダーかもしれないなんて、本当にすごいです! これまで少し停滞していた日本がまた元気で誇らしい国に戻れるよう高市総理には頑張ってほしいですね!」と、朝から興奮気味に話していました。
さて、高市新総理は、経済政策だけでなく外交や国際ルールについても、一貫した考え方を示しておられます。 その議論の根幹にある大切な原則が「相互主義」です。
本日は、この「相互主義」がなぜ国際社会で重要とされ、そしてなぜ経済的にも合理的とされるのか…行動経済学における「しっぺ返し戦略」という視点から、皆様と一緒に勉強してみたいと思います。
本日のテーマ『国際ルールの基本「相互主義」と「しっぺ返し戦略」』
まず、「相互主義」とは、国際関係における非常にシンプルで公正な大原則です。 簡単に言えば「相手国が、自国民(日本人)に認めている権利は、自国も相手国民に認めます。しかし、相手国が日本人に認めていない権利は、自国もその相手国民には認めません」という考え方です。
これは、外国人参政権や二重国籍の取り扱い、あるいは行政サービス(生活保護)の利用範囲など、あらゆる分野に関わってきます。 ※例えば韓国では、日本人を含む外国人は生活保護を受けられませんが、日本では外国人は生活保護を受給できます。
するとハナコが「でも先輩、私は時々『日本に住んで、きちんと税金を払っているのだから、国籍に関わらず日本人と同等に扱うべきだ』という意見も耳にしますが、それは違うのですか?」と尋ねてきました。
それは、国内の人道的な観点からはとても大切な視点です。しかし、国家間のルールを決める上では、その考え方は必ずしも当てはまるとは言えません。なぜなら、その議論は「相手の国が日本人をどう扱っているか」という「相互主義」の大前提を考慮していないからです。
では、なぜこの「相互主義」が、国際社会でこれほど重要視されるのでしょうか。 ここで、行動経済学の有名な「しっぺ返し戦略(Tit-for-Tat)」が登場します。
これは、同じ相手と繰り返しゲーム(取引)を行う場合、どのような戦略が一番得になるかを分析した理論です。 その戦略とは、
- 最初は、相手を信頼し「協力をする」
- 相手が「協力」したら、次回も「協力する」
- 相手が「裏切った」ら、次回は自分も「裏切る」(=しっぺ返しをする)
- 相手が再び「協力」に戻れば、自分も「協力」に戻る(=根に持たない)
一見、「しっぺ返し」というと厳しく聞こえますが、多くのシミュレーションの結果、この「最初は協力的だが、裏切りには即座に報復する」という戦略こそが、長期的にはお互いの利益を最大化する(=最も経済合理的である)ことが証明されています。
国際関係もこれと全く同じです。 お互いに権利を認め合う「協力」関係が、両国にとって一番の利益となります。しかし、もし片方の国だけが一方的に権利を与え続け、相手国からは何の権利も得られない(=裏切られ続ける)状態が続けば、その国の利益は長期的には損なわれてしまいます。
「相互主義」とは、この「しっぺ返し戦略」に基づき、お互いの国益を守り、公正な関係を築くための、非常に合理的で賢明なルールなのです。
ハナコも、「なるほど…。感情論や“お人好し”ではなく、お互いの利益のために合理的に判断することが、国際社会では大切なんですね。日本も毅然とした態度をとることが、巡り巡って日本の国益を守ることにつながる、ということですか」と、深く納得していました。
高市新総理には、これまでの日本の政治が時に曖昧にしてきたこうした国際社会の基本原則をしっかりと立て直し、世界各国と対等に渡り合いながら、日本を「再び成長できる、誇らしい国」へと導いていただくことを一国民として心から期待しております。
それでは、次回もお楽しみに! 今週もどうぞよろしくお願いいたします。
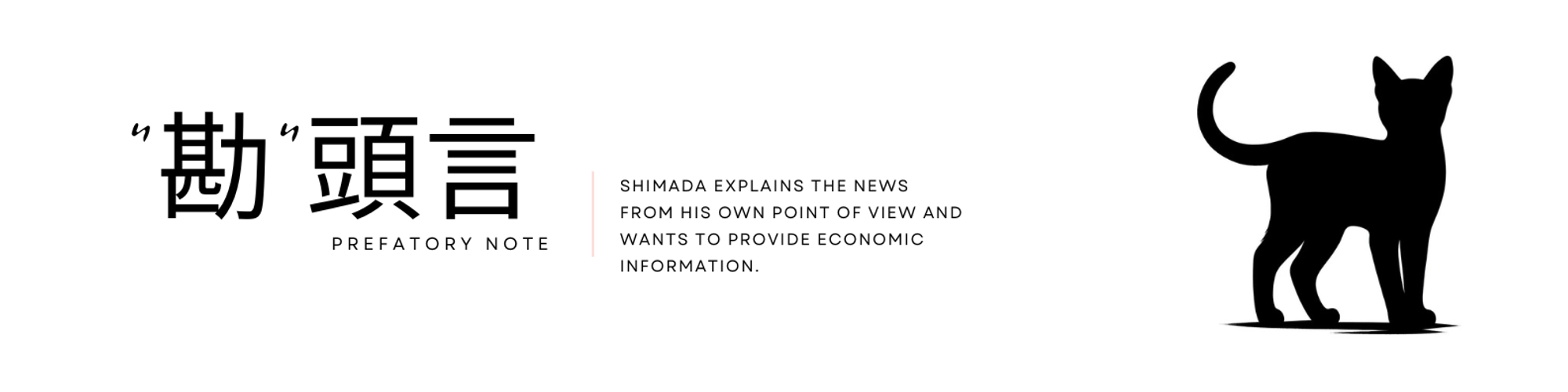 【“勘”頭言】なぜ「消滅可能性」は「フロンティア」なのか?あり方を見つける経営指針書の力
【“勘”頭言】なぜ「消滅可能性」は「フロンティア」なのか?あり方を見つける経営指針書の力
皆様、こんにちは。 ハンズバリュー株式会社の変革者・作家、島田慶資です。
さて皆様、日本は今「少子高齢化」ではなく、すでに「少子高齢社会」の真っ只中にあります。ここ山形県においても、多くの市町村が「消滅可能性都市」に該当するという厳しい現実に直面しています。
この状況を、皆様はどのように捉えていらっしゃるでしょうか。 「危機的状況だ」と思われますか?
私は、これは「フロンティア」…つまり計り知れない可能性に満ちた新時代の幕開けだと考えています。
大企業が去り、中小企業が残る理由
なぜ、危機が可能性になるのか。SWOT分析で考えてみましょう。
大企業や中堅企業が経営戦略を立てる際、最も重視するのは「外部環境」。すなわち「機会」と「脅威」です。彼らは他店舗展開や大規模な事業運営を行っている以上、このマクロ要因の影響から逃れることはできません。
人口減少や高齢化という「脅威」が明確なエリアから、彼らは何をせざるを得ないか。答えは「撤退」です。
では、大企業が撤退したその場所には、誰が残るのでしょうか。そうです!我々、中小企業・小規模事業者のみです。
かつて、巨大な隕石が地球に落下し、環境が激変した際、あれほど隆盛を誇った恐竜(大企業)は絶滅し、地中で息を潜めていた小さなネズミ(中小企業)だけが生き残ったという話があります。
今、まさに山形県をはじめ地方で起きているのは、この「環境激変」です。我々は小さいからこそ、この変化を乗り越え生き残ることができる。大企業が去った広大なフロンティアで、新たな挑戦をした者こそが、次の時代の勝者となるのではないでしょうか。
「あり方」こそが、唯一の羅針盤
当メールマガジンやユーチューブチャンネルで強みの深掘りやポジショニングの変更、強みの可視化といった手法で生き残る方法をお伝えしています。しかし、それはあくまで「対症療法」であり、本質的な経営改善ではありません。この新しいフロンティアを生き抜くために抜本的な自社の変革を成し遂げるには「自分自身が何者で、どうしていきたいのか」という、経営者と会社の「あり方」そのものが問われます。
この「あり方」を明確に言える企業は、強い。 なぜなら、「何をしなければならないか」という羅針盤を経営者だけでなく、全従業員が共有し、一丸となって信じることができるからです。
皆様の会社は、社長一人で経営できるでしょうか。絶対にできません。従業員、協力会社の皆様の力を合わせて、初めて経営は成り立つはずです。
しかし、その集まった人々が、それぞれバラバラの価値観を持っていたらどうでしょう。 「綱引き」で例えてみましょう。それぞれが違う方向を向いて力を込めても、力は分散し、まとまりません。 しかし、全員が同じ方向を向き、「よいしょ」と力を合わせれば、それは強大な力となり、他を圧倒することができます。
このサバイブしていかなければならない経営環境、そしてフロンティアを開拓していく上で、従業員と社長が力を合わせる唯一の方法。それが「あり方」を見つけることです。
経営指針書という「最強の武器」
そして、その「あり方」を見つけ、全社で共有するために絶対的に必要なものこそが、「経営指針書」です。
断言します。この経営指針書なしに、経営者と従業員が真に力を合わせることは100%不可能です。
私たち中小企業家同友会には、この「あり方」を見つけ出すための経営指針書を作成するノウハウが、山のように詰まっています。
来期、自社の「あり方」を見つけ、このフロンティアに挑戦する経営指針書づくりに、共に挑戦する仲間を募集しております。ぜひ、ご参加ください。
今週も皆様にとって、実り多き一週間となりますように。
今週もよろしくお願いします。
 【実店舗に効く話】HPの問合せが減った…?今、静かに起きている「ウェブマーケティングの大転換」とは
【実店舗に効く話】HPの問合せが減った…?今、静かに起きている「ウェブマーケティングの大転換」とは
皆さん、こんにちは。 ハンズバリュー株式会社のコンサルタント、津名久ハナコです。
すっかり秋も深まり、美味しいものがたくさんの季節ですね!先日、先輩のご実家からサツマイモが届いたそうで、キサコ先輩が持ってきてくださいました
さて、美味しい秋の味覚の話とは打って変わって…本日は、皆様のビジネスに直結する「ウェブマーケティング」の大きな転換点について、お客様とのやり取りを交えてご紹介します。
「20年頑張ってきたのに…なぜHPの問合せが減ったんだ?」
先日、福島県で墓石屋さんを経営されていらっしゃる、飯沢社長様からお電話をいただきました。 「ハナコちゃん、ちょっと相談があってね。最近、ホームページからの問い合わせが少なくなってきている気がするんだ。何か対策はあるかな?」
すぐにZoomミーティングを設定させていただき、詳しいお話を伺いました。 「うちは20年前、小さい会社だった頃からホームページに力を入れて、SEO対策もPPC広告もコンテンツマーケティングも全部やり尽くしてきた自負があるんだ。おかげで地域で一番の会社に成長できたと思ってる」
飯沢社長のおっしゃる通り、当社のウェブディレクターやマーケターも総力戦でサポートさせていただいており、Googleアナリティクスのデータを見ても決して悪い数字ではありません。
そこで、私は切り出しました。 「社長、ありがとうございます。データ上は問題ないのに問い合わせが減っている…。もしかすると、私たちは今ウェブマーケティングの『構造的な転換点』に直面しているのかもしれません」
「構造的な転換…?それって、どういうことなんだい?」 飯沢社長は、不安そうに首をかしげました。
もはや「Webマーケティング=ホームページ戦略」ではない!
そうなんです。 飯沢社長がホームページに力を入れ始めた20年前から、ここ数年に至るまで、まさに「ウェブマーケティング=ホームページ戦略」そのものでした。 SEO対策、PPC広告、コンテンツマーケティング、ブログ、SNS連携、メルマガ…すべては、自社の「ホームページ」に来てもらうための施策でしたよね。
しかし、この数年、特にYouTube、TikTok、Instagramの台頭により、お客様が情報を検索する行動が明確に変わってきているんです。
お客様の「情報の入り口」は、もうHPではない?
今、多くのお客様は、何かを調べようと思った時、いきなりGoogleで検索するのではなく、まずYouTubeやInstagram、TikTokといったSNSの中で検索をします。
そして、そこであなたの会社や商品を知ったお客様が「この会社、ちゃんとしてるかな?」「もっと詳しい情報が知りたい」と、“答え合わせ”や”信頼性の確認”のために初めて公式ホームページを訪れるのです。
これからの戦略は「SNS(認知)」と「HP(信頼)」の2段構え!
この状況下において、ホームページに期待される役割は、新規のお客様を掴まえる「リード獲得」から「信頼できる情報をストックしておく場所」へと変化しています。
つまり、これからのウェブマーケティングは役割分担を明確にした「2段構え」で考える必要があるのです。
- 【第1段階:認知・リード獲得】
お客様との最初の接点を作る場所。
→ YouTube、TikTok、InstagramなどのSNS・動画プラットフォーム - 【第2段階:情報の蓄積・信頼獲得】
お客様が安心して問い合わせできる「受け皿」となる場所。
→ 公式ホームページ
「なるほど、そうだったのか…。うちは場当たり的にSNSを運用してたけど、考え直さないといけないな」
墓石屋さんの場合、最適なプラットフォームは?
「ただ、社長様。今から全方位でSNSをやる、というのは現実的ではありませんし、逆に力が分散してしまいます」 飯沢社長様のビジネス(墓石)を考えると、お客様の年齢層は比較的高めで、しっかりとした信頼できる情報を求めていらっしゃいます。 そう考えると、最適なプラットフォームは「YouTube」でしょう。
YouTubeで認知を獲得し、ホームページで信頼を得て、お問い合わせに繋げる。 この流れを作ることが、これからの時代の、飯沢社長にとっての最適解になるはずです。
もちろん、これまで続けてきたSEO対策やPPC広告も、まだ問い合わせが獲得できているので、体感として効率は下がったとしても継続すべきです。
「そうか…最近は本当に難しくなってきたんだね。わかった、まずはYouTubeチャンネルを開設するところからスタートしてみるよ!」 飯沢社長様は、新しい一歩を踏み出す決意を固めてくださいました。
「情報の入り口」と「受け皿」を設計し直そう
皆様の会社はいかがでしょうか? お客様との「最初の接点(情報の入り口)」は、どこになっていますか? そして、そのお客様を受け止める「信頼できる受け皿(ホームページ)」は、きちんと機能していますか?
「ウェブマーケティング=ホームページ戦略」という、これまでの常識が、今まさに変わろうとしています。
「うちの業界だと、どのSNSが”入り口”になるんだろう?」 「YouTubeとホームページ、どう連携させたらいい?」 そんな時は、ぜひ私たちハンズバリューにご相談ください! この大きな転換期を乗り越えるための新しい戦略地図を、一緒に描かせていただきます!
ぜひご参考ください。
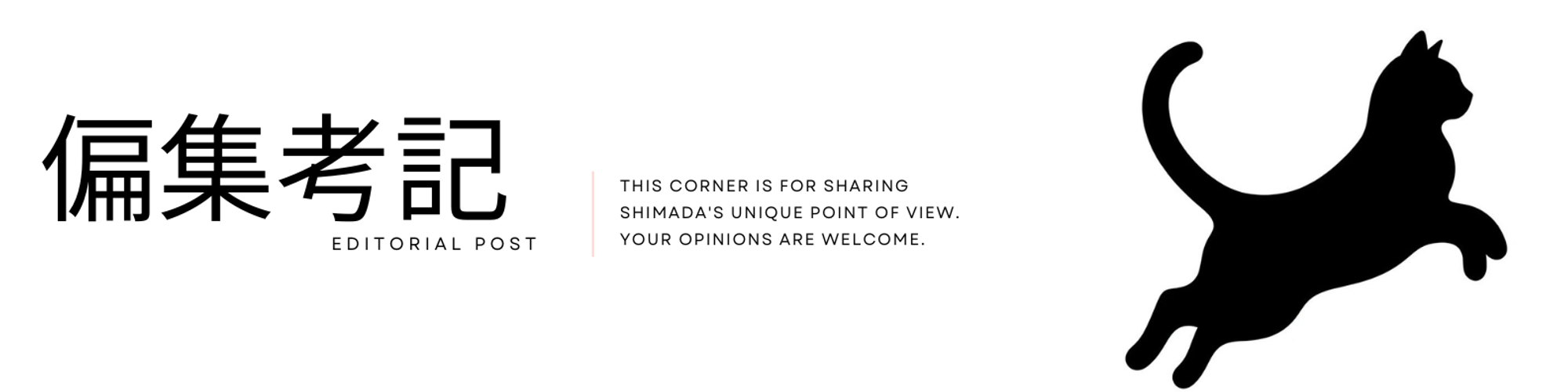 【偏集考記】「ブランド構築」という言葉に惑わされない。
【偏集考記】「ブランド構築」という言葉に惑わされない。
~中小企業が本当に磨くべきもの~
ハンズバリュー株式会社の変革者・作家の島田慶資です。
先日、当社で「ブランド」とは何かについて、社員と意見交換を行いました。世の中には様々なブランド論がありますが、今日は、島田が考えるブランドの本質について、皆さんと一緒に考える時間になればと思いSurfaceのキーボードをたたいております。
ブランド=「知名度」なのだろうか?
まず「ブランド」と聞くと、何を思い浮かべるでしょうか。有名な企業、有名な人物、あるいは有名なスーパーマーケットでしょうか。しかし、単なる「知名度」や「人気」が、そのまま「ブランド」とイコールになるかというと、どうもしっくりきません。
Appleの例 ~企業ができることお客様が決めること~
例えば、iPhoneについて考えてみます。 私個人がiPhoneに対して抱いている「ブランド認知」は、「そこそこ使いやすく、価格はほどほど、でも壊れにくく便利なスマートフォン」というものです。
では、この「認知」を私に持たせるために、Apple社が行った「ブランド構築」とは何だったのでしょうか。 それは突き詰めれば、「ソフトウェアの性能を高め、ハードウェアの設計を見直し、サポート体制を整え、使いやすくて壊れない製品を提供し続けること」しかできません。彼らが直接コントロールできるのは、そこまでです。
彼らがどれだけ努力し「こういうブランドだと思ってほしい」と狙ったとしても、その結果として私のような「認知」を持つかどうかは、最終的にお客様一人ひとりの受け取り方次第です。 つまり、企業が狙った通りのブランドイメージを100%お客様の頭の中に構築することなど本質的に不可能なのではないか、と私は思うのです。
中小企業が本当に取り組むべきこと
そう考えたとき、私たち中小企業が、コンサルタントやマーケターが提案する小手先の「ブランド構築」という商品サービスに、果たしてどれほどの意味があるのでしょうか。
私が信じる、真のブランド構築とは、もっとシンプルです。 それは「技術を磨き続けること」「お客様と真摯に向き合うこと」「そして、共に働く社員と誠実に向き合うこと」です。
日々のこの地道な積み重ねこそが、結果としてお客様や社会の中に「あの会社は信頼できる」「あの会社と共に歩みたい」という、本物のブランド(=信頼の証)を築き上げていくのだと、私は確信しています。小手先のイメージ戦略に頼っていては、本質的な成長などあり得ないのではないでしょうか。
皆さんの会社では、この「本質的なブランド構築」に取り組んでいらっしゃいますか。
今週もどうぞよろしくお願いします。 良い学びを。


