皆様、こんにちは! ハンズバリュー株式会社の島田です。
メールマガジンの感想、お待ちしております! 「読んでるよ」と言っていただければ励みになります(^_^)
目次
独り言コーナー
❶Adobe社のフォトストック(商用写真)に採用されていたカメラマンと知り合うことが出来ました。弊社の提供するホームページの品質がグッと上がります。お客さまに写真を提供しましたところ拍手喝采でした🥰
❷4月2日に僕の弟ちゃんに子供が生まれました。11歳離れている弟で、子供のイメージしかありませんが、彼も故郷・徳島で頑張っているようです。
❸坊やの保育園の送迎は、島田の仕事です。4月の風物詩ですね。年少さんの教室からはお母さんと離ればなれになった子供たちの絶叫がとまりません。遠く保育園の駐車場からも絶叫が聞こえてきます。頑張れ、子供たち。
❹先週、九州は福岡の大牟田市のお客さまを訪問しました。がっつり2日間、かからわせていただきましてお客さまから感謝のお言葉をいただきました。懇親会では、九州の名産を沢山提供いただき、遠慮なく平らげさせていただきました。ありがとうございます!
❺事業承継の場面で、親子で険悪な関係を見かけます。僕と坊やでも同様の関係になるのか不思議に思っています。誰しも子供とケンカしたいと思っていないですよね。何時何処で関係性が変わるのでしょうか?
島田の気になるニュース
❶生成AIを活用しているでしょうか?どの生成AIを利用してもアウトプットはマークダウンの形式でしょう。 ワードやエクセルにはそのまま活用できないことにストレスを感じていました。そこで島田が変換ツールを開発してみました。ご活用ください。
Markdown2ODT
❷続けて手前の開発のご紹介。生成AIを活用してシステム開発を行いました。 温泉旅館とインフルエンサーのマッチングサイトです。まだ開発途中ではありますが、ひっそりリリースしております。無料で案件を掲載します。旅館・ホテルの皆様、案件のご相談をお待ちしております。
つなぐSNS「温泉旅館とインフルエンサーをつなぐプラットフォーム」
❸島田は、消費税撤廃論者です。単なる輸出補助金でしかないですよね。害悪。自民党はヒールに徹しているのか、国民への煽りがすごいですね。この話を聞いて納得してもらえると思っているのでしょうか?疑問です。
自民幹事長「下げる話だけでは国民に迷惑」与野党から「消費減税」求める声に
❹現状、一時停止措置が取られています。牛を扱うお客さまから教えていただきましたが、輸出も復活しているようです。国対国の交渉が、我々事業者にも降りかかってくるというのは驚きですね。まさに不確実性の時代を感じさせられます。
米沢牛の競り アメリカの相互関税による国産牛の輸出減で国内流通増加し消費の低迷懸念
❺グローバリズムの失敗を表しているかのようですね。世界中のみんなが価値観を共有して平和であることがグローバリズムの前提条件。どうしても世界中のすべての国が同様の価値観を共有できるとは思えません。どこかで逆回転がかかるのでしょう。日本の基幹産業の一つに観光は成長するのでしょうが、中身は変わるかもしれませんね。
ウクライナ、ロシア軍参加の中国人捕虜に 米国「憂慮」
【今週の経済入門】円高?円安? 知っておきたい為替相場の仕組みと「トリレンマ」
皆様こんにちは、ハンズバリュー株式会社の秘書・勝頼ヒデコです。 いつもメールマガジンをお読みいただき、ありがとうございます。

皆様こんにちは、ハンズバリュー株式会社の秘書・勝頼ヒデコです。 いつもメルマガジンをお読みいただき、ありがとうございます。
先日、お天気が良かったので、同僚のデザイナーと一緒に日帰り温泉に行ってまいりました。この季節はドライブも気持ちが良いですね!桜を眺めながら、米沢市のお隣、飯坂温泉まで足を伸ばしてみました。
飯坂温泉は昭和の懐かしい面影が残る素敵な温泉街なのですが、新しいカフェもオープンしたと旅館の女将さんに伺い、早速訪問してみました。私たちより少し先輩の女性経営者の方がお一人で切り盛りされていて、いただいたパンケーキが絶品!
心のこもったおもてなしに、私たちも元気をいただきました。陰ながら応援しています!
さて、本日はニュースでもよく耳にする「為替」について、皆さんと一緒に考えてみたいと思います。
本日のテーマ『円高と円安、どっちがいいの? 為替相場の不思議』
「今日の東京外国為替市場、円相場は…」といったニュース、毎日耳にしますよね。でも、「円高」と「円安」、結局どちらが私たちの経済にとって良いのか、ちょっと分かりにくいと感じることはありませんか?
実は、為替レートは株価とも密接に関係しています。
例えば、一般的に「円安」になることや、アメリカの代表的な株価指数である「ダウ平均株価」が高くなることは、日本の「日経平均株価」が上昇する動きと連動しやすい、という傾向があります。(多重回帰分析をすると、かなり強い相関関係が確認できます。)
また、為替は私たちの生活にも直接影響しますよね。円高になれば輸入品(例えば牛肉など)が安く買えたり、逆に円安になると海外旅行の費用が割高になったりします。
このように、経済全体にも私たちの暮らしにも影響が大きい為替ですが、そのレートはどうやって決まっているのでしょうか? 今日は、その基本的な仕組みである「固定相場制」と「変動相場制」について見ていきましょう。
為替相場のキホンは「固定相場制」と「変動相場制」
簡単に言うと
- 固定相場制→国が他の国の通貨(例えば米ドル)に対して、自国通貨の交換レートを一定に「固定」する制度。
- 変動相場制→為替レートを固定せず、外国為替市場での需要と供給のバランスによって日々「変動」するに任せる制度。現在、日本やアメリカなど多くの先進国が採用しています。
昔は「固定相場制」が主流だった?金本位制の時代
実は、第二次世界大戦後しばらくの間、世界の多くの国は「固定相場制」を採用していました。その中心となったのがアメリカのドルです。
なぜドルが世界の中心(基軸通貨)になり得たのでしょうか? それは、当時のアメリカが「ドルと金(ゴールド)を、いつでも決まったレートで交換しますよ」と約束していたからです(金ドル本位制またはブレトン・ウッズ体制と呼ばれます)。
この「ドル=金」という信用があったため、各国は自国通貨とドルの交換レートを固定することで、間接的に金の価値に裏付けられた安定した通貨制度を築くことができました。この大元の考え方は、各国が金の保有量に応じて通貨を発行し、その価値を保証する「金本位制」に遡ります。
「固定相場制」のメリットと限界
固定相場制の大きなメリットは、為替レートが変動しないため、貿易を行う企業(特に輸出企業)にとっては、為替変動リスクを心配せずに安定した取引ができる点です。
しかし、良いことばかりではありません。
固定相場制を維持するためには、自国の経済状況に関わらず、為替レートを維持するように金融政策(特に金利)を調整する必要が出てきます。例えば、アメリカが金利を上げたとします。すると、円で預金するよりドルで預金した方が有利になるため、皆が円を売ってドルを買おうとします。
変動相場制ならこれで円安になりますが、固定相場制では円の価値を維持しなければなりません。そのためには、日本もアメリカに合わせて金利を上げざるを得なくなる、といった状況が起こりうるのです。
国内の景気が良くない時に金利を上げなければならない…となると、国内経済にとっては大きな負担になりかねません。特に、日本のように輸出産業への依存度が比較的高くない国にとっては「一部の輸出企業のために、なぜ国全体の経済状況に合わない金融政策をとるのか?」という疑問も生じます。
また、金本位制のように「金の保有量」で発行できる通貨の量が決まってしまうと、経済の成長に合わせて柔軟にお金の量を調整することが難しくなります。これは、前回お話しした「信用創造」の規模も制限してしまうことになり、経済活動を停滞させる(デフレを招く)可能性も指摘されていました。
そのため、各国は金の保有量に縛られず、自国の経済状況に合わせて通貨を発行する「管理通貨制度」へと移行していきました。
多くの国が「変動相場制」を選んだ理由と「トリレンマ」
こうした固定相場制の持つ矛盾や、より自国の経済状況に合った金融政策を行いたいという考えから、1970年代以降、多くの国が変動相場制へと移行しました。変動相場制のもとでは、通貨の価値(為替レート)は、その国の経済力や政治的な安定性、将来性などへの「信用」を反映して、市場で決まることになります。
ここで、国際金融における重要な原則「国際金融のトリレンマ」をご紹介します。これは、
- 自由な資本移動(お金が国境を越えて自由に行き来できること)
- 為替相場の安定(固定相場制)
- 独立した金融政策(自国の経済状況に合わせて自由に金融政策を決定できること)
この3つは、同時に実現することができない、という原則です。どれか2つを選ぶと、残りの1つは諦めなければならない、というジレンマがあるのです。
現在の日本や多くの先進国は、「自由な資本移動」と「独立した金融政策」を選択しています。その結果、「為替相場の安定(固定相場制)」は諦め、「変動相場制」を採用しているわけです。 一方で、例えば中国などは、「為替相場の安定」とある程度の「独立した金融政策」を維持するために、「自由な資本移動」をある程度制限する、という政策をとっていますが、これには国際的なプレッシャーも伴います。
「なるほど…為替って、ただ数字が動いているだけじゃなくて、国の歴史や政策、世界との関係が絡み合っているんですね…」 と同僚。為替のニュースを見る目が、少し変わりそうですね。
経済の仕組みは本当に奥が深いですが、少しずつ理解を深めていけると、世の中の動きがより立体的に見えてくるかもしれませんね。私も皆様と一緒に、学び続けていきたいと思います。
それでは、次回もお楽しみに! 今週もどうぞよろしくお願いいたします。
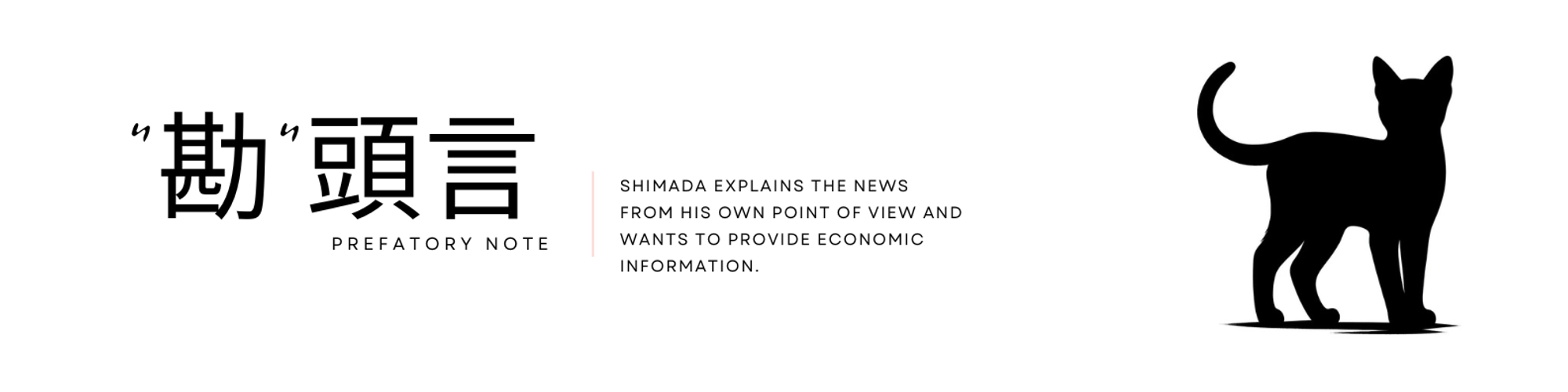 【“勘”頭言】みんなでひらく会社の未来から学ぶ
【“勘”頭言】みんなでひらく会社の未来から学ぶ
皆様、こんにちは。 ハンズバリュー株式会社の変革者・作家、島田慶資です。
先日、山形県中小企業家同友会の定時総会のグループ長研修が開催されました。 株式会社吉村の代表取締役社長・橋本久美子氏(東京同友会代表理事・中同協女性部連絡会代表)より「みんなでひらく会社の未来~総意と自主性が付加価値と新たな市場をつくる~」というテーマでミニ報告を伺うことができました。
創業90年を超える茶袋メーカーである株式会社吉村が、日本茶の需要減少という大きな変化の中、社員の総意と自主性を引き出し、新市場をひらく具体的な取り組みを実践している様子は、大変勉強になりました。
なかでも印象的だったのは、「サンタクロースの経営理念は何か?」という比喩を通じて“仕事の本質は何のためにあるのか”を考える大切さが語られた点です。
今回は、橋本社長の事例をもとに「未来をひらく企業づくり」へのヒントを共有したいと思います。
株式会社吉村の事例 — 総意と自主性が生む新たな市場
株式会社吉村は、茶袋製造の老舗として長きにわたり日本茶産業を支えてきました。しかし、日本茶の需要低下や市場環境の変化に対応するためには、これまでの常識にとらわれない新しい商品や販路を開拓する必要がありました。
そこで同社が注力したのが、「社員の創意」を活かす経営への転換です。心理的安全性を高める仕組みづくりと、経営者自身が“未来質問”を繰り返すことで、社員から率直な意見を集め、それらをすぐに試行する風土を形成してきました。
抹茶を手軽に楽しめるシェイカーや、茶器・スイーツの開発など、多彩な新商品が生まれる背景には「社員こそが商品開発の主役」という考え方があります。
結果的に、伝統的な茶袋メーカーの枠を超え、付加価値の高い商材へとビジネスを広げることにつながっています。
経営理念とサンタクロース — 本質を捉える視点
橋本社長が経営指針を作成する際「サンタクロースの経営理念は何だろう?」という先輩経営者の問いかけを受けたエピソードはとても印象的でした。サンタクロースの“仕事”はプレゼントを配ることですが、その“理念”は「子どもたちの笑顔や喜びをつくること」です。まさに“何のために仕事をするのか”の本質を端的に示しています。
この比喩を取り入れることで、企業の経営理念が現場社員にとってもイメージしやすいでしょう。
「われわれは何のために、誰のためにこの仕事をしているのか」を明文化することで、日々の厳しい業務に向き合う姿勢やモチベーションに大きな変化が生まれます。
未来質問の活用 — 心理的安全性を育む実践
株式会社吉村では、課題に対して「なぜうまくいかないのか」よりも「どうすればうまくいくか」を問いかける“未来質問”が浸透しています。社員が自由にアイデアや提案を出しやすい土壌には、心理的安全性を重視する経営姿勢が不可欠です。
失敗を過度に責めるのではなく、チャレンジする過程を評価し合う社風が整っているからこそ、新しい市場を切り拓く創造的なアイデアが生まれ続けているのです。
私自身の所感と今後の展望 — 経営者としての責任と行動
ミニ報告会を通じて、島田自身も「理念を具体化することで社員と喜びを共有する」大切さを改めて実感しました。
山形県同友会のような経営者同士の学び合いの場では、それぞれの会社で起こっているリアルな課題が具体的に共有されるため、経営課題に対するヒントが無数に見つかります。
島田自身も「何のために仕事をするのか?」という問いを常に心に留め、自社の社員と「サンタクロースの経営理念」のようにわかりやすい言葉で理念を共有していきたいと思います。
まとめ
グループ長研修で得られた学びは、単に経営手法のヒントだけでなく、経営理念の本質を見つめ直すきっかけとなりました。
プレゼントを配ることだけがサンタクロースの仕事ではないように、単なる製品・サービスの提供だけが私たちの最終目的ではありません。社員が何のために働き、どんな喜びを届けたいのかを明確にすることで、組織は強くなると実感しています。
これを機会に、さらに経営者同士のディスカッションを深めながら、「人を生かす経営」を実践していきたいと思います。
もし同友会の活動にご興味をお持ちの方は、ぜひお声かけください。 ともに熱い経営議論を交わし、未来をひらいていきましょう。(同友会、入会しましょう!)
今週もよろしくお願いします。
 【実店舗に効く話】驚異の反応率!?インフルエンサー活用のリアルと成功の秘訣
【実店舗に効く話】驚異の反応率!?インフルエンサー活用のリアルと成功の秘訣
皆さん、こんにちは。 ハンズバリュー株式会社のコンサルタント、津名久ハナコです。
すっかり暖かくなって、お散歩が楽しい季節になりましたね!☀️ 先日、お客様の会社へ車で向かう途中、綺麗な桜並木を通ったんです。ピンク色のお花を眺めながらのドライブは、本当に気持ちがいいものですね~🌸
お昼には、天童市にあるお気に入りの洋食屋さん「すみれ」さんへ。大きな窓から満開の山桜とソメイヨシノが見えて、絶景!😍 美しい桜を眺めながら美味しいパスタをいただいて、午後の訪問に向けてしっかり元気をチャージしました💪
さて、今回は、最近注目されている「インフルエンサー活用」について、皆様と情報を分かち合いたいと思います。実は、私たちハンズバリューでも、この分野の研究を進めているんですよ!
インフルエンサー施策って、実際どのくらいの効果があるの?
「インフルエンサーとのコラボ企画、どのくらいの反響が取れるんだろう?」 …皆様も、関心がありませんか?
先日、お客様のインスタグラムでコラボしていただけるインフルエンサーさんを募集した際、面談で興味深いお話を伺うことができました。
ズバリ、結論からお伝えしますね! インフルエンサーさんにお願いした場合のコンバージョン率(※)は、一般的に平均で5%~7%。そして、10%を超えると非常に優秀な成績と評価されるそうです!
(※コンバージョン率:ここでは、インフルエンサーさんの投稿を見て、商品購入やサービス申し込みなど、最終的な成果に繋がった割合のことです)
これ、どれくらい凄いかというと… ホームページのコンバージョン率って、一般的に1%いけばかなり優秀と言われるんです。なんと、その5倍から7倍もの数字が期待できる可能性があるということ…!これは驚きですよね!👀
なぜそんなに高い反応率が? インフルエンサーさんの裏事情
ただ、もちろん、いつでもコンスタントにこの数字が出るわけではないようです。 インフルエンサーさんも、普段から案件(企業からのPR依頼)ばかり紹介していると、フォロワーさんから「なんだか宣伝ばかりだな…」と思われてしまい、反応が悪くなってしまうとのこと。
だから、インフルエンサーさんは、フォロワーさんとの信頼関係を大切にし「ここぞ!」というタイミングで本当に良いと思った案件だけを選んで紹介するようにしているそうです。そうすることで、フォロワーさんの心に響き、高い反応率(コンバージョン率)を叩き出せるんですね。インフルエンサーさんの生活も、その厳選した案件で成り立っているという側面もあるようです。
なるほど~、ただ紹介するだけじゃない、プロの仕事なんですね!
インフルエンサーさんと上手にコラボするためのポイント
では、実際にインフルエンサーさんとコラボレーションする際には、どんな点に気をつければ良いのでしょうか? 私が重要だと考えるポイントをいくつかご紹介しますね!
1. 目的をハッキリさせる!
まずは「何のために」インフルエンサーさんに依頼するのかを明確にしましょう。お店や商品の認知度を上げたいのか、それとも具体的な購入や来店に繋げたいのか。目的によって、お願いする内容やインフルエンサーさんの選び方も変わってきます。2. 「誰に届けたいか」で選ぶ!
インフルエンサーさんのフォロワー数が多ければ良い、というわけではありません。自社の商品やサービスと親和性が高く、そのフォロワーさんが自分たちの届けたいお客様層(ターゲット)と合っているかが、とっても重要です!普段の投稿内容や、フォロワーさんからのコメントなども参考に、じっくり選びましょう。3. 想いを伝えて、一緒に創る!
「これを、この通りに紹介してください」という一方的なお願いだけでは、インフルエンサーさんの魅力が半減してしまうことも…。自社の商品やサービスの魅力、開発の想いなどをしっかり伝え、インフルエンサーさん自身の言葉で自由に表現してもらえるように、良好な関係を築くことを意識しましょう。一緒に企画を創り上げていくというスタンスが大切です。(お客さまからは丸投げできないか相談いただきますが、丸投げはお止めください。。。)4. 効果測定の方法を決めておく!
「なんとなく良かった」で終わらせないために、どんな指標で効果を測るかを事前に決めておきましょう。投稿の「いいね!」やリーチ数だけでなく、専用のクーポンコードを発行したりホームページへのアクセス数を計測したりするなど、目的に合わせた測定方法を準備しておくことが成功のカギです。可能性を秘めたインフルエンサー活用、まずは情報収集から!
インフルエンサー活用は、上手に行えば、ホームページだけではリーチできない層に効果的にアプローチできる大きな可能性を秘めています。
一方で、ただ依頼するだけでは期待した効果が得られないことも。今回ご紹介したようなポイントを押さえて戦略的に取り組むことが重要ですね!
「うちの商品に合うインフルエンサーさんって、どうやって探せばいいの?」 「具体的な費用感や依頼方法が知りたい!」
そんな風に思われたら、ぜひ私たちハンズバリューにご相談ください! インフルエンサー活用の第一歩から、具体的な施策の実行まで、皆様の状況に合わせてサポートさせていただきます!
まずは、身近なインフルエンサーさんの情報収集から始めてみてはいかがでしょうか?😊ぜひご参考ください。
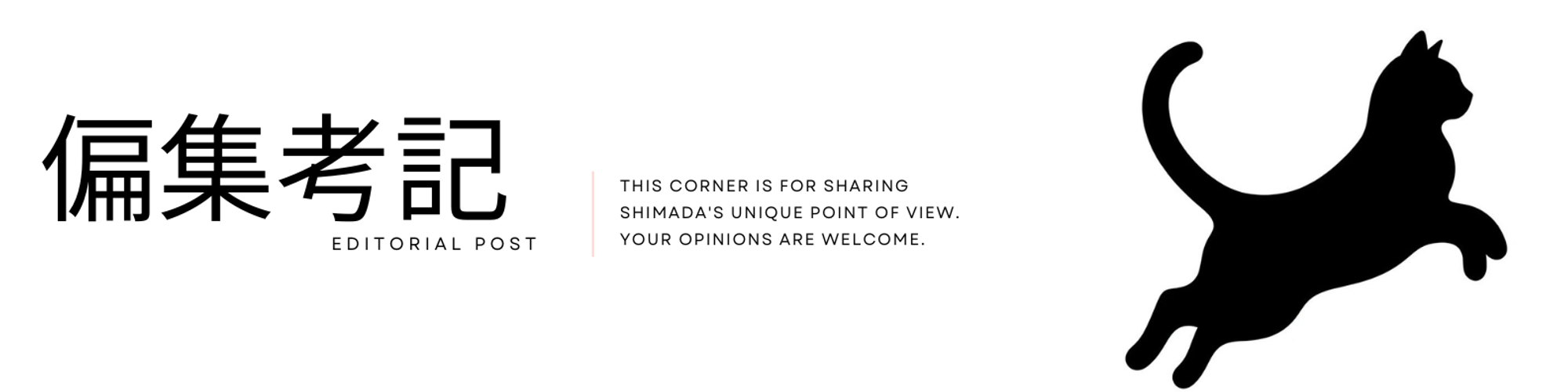 【偏集考記】あなたの会社には「分かち合う」仲間がいますか? 仕事の5段階と組織の壁
【偏集考記】あなたの会社には「分かち合う」仲間がいますか? 仕事の5段階と組織の壁
ハンズバリュー株式会社の変革者・作家の島田慶資です。 先日、あるお客様を訪問した際に、仕事への取り組み方(習熟度)について「仕事の5段階」のお話を伺いました。今日はそのお話を共有させていただければと思います。
仕事の習熟度、5つの段階
その5段階とは、以下の通りです。
- 知る段階
→勉強したり情報収集したりして、まずは知識として知っている状態。 - わかる段階
→先輩や上司から教わりながら自分で試してみたりして「なるほど、こういうことか」と理解が進んだ状態。 - 行う段階
→理解したことを指示されれば日常業務として実行できる状態。 - できる段階
→日常業務としてこなすだけでなく、自ら創意工夫を凝らしより高い成果を出せる状態。 - 分かち合う段階
→自身の知識・経験・スキル、そして会社の目標や理念などを、周囲の仲間と共有し、共に達成しようと働きかける状態。
立ちはだかる「2つの壁」
そして、この5段階の間には特に乗り越えるのが難しいとされる「壁」が2つある、とそのお客様は教えてくださいました。
一つ目は、「わかる」と「行う」の間にある壁。 これは、知識としては理解できても、なかなか実際の行動に移せない、あるいは継続できないという壁です。しかし、この壁は会社の仕組みや、上司・先輩からの適切なサポート、丁寧な関わり方によって、比較的乗り越えやすいものでしょう。
問題は、二つ目の壁です。それは「できる」と「分かち合う」の間にあるより高く、厚い壁です。
なぜ「分かち合い」の壁は高いのか?
個人のスキルとして「できる」レベルに到達した人が、なぜそれを「分かち合う」段階に進むのが難しいのでしょうか?
それは、この段階に至るには単なるスキルやノウハウの共有、あるいは制度・仕組みといった問題だけでは不十分だからです。そこには心の底から会社の方針やビジョンに共感し、仕事に対する誇りを持ち、仲間と共に成功したいと願う「精神性」が求められるからです。自分の成果や能力を独り占めするのではなく、組織全体の成功のために貢献しようという利他の心がなければ、この壁を越えることは難しいのかもしれません。
目標は「分かち合って」こそ、意味を持つ
このメールマガジンを読んでくださっている熱心な経営者の皆様は、きっと会社の理念やビジョンを掲げ、高い目標に向かって日々邁進されていることと思います。
しかし、どれだけ崇高な理念を掲げて野心的な目標を設定したとしても、それを心から「分かち合って」くれる仲間がいなければ、その目標は残念ながら「無いのと同じ」になってしまうのではないでしょうか。
組織であることの合理性とは?
会社に従業員という「仲間」がいる以上、仕事は社長一人のものではありません。それは「みんなで達成するべき仕事」です。もし社長一人で全てが完璧に回るのであれば、極論、仲間は不要ということになります。
仲間がいるからこそ、一人では到底達成できないような高い目標を目指すことに「合理性」が生まれます。そして、その目標が仲間一人ひとりに理解され、心から「分かち合われて」いる状態でなければ、組織としての力は最大限に発揮されません。
自問自答と、私たちの現在地
この5段階のお話を伺い、私自身深く考えさせられました。「ハンズバリューは今、どの段階にいるのだろうか?」「私自身は、どこまで『分かち合う』ことができているだろうか?」と。正直、反省すべき点がたくさん見つかりました。
現実的に見れば、どんな組織であっても経営者の想いや高い目標を最初から全員が完璧に「分かち合える」ということは稀でしょう。もしかしたら、最初は一人か二人、多くても三人程度かもしれません。
それでも「分かち合える仲間」を増やしていく
しかし、本気で高い目標を達成しようと願うならば、その「分かち合える仲間」を一人、また一人と増やしていく努力を、経営者は諦めてはならないのだと思います。
それこそが、「みんなで達成する大きな仕事」であり、私たちが個人事業主ではなく、法人として組織として存在する意義なのではないか——。私は、お客様からそのような問題提起をいただいたのだと受け止めています。
あなたと、あなたの組織はいかがでしょうか?
さて、皆様の会社ではいかがでしょうか。 心から理念や目標を「分かち合う仲間」は、どのぐらいいらっしゃいますか? そして、あなたは経営者として、どこまで「分かち合える組織」を目指していきたいですか?
組織のあり方、そして自分自身の関わり方を見つめ直す、良い機会かもしれません。
それでは、またお会いしましょう。 今日も一日、良い学びを。


