皆様、こんにちは! ハンズバリュー株式会社の島田です。
メールマガジンの感想、お待ちしております! 「読んでるよ」と言っていただければ励みになります(^_^)
目次
独り言コーナー
❶お米の価格高騰やトランプ・ショックなど、十分に予見できていたことが回避できていません。旧日本軍のお家芸「責任転嫁」「楽観主義」「戦力の逐次投入」「決断と実行の遅さ」「戦略目標よりも手順やメンツを優先」を、いまだに引きずっているように感じます。なぜに政府は変わらないのでしょうか。不思議に思います。
❷4月1日に山形・福島では雪が降りました。すでにタイヤ交換後だったので、すこし焦りましたが路面には積雪しなかったので一安心。
❸坊やの要望で某大手チェーン店で食事しました。商品に違和感を感じたので、ホームページから問合せしたところ、40分後に謝罪と説明の電話がかかってきました。きちんと商品の試食をしてからの電話で、誠意が伝わる対応で驚きました。はたして当社でも同様の対応が出来るのか。。。考えさせられました。
❹我が家のサステナブルとして、クズ野菜を冷凍して叉焼を煮込むときのダシに使っています。お肉の臭み取りにも効果的ですし、何より味に深みが出ます。皆様もクズ野菜の活用、お試しください。使えます!
❺坊やが年長さんに進級しました。新しい挑戦が始まる時期です。これまで毎日、彼のおしぼりを準備していましたが、年長さんになると自分でおしぼりを作るようになるそうで、その作業が不要になりました。 毎日「少し面倒だな」と感じていた作業がなくなると、彼の成長を強く実感すると同時に、彼と過ごす時間が確実に減っていることに気づきました。自分の時間が欲しいと思っていたものの、なんだかさみしさも感じてしまいます。
島田の気になるニュース
❶諦め感が強い報道ですね。我々就職氷河期世代を無視して、経済を壊した原因は自民党を含めた当時の政治家全員の責任。あの共産党でさえ、我々就職氷河期世代には無関心でした。そのツケが今に来ています。 2006年に小泉純一郎元総理が「改革なくして成長なし。痛みを伴う改革を今行わなければ、将来の世代に大きなツケを残すことになる。」とおっしゃっていました。答えあわせできそうですね。
2025年度の正社員採用予定、コロナ禍以来の低水準に
❷誰も得しない制度だったと思うのですが、いかがでしょうか?真面目に紹介している仲介業者さんはチャンスですね。
転職ころがしに歯止め 仲介業者の「祝い金」全面禁止
❸誰しもが考える実装をマネーフォワードが先手を打ちました。提供している自社の会計データはAI学習に活用されないのかなど疑問が残ります。
生成AIで財務分析「マネーフォワード クラウド連結会計 for GPT」公開
❹うーん、入力できる数値をしっかり把握できているならツールは不要のような気がします。支援者向けと割り切ると、活用できる場面はかなり限定的なのではないでしょうか?本当に誰得?
利益を得るための売上高をシミュレーションできる儲かる経営 キヅク君
❺消費税の減税発言も撤回。もうブレブレ。旧民主党政権を思い出しますね。民意で選ばれていない総理だと思うのは僕だけでしょうか。
石破首相また謝罪 予算成立後の「強力な物価高対策」発言で「ご心配、ご迷惑。申し訳なく思う」
【今週の経済入門】なぜハマる?なぜ沼る?恋愛とビジネスに潜む「サンクコスト効果」の心理学
皆様こんにちは、ハンズバリュー株式会社の秘書・勝頼ヒデコです。 いつもメールマガジンをお読みいただき、ありがとうございます。

4月に入り街ではフレッシュな新入社員の方々を見かける季節となりました。皆様の会社では、今年は新しい仲間を迎えられましたでしょうか? 当社では今年は新卒採用はありませんでしたが、自分が初めて入社式や歓迎会に参加した時のドキドキ感を、なんだか懐かしく思い出します。
さて、本日は、そんな春のウキウキした雰囲気とは少し角度を変えて「恋愛」に隠された経済学について皆様と考えてみたいと思います。
本日のテーマ『なぜか惹かれてしまう…その心理、経済学で読み解けますか?』
最近、接客を伴う飲食店などで、お客様が特定の方に夢中になるあまり、多額のお金(や時間)を費やしてしまい、結果的にトラブルになってしまう…といったニュースを目にすることがあります。
これを聞いて、皆様は不思議に思いませんか? 「なぜ、時間やお金をたくさん使っている側が、相手にそこまで惚れ込んでしまうのだろう?」と。本来であれば、相手がたくさん自分のためによくしてくれるから、関心を持つ…というのが自然な気もしますよね。でも、実際には逆のケースも多いようです。
実はこの現象、経済学で「サンクコスト効果(埋没費用効果)」と呼ばれる心理が働いています。
「もったいない」が引き起こす?サンクコスト効果とは
「サンクコスト(Sunk Cost)」とは、直訳すると「埋没費用」、つまり、すでに支払ってしまって、もう取り戻すことのできない費用(お金、時間、労力など)のことです。
そして「サンクコスト効果」とは、この「すでに投入したコストがもったいない」という心理から、合理的に考えれば撤退したり、方針転換したりすべき状況でも、それができなくなってしまう現象を指します。例えば、「せっかく途中まで読んだから」「ここまでお金をかけたから」と、面白くない本を最後まで読んでしまったり、うまくいっていない計画を続けてしまったり…皆様も、似たような経験はありませんか?
サンクコストが「執着」を生む?
先ほどのプロの女性がいる夜のお店のニュースに、このサンクコスト効果を当てはめて考えてみましょう。
お客様が、特定の方に対してお金や時間、そして感情的なエネルギーを「投資」します。その投資額(サンクコスト)が大きくなればなるほど、「これだけ時間とお金をかけたのだから、無駄にしたくない」「特別な関係なはずだ」という気持ちが強くなり、引き返すのが難しくなっていきます。
この「投資を回収したい(本人は投資とは思っていないでしょうが…)」という心理が、時に強い「執着」となり、それを「愛情」だと錯覚してしまう…。そして、その思いが行き過ぎてしまうと報道されるような金銭トラブルに発展してしまうのかもしれません。
このように人の感情や関係性を投資やコストといった側面から分析し、ある意味で「設計」しようとする考え方を「恋愛工学」と私は呼んでいます。(少しドライな響きかもしれませんが、経済学的な視点の一つとして捉えています。)
ビジネスにも応用できる?顧客ロイヤリティのヒント
「なるほど…『もったいない』って気持ち、分かりますけど、それが恋愛とかに繋がっているなんて、なんだか複雑ですね…」と、隣で聞いていたハナコも唸っていました。
「サンクコスト効果」の視点は、ビジネスにおけるお客様との関係構築にも応用できるかもしれません。
もちろん、お客様にとって本当に価値のある、良いサービスや商品を提供することが、商売の基本であり王道です。それは大前提とした上で、「お客様に自社のサービスやブランドに対して、何らかの形で時間や労力・感情を『投資』してもらう」という視点も重要なのではないでしょうか。
例えば、製品開発へのフィードバックをお願いしたり、会員限定のコミュニティに参加してもらったり、ポイントを貯めてもらったり…。お客様が「自分はこのサービスに関わっている」「時間や手間をかけた」と感じる経験は、単なる消費者として以上の深い愛着や「自分ごと」としての意識…つまり「ロイヤリティ(忠誠心)」を育むことに繋がります。
お客様が自ら進んで関与(投資)したという実感が、サービスへの満足感やブランドへの愛情、あるいは「やりがい」のようなポジティブな感情を生み出す…そう考えればお客様を「ロイヤルカスタマー」へと育てていくことは、決して難しいことではないのかもしれません。
厳しい経営環境が続く現代において、お客様との良好で長期的な関係性をいかに築いていくかは非常に重要なテーマです。その一つのヒントとして「サンクコスト効果」という人の心理を理解し、お客様の自発的な「関与」をデザインするという視点も有効なのではないでしょうか。
人の心と経済の動きは、本当に様々なところで繋がっていて知れば知るほど面白いですね。私も日々勉強です。
ハンズバリュー株式会社は、皆様のビジネスを成功に導くための様々な視点や情報を提供できるよう、これからも努めてまいります。
それでは、次回もお楽しみに! 今週もどうぞよろしくお願いいたします。
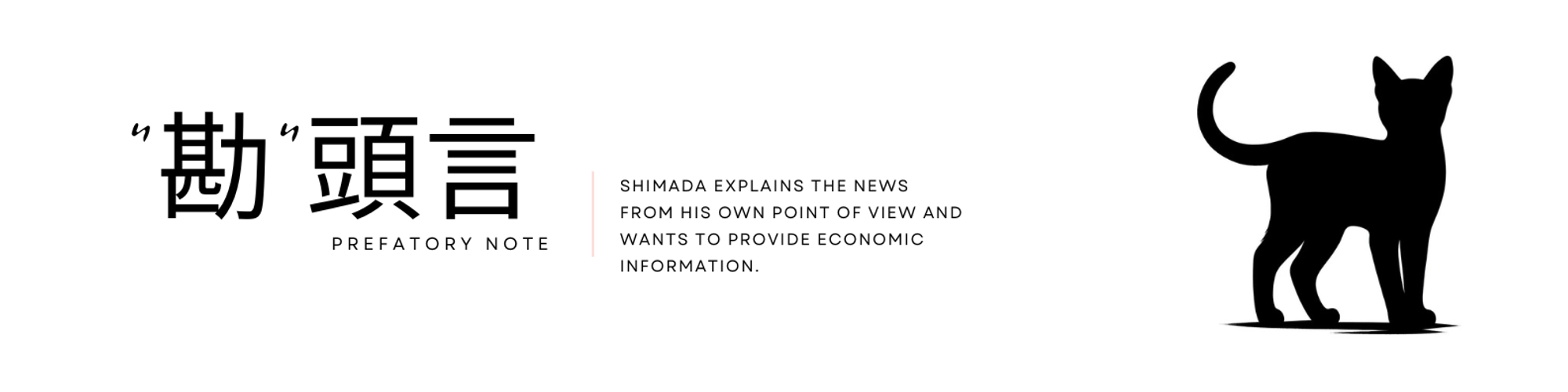 【“勘”頭言】出会いが生む新しい物語
【“勘”頭言】出会いが生む新しい物語
— 高校生起業家と中小企業をつなぐ価値創造のはじまり
皆様、こんにちは。 ハンズバリュー株式会社の変革者・作家、島田慶資です。
先日、高校生の起業家と中小企業を引き合わせる機会に恵まれました。高校生起業家は「山形をもっと良くしたい」「高校生と中小企業を結びつけて、新たな価値を生み出すような仕事をしてみたい」という強い思いから創業に踏み切ったそうです。
まだ学生でありながら、地元の未来を真剣に考え、具体的な行動を起こしている姿には大いに刺激を受けました。私自身もかつて創業したときのことを思い出しながら、その出会いをお手伝いしているうちに“人と人”“組織と組織”が結びつく瞬間の尊さを改めて考えさせられました。
互いを活かし合う関係 — 「あなたと私でならできる」の本質
そもそも、まったく異なる立場の人々がなぜ巡り合い、どのようにして“新しい価値”を創り出していくのでしょうか。
たとえば今回のように、高校生の起業家と中小企業の経営者が出会う背景には、明確な「こんなことができそうだ」という構想や「こんな人と組んでみたい」という思いがあるわけではなく、ときには純粋な好奇心や「面白そうだ」という直感的な興味がきっかけだったりします。
そうした出会いが動き出すとき“私はこれをやりたい、でも一人では達成しきれない”という想いと“うちにはこんな技術がある、でもそこに新たな発想を取り入れたい”という期待が、次第に共鳴を起こしているのではないでしょうか。
「私だけでは成し得ないけれど、あなたとなら実現できそうだ」という気持ちが芽生える瞬間こそ“新しい価値”の種が生まれるときだと感じます。
仕事の呼びかけとしての「つなぐ」という行為
この「私とあなたでならできるかもしれない」という感覚は、“営業”という言葉にも通じるかもしれませんが、ここで言う「営業」は何も商品やサービスを“売り込む”ことだけを指しているわけではありません。むしろ、誰かを“つなぐ”行為そのものに、すでに仕事の本質があるのではないかと思うのです。
たとえば、ある人が「こういう分野に強い会社を探しているんだけど、知り合いにいないかな?」と声をかけてきたとき、“あ、だったらあの人なら面白いことができそうだ”と閃いて紹介するような場面があります。
ここには売り手と買い手という構図ではなく、「この二人なら絶対に新しい価値を生み出してくれるだろう」というワクワク感が先行しているように見えます。そうやって“縁”が結ばれるとき、仕事は動き始め、今までになかった形で展開していくのです。
採用の場面に見える「新しい価値創造」の芽生え
「出会いが新しい価値を生む」という点は、採用の場面にも当てはまると思います。
会社側が人を募集するとき、単に“人手不足を解消したい”という理由だけで動いているわけではありません。実際には、「うちの組織にはこんな新しい力が加わると、さらに成長できるのではないか」「この人となら、自分たちがまだ見ぬ未来を切り開いていけるかもしれない」という期待があるのではないでしょうか。
そして、応募する側もまた「今ある社会的な価値や仕組みを、自分の力でどれだけ進化させられるだろうか」「この会社や仲間と一緒なら、何か面白いことができそうだ」という思いを抱えているかもしれません。そこに合意が生まれるとき、採用は単なる“雇用契約”にとどまらず“二人三脚で新たな価値を創り出す”物語の幕開けとなるのです。
4月がもたらす新しい物語の数々
毎年4月は、就職や転職、新事業のスタートなどを契機に、社会の至るところで“新しい顔ぶれ”と“これまでの枠組み”が出会う時期です。
学生だった人が社会人となって、新しい会社との出会いを重ね、その会社もまた新しいメンバーを迎えて未知のステージへ進んでいく。
こうした季節の移り変わりは“出会い”がいっそう活性化するきっかけにもなります。先日の高校生起業家と中小企業の出会いを目の当たりにして、私は改めて「出会いには、どこか加速度的な広がりがある」と感じました。
一度パズルのピースが噛み合い始めると、そこへさらに異なるピースが呼び寄せられて、次々と連鎖的に新しいプロジェクトや人々が加わってくる――まさに“物語”が動き出す瞬間です。
まとめ
高校生の起業家と中小企業の出会いが示すように、互いの想いが交錯し「あなただからこそやってみたい」「私とならば面白いことができそうだ」という期待感が高まったとき、そこには自然と“新しい価値を生む物語”が芽生えます。
私が感じたのは”ご縁”という概念もまた、この“私ひとりでは無理だけれど、あなたとなら実現できるかもしれない”という予感から始まるのではないかということ。そして営業や採用など仕事においても同じく「この人となら会社に新しい風を吹き込める」「この会社となら自分の力を試せる」といった思いが交わるとき、物語は一層鮮やかに動き出します。
4月という、新しい出会いが無数に重なる季節に、私たちはいくつもの“未来の物語”を目撃します。
そのひとつひとつに「想いを共有したい」「新しい何かを生み出したい」という情熱が宿るかぎり、出会いは絶えることなく続き、社会は少しずつ前へと進んでいくのだと信じています。
今週もよろしくお願いします。
 【実店舗に効く話】苦手なセールスが楽になる?
【実店舗に効く話】苦手なセールスが楽になる?
あなたの”弱み”を”強み”に変えるヒント
皆さん、こんにちは。 ハンズバリュー株式会社のコンサルタント、津名久ハナコです。 先週、山形ではなんと雪が降ったんですよ~!❄️ 4月に入って桜ももうすぐかな?なんてウキウキしていたのに、まさかの雪景色!びっくりしました!
もうノーマルタイヤに履き替えていたので、お客様のところへ向かう道中はドキドキ…。「ハナコちゃん、よく来たね~!」と温かく迎えていただけてホッと一安心でした😊
訪問すると、いつも温かいお茶とお菓子で迎えてくださるお客様。
「ハナコちゃん、いっぱい食べてね!」って、この日もおまんじゅうをいただきました😋 なぜか私が伺う時って、お客様がおやつを用意してくださることが多いんですが…私が来るからおやつを用意してくださるのか、おやつがあるから私が来るのか…最近、どっちが先なのか分からなくなってきました(笑)。いつも本当に感謝しております!
さて、今回は、私の大学時代の友人から、お仕事の相談を受けたお話です。 金融機関で働く彼女(サトコと呼びますね)が、営業ノルマの達成に悩んでいたんです。
「お願い…!クレジットカード契約してくれない?」涙目の友人…
先週の日曜日、山形市のカフェにて「ハナコ、お願い…!クレジットカードの契約、お願いできないかな?」と、少し切羽詰まった様子のサトコ。「いいけど…」と答えつつ詳しく聞いてみると、年会費がかかるタイプで私が普段使っているポイントが貯まりやすいカードと比べると正直メリットは薄そう…。
「契約しても、すぐ解約しちゃっていい?」と聞くと「6ヶ月だけ待ってくれたら解約してもいいから!」と…。
「でも、そんな営業、辛くない?続けられるの?」と心配になって聞くと「そうなの…お客様には全然相手にされないし、契約してくれたのは両親と祖父母だけ…。もうどうしたらいいか…」と、すっかり自信をなくしていました。
私はサトコの話を聞いていて「目標達成の道筋が見えていないんだな」と感じました。そこで一緒にノルマ達成について考えてみることにしました。
セールスは「説得」じゃない? 大事なのは「見極め」!
そもそもセールスって「お客様を説得すること」が目的だと思われがちですが、私たちハンズバリューは違う考えを持っています。一番大事なのは「説得する必要のないお客様、つまり本当にその商品を必要としているお客様を見極めること」と島田さんから教えていただいています。
そのためには、まずはお客様が「今、どんなことで悩んでいるのか」「そもそも、それを買うタイミングなのか」を聞く必要があるでしょう。
「お願い」する前に、たった30秒だけ聞いてみよう!
今回のクレジットカードの場合も、「お願い!」と切り出す前に「今、新しいクレジットカードって必要だと感じていますか?」と、まずはお客様の状況を30秒ほど聞いてみるべきだと考えます。
とはいえ、いきなり聞いても不自然です。 そこで「例えば、お財布を分ける感覚で仕事用とかプライベート用とか、専用のクレジットカードを作って収支管理を分かりやすくしませんか?」といった感じで、お客様の状況を伺うキッカケを作る提案をしてみました。
「話し下手」は「聞き上手」! 短所を長所に変える
サトコは元々、少し気弱で人に熱意をもってグイグイ話すタイプではありませんでした。でも、それって裏を返せば「じっくり人の話を聞ける」ということ!
その短所を長所として捉え「お客様の要望をしっかり聞くこと」に徹してみては?とアドバイスしました。
「短所」や「長所」って、実は単なる「特徴」でしかなくて、状況や場面によって、強みにも弱みにもなるんです。サトコのように、じっくり聞く姿勢がお客様の心を開くカギになることだってあるんです。
「そうだね…。私、お客様に熱っぽく粘り強く話すのって苦手だし、人の話を遮ってまで喋るのもできないし…」とサトコ。
ニーズを拾って、可能性を広げる!
しっかりお客様の話を聞くことができれば、たとえクレジットカードの契約に繋がらなくても「実は、こんなことにも困っていて…」といった、他のニーズを拾えるかもしれません。
投資信託や保険など、他の商品に繋がるかもしれませんし、あるいは他の担当者への「トスアップ(引き継ぎ)」に繋がる可能性がありますよね。お客様の本当の課題解決に貢献できるチャンスが広がるんです。
「200人に会えば達成できる!」数字で行動を見える化
さらに「買ってくれそうなお客様を見極める」という視点で考えれば、確率論で目標達成までの道のりが見えてきます。
例えば、クレジットカードの契約率が5%だと仮定すると、ノルマが10件なら200人のお客様にお会いすれば計算上は達成できるはずです。
「いつ達成できるか分からない…」と闇雲に動くのは辛いですが「200人に会えば達成できる!」と思えれば、少しやる気も出てきませんか?
目標が見えれば、あとはそれをスケジュールに落とし込むだけ。効率よく訪問するためにリストの中から近場のお客様をピックアップ。まずはご挨拶回り(名刺配り)から始めてその後に電話でアポイントを取って再訪する、といった具体的な作戦も立てられます。
結果は…?
その後、サトコはこの考え方で行動を変えてみたそうです。
すると、お客様の話をじっくり聞く中で、色々な相談を受けるようになり、他の商品契約に繋がったり先輩行員さんにスムーズに引き継ぎができるようになったり…。結果的に自信を取り戻しクレジットカードのノルマも無事に達成できたと、嬉しい報告をくれました!😊
あなたの「弱み」も、きっと誰かの役に立つ!
今回のサトコのように、自分が「苦手だ」「短所だ」と思っていることでも、見方を変えればそれがお客様の役に立つ「強み」になることがあります。
「私には才能なんてない…」なんて諦める前に、一度ご自身の「特徴」を客観的に見つめ直してみませんか? そして、具体的な行動計画に落とし込んでみませんか?
「自分の強みが分からない…」 「どうやって計画に落とし込めばいいの?」
そんな時は、ぜひ私たちハンズバリューにご相談くださいね! あなたの隠れた強みを見つけ出し、それを活かした具体的な一歩を一緒に考えさせていただきます!
ぜひご参考ください。
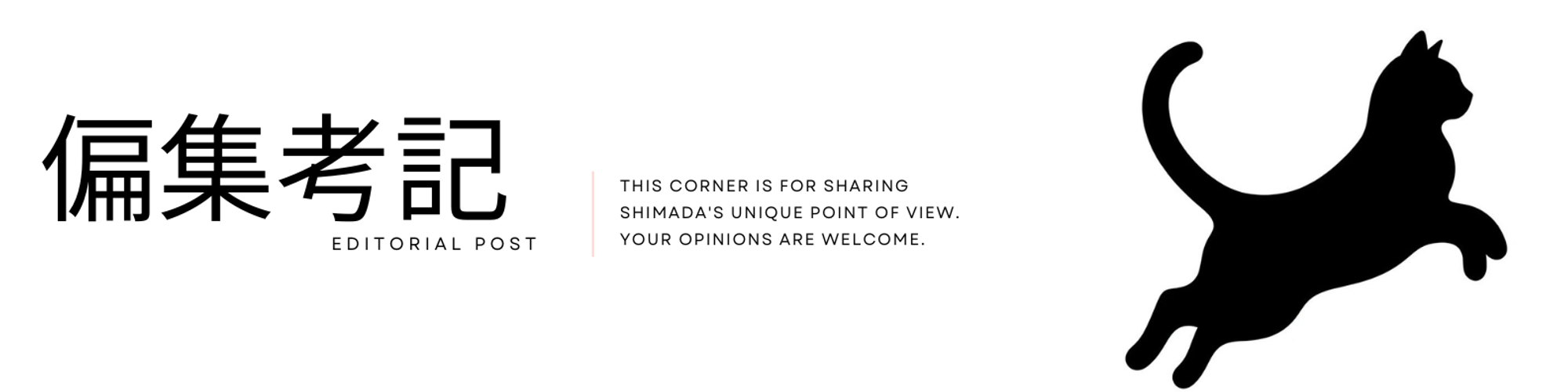 【偏集考記】事業承継を後押しする「営業の慣性力」とは? 創業者と後継者、それぞれの景色
【偏集考記】事業承継を後押しする「営業の慣性力」とは? 創業者と後継者、それぞれの景色
ハンズバリュー株式会社の変革者・作家の島田慶資です。
最近、会社の「営業」について考える中で、「慣性力」という言葉が頭に浮かびました。物理の世界でいう、物体が運動を続けようとする力のことですが、これは会社の営業活動にも当てはまるのではないかと感じています。
ゼロからイチを生み出す苦労
2009年に創業した当初を振り返ると、本当に手探りの毎日でした。「どうすればお客様に価値を届けられるのか」「どうすれば1万円の売上を立てられるのか」…その具体的な方法が全く分からず、暗中模索していたことを思い出します。
動き出した歯車が生む「慣性力」
それが現在では、大変ありがたいことに、日々お客様から様々なご相談をいただく機会に恵まれています。一つ一つのご相談に誠実に向き合わせていただく中で、毎日、安定した売上を見込めるようになりました。もちろん、そのためには前提条件がありますが、お客様の数を増やしていけば売上もより安定していく道筋が見えています。
この状況を可能にしているのは、まさに創業からの年数、お客様と築き上げてきた信頼関係といった「営業の慣性力」が働いているからだと考えています。 一度動き出した歯車が、次の回転を助けてくれるような感覚です。
事業承継における「慣性力」の価値
この「営業の慣性力」は、事業承継という場面において非常に大きな意味を持つのではないでしょうか。
後継者の方は、多くの場合この「慣性力」が働いている状態、つまり、ある程度の売上基盤や顧客との関係性が構築された状態で事業を引き継ぐことになります。これは島田がが創業当時に味わった「ゼロから1万円の売上をどう作るか」という類の苦労とは、また質の異なるスタートラインです。ある意味で大きなアドバンテージと言えるでしょう。
ただし「慣性力」に安住はできない
しかし、ここで注意が必要です。お客様も私たちと同じようにを重ね、ライフスタイルが変化し、(お客さまが)事業承継などを経験されます。その成長ステージの変化によって、当社とのお付き合いの形が変わったり、残念ながらお別れに繋がったりすることもあり得ます。
つまり、この「営業の慣性力」に甘んじていては、いつかその力も弱まってしまうということです。常に新しいお客様との出会いを求め、変化に対応し続ける努力は事業を継続する上で絶対に欠かせません。
そして何より、後継者には後継者ならではのプレッシャーや課題があります。創業者とは異なる「景色」の中で、新たな責任を背負い、会社を未来へ導いていかなければなりません。
創業者と後継者、それぞれの立場で
結局のところ、創業者には創業者の苦労があり、事業承継を受ける側にはまた別の種類の悩みや課題がある、ということなのでしょう。
私自身は創業側の苦労を経験しましたが、現在多くの後継経営者の皆様とご一緒させていただく中で、その立場ならではの「景色」や葛藤を日々学ばせていただいています。
まとめ
事業承継において、「営業の慣性力」は間違いなく大きな追い風となります。しかし、その風に乗りながらも、時代の変化を読み自ら力強く舵を取り続ける覚悟と行動が、後継者には求められます。
それぞれの立場で日々奮闘されている経営者の皆様を心から応援しております。
それでは、またお会いしましょう。 今日も一日、良い学びを。


