皆様、こんにちは! ハンズバリュー株式会社の島田です。
※社内で回覧していただいているお客さまがいらっしゃいました。ありがとうございます!!著作を明記していただけるのであれば、自由に配布ください。
メールマガジンの感想、お待ちしております! 「読んでるよ」と言っていただければ励みになります(^_^)
目次
独り言コーナー
❶福島市内の信夫山の里山歩きをサイクリングの代替として取り入れています。ぐるっと1周すると約70分。消費カロリーは600キロ前後。なかなか良い運動です。継続します😊
❷私事ですが、坊やに合った小学校に入学するため引越をして学区を変えることにしました。福島市内での移動になるのですが、福島駅からは遠くなります。飲んだ後の移動はどうしようか悩みます😥
❸坊やが保育園でサツマイモを掘ってきました。焼き芋にしてくれとオーダーをいただいたので、魚焼きグリルで焼いてみましたが、120分間焼き続けなければならず、焼き芋は買って食べるものだとの境地を開きました。
❹寒くなり年末へのカウントダウンが始まっているように感じます。次年度のカレンダーや手帳、高島易断なんかも見かけます。来年の一白水星は絶好調。信じているぞ高島易断!
❺坊やが保育園のお祭りでラップの芯でできた剣が売り切れてしまったため残念な表情でした。ペットボトルとラップの芯を組み合わせて粗末な剣を手作りしてみました。大好評。喜びはプライスレスですね。
島田の気になるニュース
❶経済対策を一切してこなかったので、当然の結果。ガソリン・軽油の暫定税率廃止と基礎控除引き上げは必須。再エネ賦課金も廃止が妥当でしょう。
京都だけじゃない日本人観光客離れ 東京など35都道府県で宿泊者減少
❷東京の仕事で、住まいは地方が最適解。その答え合わせではないでしょうか?たしか可処分所得は東京は最下位だったような気がします。
茨城県の可処分所得が全国1位!その理由とは?
❸退職代行サービス「モームリ」の従業員さんの内部告発。ホリエモンとの対談からきな臭い感じを受けていました。
「モームリ」弁護士あっせん疑い「社長は違法性認識」証言 元従業員「口止めされ」【知ってもっと】【グッド!モーニング】(2025年11月1日)※クリックで動画が再生します
❹動画生成AIで作ったフェイク動画。映画が大ヒットしているチェーンソーマンのワンシーン…のように見えるでしょう。品質がホンモノと同レベル。生成AIは便利ですが、これはやり過ぎ。
chainsaw man (YouTube Short)※クリックで動画が再生します
❺立場が弱いから働いているだけであり、立場が逆転したら裏切られるだけでしょう。日本人が嫌なことを、なぜ外国人は嫌がらないのか?想像力の欠如であり…深くは言いますまい。根本的に”稼ぎ方”が変わらなければ、弱い企業のまま何も変わりません。
残業断る日本人 嫌がらぬ外国人 「彼らがいたから会社続けられた」
【今週の経済入門】人口減少と経済発展は「無関係」である歴史的証拠
皆様こんにちは、ハンズバリュー株式会社の秘書・勝頼ヒデコです。 いつもメールマガジンをお読みいただき、ありがとうございます。

高市早苗新総理と片山さつき財務大臣のコンビによる新政権、早速目覚ましい活躍ですね🥰🎊 長年の懸案だったガソリンの暫定税率廃止について「財源がない」というこれまでの議論を一蹴し、国債発行(通貨発行)によって実行されそうなこと、本当に画期的です。
この議論の過程で、あるテレビ番組では河野太郎元デジタル担当大臣が「フェラーリやポルシェ(に乗る富裕層)にまで減税効果が及ぶのはふさわしくない」という趣旨の発言をされたと聞きました😥
ガソリン減税が地方経済や物流にどれほど重要かを無視した意見で本当に怒り心頭です。
(深呼吸して…)少し経済のことが分かってくると、世の中は全く違った景色に見えてくるのだなと実感いたします。皆様と一緒に経済の勉強を続けられることに感謝しております。
さて、本日は、日本の政府がいかに経済政策を間違え続けてきたか、という事実にも関連するお話です。 メルマガでも何度か触れてきましたが「人口の増減と、経済の発展はまったく関係がない」ということを、決定的な「反証事例」から皆様と共有したいと思います。
本日のテーマ『「人口が多すぎるから貧しくなる」と日本政府が国民を“輸出”していた時代』
「先輩、テレビや新聞では毎日『少子化で人口が減るから日本経済はもう成長できない』『デフレも人口減少が原因だ』って言ってますよね?」 後輩のハナコが、いつものように不安そうな顔で尋ねてきました。
「ええ、そうね、ハナコ。でも、もしその理屈が本当なら、昔……日本が『人口が多すぎること』を経済の問題だと真剣に悩み、国民を海外に“輸出”していた政策は、どう説明するのかしら?」
「えっ!? 日本国民を、ゆ、輸出、ですか…?」
そうなんです。皆様は日本がかつて国策として多くの国民をブラジルやハワイなどへ「海外移住」させていた歴史をご存知でしょうか。
明治から昭和にかけ、日本は世界第3位の「移民送出国」でした。 政府が主導し、貧困にあえぐ農村部の人々などを中心に累計80万人もの方々が海を渡ったのです。
では、なぜ政府はそんなことをしたのでしょうか。 驚くべきことに理由は「日本は人口が多すぎることが経済発展の問題だと考えていたから」です。
当時の日本政府や専門家たちは「人口が多すぎるせいで国内の富が分散してしまい、国民全体が豊かになれない」「人口過剰こそがデフレ(物価下落)の原因だ」と公然と論じていました。
まさに、今とは真逆の理屈です。
「えええ!? 待ってください、先輩! 今は『人口が減るからデフレになる』って言ってて、昔は『人口が多すぎるからデフレになる』って言ってたんですか? まったくの真逆じゃないですか!」 ハナコの言う通り、支離滅裂です。
国は、人口が多すぎて食えないからと国民を他国に送り出し、外貨を稼いでくることを期待しました。 これは、国内の人口を一時的にでも減らそうという政策に他なりません。
この歴史的な事実が、私たちに教えてくれることはたった一つです。 人口の増減そのものが、経済の発展やデフレと直接関係しているわけではない、ということです。
経済が成長するか停滞するかは、いつの時代も「国内の需要(モノやサービスを買う力)が足りているか」だけで決まります。人口が多かろうが少なかろうが、政府が通貨発行(国債発行)によって国民の需要を創出し、経済を回しさえすれば、経済は成長します。逆にそれをしなければ、いくら人口が多くても貧しく(デフレに)なるのです。
「人口が減るから大変だ」という言説は、もしかすると政府が緊縮財政という政策の失敗を「人口」という自分たちではどうしようもないもののせいにしたいだけなのかもしれません。
私たちが正しい歴史と経済の知識を持つこと。 それこそが、間違った議論に惑わされず、豊かな未来を選択する力になると信じています。
それでは、次回もお楽しみに! 今週もどうぞよろしくお願いいたします。
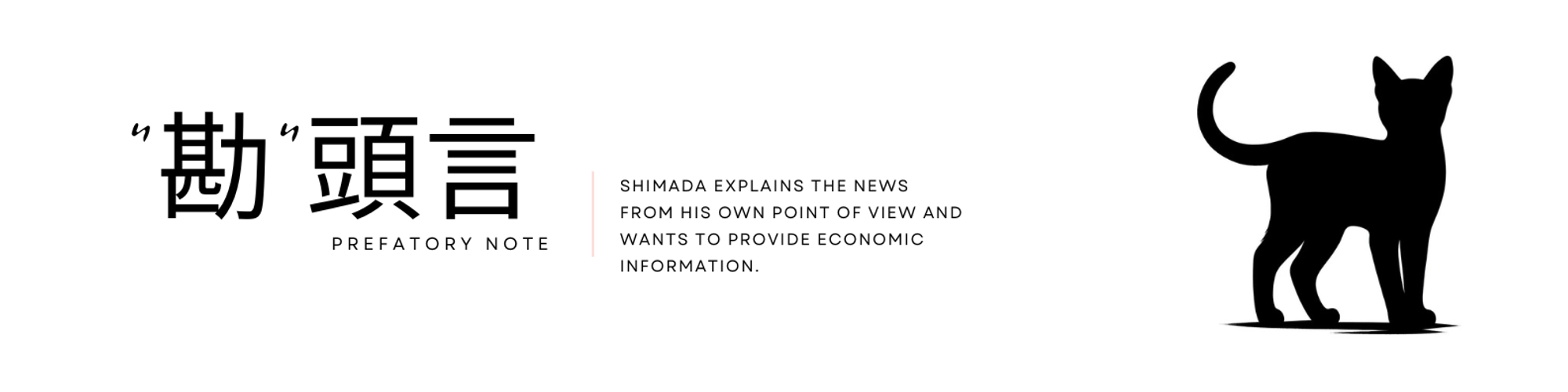 【“勘”頭言】「運任せの経営」から脱却する、たった一つの問い。変えようと思わなければ変わらない。
【“勘”頭言】「運任せの経営」から脱却する、たった一つの問い。変えようと思わなければ変わらない。
皆様、こんにちは。 ハンズバリュー株式会社の変革者・作家、島田慶資です。
先日、当社の朝礼で、ある社員からハッとするような問題提起がありました。 それは「私たちの会社の売上構成比は、本当に理想的な状態なのだろうか?」との事業の根幹に関わる問いでした。(この質問が朝礼で出ることに感謝しています😊)
あなたの会社の「安定収益」は何パーセントですか?
私たちは日々、お客様からのご依頼に全力で応えています。 その中には、スポット的なプロジェクトもあれば、保守契約のような継続的なお付き合いもあります。 しかし、その「スポット的な売上」と「継続的な安定収益」の比率を、これまで明確に意識し意図的にコントロールしようとしていただろうか?…社員からの問いかけに考えさせられました。
現状、当社の安定収益の割合は約30%。 残りの70%は、その時々のご依頼によって変動します。
もし、この安定収益の比率を50%まで高めることができれば、会社の経営はどれだけ盤石になるだろうか。 予算策定も、未来への投資も、より大胆にそして確信を持って行えるようになるはずです。
とある中古車販売店が「車検」に注力した理由
この議論の中で、私の脳裏に浮かんだのは、ある自動車販売会社の経営改革事例です。 その会社は以前、利益率が低く、業績が市況や営業力に大きく左右される「中古車販売」が事業の中心でした。まさに、その年になってみないと売上がどうなるか分からない「運任せ」の状態です。
しかし、その社長は「これではいけない」と決断します。 そして、安定的に収益が見込める「車検」や「リース」事業へ、意図的に経営資源をシフトさせていきました。 売上構成比を変革することで、会社は「運」に左右される事業体質から脱却し、安定した成長軌道に乗ることができたのです。
「変えよう」と思わなければ、何も変わらない
この事例が私たちに教えてくれる、極めてシンプルな真理。それは「経営者が『変える』と本気で意思決定しない限り、数字(構成比)は絶対に変わらない」ということです。
日々の業務に追われているだけでは、事業構造は変わりません。
むしろ、慣性の法則のまま、これまでのやり方を続けてしまうでしょう。売上構成比の変革は、経営者による強い意志と、具体的な戦略があって初めて成し遂げられるのです。
創業の原点を忘れず、次のステージへ
創業当初、お客様から500円をいただくことすらできなかった頃を思えば、今、こうしてお客様からお声がけいただける現状は、本当にありがたいことです。
その感謝を忘れることなく、そして、社員からの問題提起を真摯に受け止めて「売上構成比の意図的な変革」に取り組むステージに来たと確信しています。
安定収益を増やす努力。離脱を防ぐ努力。そして、新たな挑戦。
この三つのバランスを、データに基づいて冷静に見つめ、来期の経営に活かしていく。その決意を新たにしました。
さて、皆さんの会社の「安定収益」は、今、何パーセントでしょうか。 その比率は、意図して創り上げたものでしょうか、それとも、日々の活動の結果としてそうなっているだけでしょうか。
今週もよろしくお願いします。
 【実店舗に効く話】「新聞に載ったのに、問合せが来ない…」社長様へ。“広報の成果”を集客に繋げる活用術
【実店舗に効く話】「新聞に載ったのに、問合せが来ない…」社長様へ。“広報の成果”を集客に繋げる活用術
皆さん、こんにちは。 ハンズバリュー株式会社のコンサルタント、津名久ハナコです。
10月もあっという間に過ぎ、街は少しずつ冬の装いですね。 当社では毎年11月に、社員はもちろん、日頃お世話になっている制作パートナーの方々もお招きして、盛大なクリスマス会を開催しています🎄
日中から行い、お子様連れのご家族も安心して参加できるようにしているので、毎年大盛り上がり! 私たち社員も、前日からお酒を断ち(!)、ビンゴ大会や社長クイズ大会などの余興準備に全力を注ぎます。今年もみんなで絆を深められるのが、今からとても楽しみです!
さて本日は、そんな「絆」や「信頼」の作り方にも通じる「広報活動」についてのお話です。 先日、広報支援させていただいた行政書士の綾香先生から、嬉しいご報告と、次なるご相談をいただきました。
「新聞に載ったのに…なぜ新規の問合せがゼロなの?」
お昼過ぎ、一本のお電話が鳴りました。
「もしもし、ハナコちゃん?行政書士の綾香です!あのね、この間の広報支援、うまくいったわよ!」
「先生、おめでとうございます!やりましたね!」
「ありがとう!新聞に載った途端、既存のお客様や取引先の金融機関さんからも『すごいですね!』って声をかけてもらえるようになって。本当に取り組んでみて良かったわ」
電話口の綾香先生は、とても嬉しそう。しかし、その声には続きがありました。
「…でもね、ハナコちゃん。すごく喜んではいるんだけど、実は、新規のお客様からのお問い合わせは今のところ全くないの」
なるほど…!綾香先生、ご不安ですよね。それこそが、多くの企業が陥りがちな「広報の落とし穴」なんです。 今日は皆様と一緒に「広報(PR)」と「集客(リード獲得)」の違い、そして「広報の成果をどうやって集客に繋げるか」について、整理してみたいと思います!
「広報」と「集客」は目的が全く違います!
まず、大前提として知っておいていただきたいのが「広報」と「集客」は全くの別物だということです。
- 広報(PR)の目的 社会的な認知度を高め「信頼」を積み上げること。
- 集客(リード獲得)の目的 お客様から「問い合わせ」を直接いただくこと。
新聞記事に掲載されることは、あくまで「認知」と「信頼」を高める活動です。ですから、「記事に掲載された=すぐにお客様から電話が鳴る」という直接的な因果関係は、基本的にはありません。 (もちろん、広報活動を地道に続けていけば、結果として自然とお声がけいただける状況は作れますが、それは随分先の話です)
「新聞記事」は、ゴールではなく“武器”である
「じゃあ、せっかく新聞に載ったのに、意味がなかったの…?」 いいえ、そんなことはありません! その「新聞記事に掲載された」という事実はお客様の信頼を勝ち取るための最強の“武器”になるんです!
問題は、その武器を「どう使うか」。 広報で手に入れた「信頼」という武器を、今度は「マーケティング」や「セールス」の場面で、徹底的に活用していくのです。
【最強の武器(新聞記事)の活用法】
- 公式ホームページで「信頼」を可視化する
- 「掲載実績」のコーナーを新設し、記事を紹介する。
- トップページに、取材された新聞社のロゴを「掲載されました!」と表示する。
- ブログで「新聞に取り上げていただきました」という報告記事を書く。
- 営業資料(提案書)の“1ページ目”に追加する
- 初めてお会いするお客様は、あなたのことをまだ知りません。 提案の冒頭で「新聞にも取り上げられた、信頼できる専門家です」という事実を提示しましょう。
- SNSのプロフィールに明記する
- 「〇〇新聞 掲載」とプロフィール欄に一言添える。
- 掲載報告の投稿を「ピン留め」して、常に見えるようにしておく。
- あらゆるお客様接点で活用する
- DMやFAX、ご案内のチラシにも「〇〇新聞掲載!」と一言添える。
- メールの署名欄に「<メディア掲載>〇〇新聞(2025/XX/XX)」と加える。
このように、手に入れた「信頼」を、あらゆる場面で徹底的に活用することで「この人は素晴らしい先生なんだ」「しっかりした会社なんだ」という認識がお客様に刷り込まれ、商談の成約率向上や、リード獲得に繋がっていくのです。
「そういうことだったんですね!」綾香先生の決意
このご説明に綾香先生は深く頷かれました。 「なるほど…!そういうことだったんですね。ただ広報をやって満足しているだけじゃダメだったんだわ」
早速、綾香先生は、 「お客様に提案する資料に、今回の新聞記事をすぐに入れるわ!」 「ハンズバリューさん、トップページにロゴマークの掲載と、ブログ、プロフィールページの更新をお願いできる?」 と、次々とアクションを決めていらっしゃいました。😯
「広報」で得た武器を、「マーケティング」で使いこなそう!
広報(PR)だけやっていれば、自動的に集客ができるわけではありません。 広報で「信頼」という武器を手に入れ、それをマーケティングやセールスの現場で上手に使いこなす。この両輪が揃って、初めてビジネスは加速していきます。
皆様の会社にも、過去に取り上げられた新聞記事や雑誌の切り抜きが、眠っていませんか? その素晴らしい「武器」を、お客様の信頼獲得のために、今こそ活用してみてはいかがでしょうか。
「うちの“武器”って何だろう?」 「この掲載実績、どうやって活用すればいい?」 そんな時は、ぜひ私たちハンズバリューにご相談ください! 皆様が積み上げてきた「信頼」を未来の「集客」に繋げるための作戦会議を一緒にさせていただきます!
ぜひご参考ください。
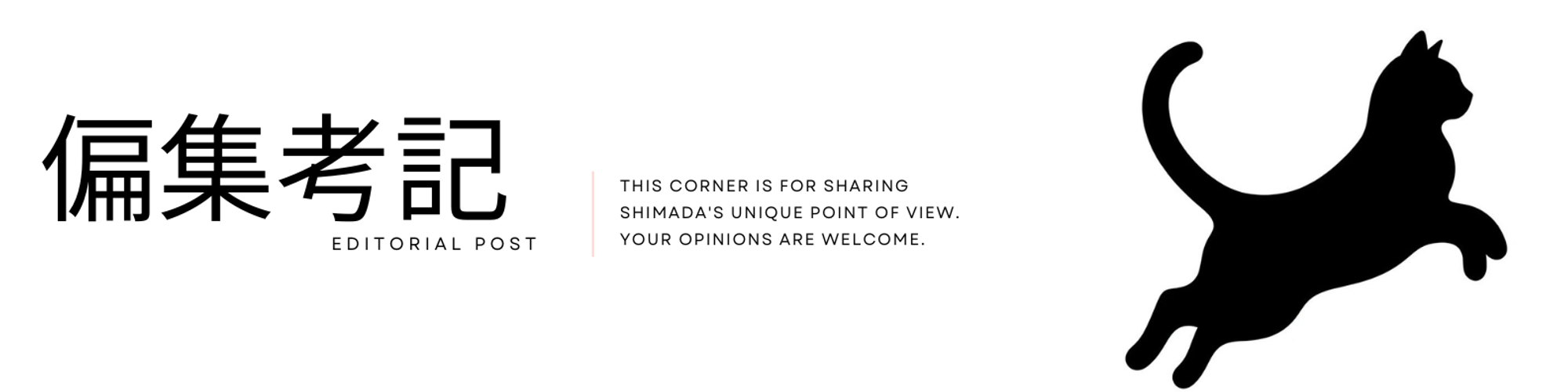 【偏集考記】「夢を語れるのは社長だけ」
【偏集考記】「夢を語れるのは社長だけ」
~経営指針づくりで再確認した社長にしかできないこと~
ハンズバリュー株式会社の変革者・作家の島田慶資です。
先日、山形県中小企業家同友会の「経営指針をつくる会in ティスビル補講」にて、受講生と共に経営指針書を深掘りする、大変貴重な勉強の機会をいただきました。その中で、普段何気なく使っている「言葉の定義」について、改めて考えさせられる場面がいくつもありました。本日は、その学びを皆様と共有させていただければと思います。
未来を語れるのは、社長だけ
同友会では、10年後の会社のありたい姿を描く「10年ビジョン」を作成します。このビジョンについて従業員さんに尋ねると、彼らは自分自身の10年後を想像することはできます。「自分は何歳になり、家族はどうなっているか」「どんなポジションで、どんな働き方をしていたいか」と。
しかし、会社の事業規模や、未来のお客様の姿については、想像することが困難です。これは、見ている景色、立っている場所が、社長とは全く違うのですから当然のことです。
だからこそ、会社の未来に夢のある定義を与え、その姿を具体的に語れるのは、この世で社長、あなた一人しかいないのです。この「夢を定義する責任」こそ、社長にしか果たせない、最も重要な役割の一つだと、私は改めて痛感しました。
資金計画における「人」とは、社長のこと
次に、よく使われる「企業は人なり」という言葉です。 この文脈における「人」とは誰でしょうか。私は、社長、あなた個人のことだと理解しています。
会社の財務戦略、資金の管理は、社長の意思決定、知識、経験、そして覚悟が、そのまま貸借対照表や資金計画に現れます。従業員さんが「借金をしましょう」と提案してくることはありません。
在庫の管理方法や売掛金の回収スピードも、すべては社長の決断一つです。
その意思決定が甘ければ、会社は無駄な借入金という経費を垂れ流すことになります。資金計画における「企業は人なり」とは、社長の実力が全てである、という厳しい現実を指していると考えます。
ティーチングとコーチングは、車の両輪
かつて「まずティーチング(教えること)ありき。コーチングは、それができた人に対して行い自主性を育むものだ」と考えていました。しかし、今の私の理解は違います。
もちろん、技術や知識をしっかり「教える」ことは大前提です。
しかし、それだけでは、人は「やらされ仕事」の域を出ません。本人の内側から「前向きに取り組みたい」という気持ちが生まれなければ、真の成長には繋がりません。 だからこそ「教える(ティーチング)」と同時に、本人が自ら「気づく機会(コーチング)」を提供することが不可欠なのです。
重要なのは、私たちの「姿勢」と「関わり方」そのものです。
社長の「やる気」が、会社の未来
そして、経営指針書の決意文には、社長の「やる気」が凝縮されて現れます。 社長が全ての責任を背負い、夢を描き、その実現に向かって前進していく。
従業員さんは、その「背中」を見て成長していくのです。もし、社長自身に不安や迷いがあれば、それは即座に企業の成長の鈍化に繋がります。
まとめ
夢を定義し、たった一人で財務の責任を負い、人の成長に深く関わり、自らのやる気で未来を切り拓く。 これら全てが、社長という存在に課せられた、重くも尊い役割です。
私は、中小企業家同友会での学びを通じて、こうした経営の原理原則に何度も立ち返る機会をいただいています。この学びの輪が広がり、地域にとって「なくてはならない会社」が一つでも多く増えることこそが、より良い未来を創る礎になると確信しています。
今週もどうぞよろしくお願いします。 良い学びを。


