皆様、こんにちは! ハンズバリュー株式会社の島田です。
※社内で回覧していただいているお客さまがいらっしゃいました。ありがとうございます!!著作を明記していただけるのであれば、自由に配布ください。
メールマガジンの感想、お待ちしております! 「読んでるよ」と言っていただければ励みになります(^_^)
目次
独り言コーナー
❶社員さんと力を合わせてYouTube動画を完成させることが出来ました。動画の品質や反響よりも、みんなが協力してくださったことに感謝しています。ありがたいし、だからこそ、より一層結果に繋げたいと強く思いました。
❷当メルマガ配信数は3年程かけて134人に配信しています。単純比較できないとは思いますが、YouTubeのチャンネル登録者数は現在24人。いつ頃、メルマガ登録者数をYouTubeが抜くのか楽しみにしています。なお、メルマガの開封率はおおよそ45%です。読んでくださっている方には感謝しております。年末にプレゼント企画もしたい!
❸ITCふくしまの20周年記念祝賀会に参加しました。YouTubeチャンネル登録者数40万人のYouTuberさとまいさんを講師に勉強しました。仮説力の重要性を改めて学びました。
❹久々に徹夜にちかい仕事をしました。徹夜は品質の低い仕事だとわかっていても、直前に仕事の依頼が重なるとどうしても避けられない。徹夜明けから2日間は体調が良くありません。年齢ですねぇ。。。
❺坊やが保育園で「トイレの花子さん」を教わったようです。一人でトイレに行くことを怖がるようになりました。これまでは、一人でトイレに行っていましたが「一緒に来てほしい」といわると作業がとまります。お化けを怖がるお年頃なんですね。
島田の気になるニュース
❶取材いただきました。当社のことより、山形の旅館ホテルにおける経営環境の厳しさや課題を共有できたことに嬉しく思っています。
旅館再生へ伴走支援、強み引き出し差別化 ハンズバリュー(山形)
❷上記のYouTubeチャンネルです。ぜひ、チャンネル登録をお願いします!毎週投稿していきます。
ハンズバリュー株式会社のYouTubeチャンネル「島田慶資のよい経営者になろう」
❸労働者としては歓迎。ただ、押しつけられている感じがしませんか?あわせて確認ください。
手引き作成に着手 ストレスチェックの義務拡大で 厚労省
「厚生労働省版ストレスチェック実施プログラム」を無料で配布
❹全ての都道府県で最低賃金が1,000円を超えました。SNSでリサーチすると社会保険料などの負担が多すぎて賃上げの効果が薄いと沢山のコメントがついていました。みんな、気がついてきているんですね。
すべての都道府県の地域別最低賃金の答申が出揃いました
❺ずーーっと続いている安定志向。いつ挑戦や成長志向の時代がありましたかね。失われた30年は継続していると思います。
新入社員「年功序列望む」5割超 就活生の「成長意欲」1割減
【今週の経済入門】石破政権の一年間を振り返る~私たちの暮らしはどう変わった?~
皆様こんにちは、ハンズバリュー株式会社の秘書・勝頼ヒデコです。 いつもメールマガジンをお読みいただき、ありがとうございます。

先日、石破総理が辞任を表明され、政界がにわかに慌ただしくなってまいりました。 後輩のハナコも「なんだか、めまぐるしいですね。この一年、私たちの生活って何か変わりましたっけ?」と戸惑っている様子でした。
確かに、日々のニュースに追われていると大きな変化を実感しにくいかもしれません。
しかし、この一年間にも私たちの暮らしや将来に深く関わる様々な経済政策が決定・実行されてきました。本日は、石破政権が取り組んだ主な経済政策を冷静に振り返ってみたいと思います。
本日のテーマ『石破政権の総括~「上げる政策」と「上げない政策」~』
この一年間の経済政策を振り返ると、ある部分では国民の負担を「上げる」あるいは所得を「上げる」一方で、別の部分では負担を「下げない」という、非常に特徴的なコントラストが見えてきます。
最低賃金の大幅引き上げと、遺族年金の見直し
まず、政権の最大の功績として語られているのが「最低賃金の大幅な引き上げ」です。2025年度には全国平均で時給1,121円となり、過去最大の上げ幅を記録しました。 政府は「2020年代に1,500円」という目標も掲げ「石破レガシー」とも呼ばれています。
「お給料が上がるのは、素直に嬉しいニュースですよね!」とハナコも言います。一面的には、物価高に苦しむ多くの人々にとって心強い政策であったことは間違いありません。しかしながら、社会保険の加入条件などの措置をしていないので働く時間を減らすだけに終わりそうです。そもそも社会保険料が重すぎて賃上げしても手取りは期待ほど増えないでしょう。
また、私たちの将来の安心に関わる制度変更も決定されました。それが「遺族年金制度の見直し」です。 これまで、夫に先立たれた妻が受け取る遺族年金には、原則として期間の定めがありませんでした。しかし今回の改革で、18歳未満の子供がいない一部の世代については、原則5年間で給付が打ち切られる「有期給付」へと変更されることになったのです。
私事ですが、私の母は若くして父を亡くし、遺族年金に支えられながら私を育ててくれました。もし、あの時に給付が5年で打ち切られていたら…と考えると、胸が痛みます。もちろん、制度の持続可能性を考えることは重要ですが、セーフティネットに関わる大きな変更であったことも事実です。最低賃金という「目に見える所得」を引き上げる一方で遺族年金という「万が一の支え」については、対象者を絞り込むという、まさに光と影のような二つの政策が同時に進められたのが、この一年間の大きな特徴でした。
「財源の壁」で見送られた減税策
次に、国民の期待が大きかったにもかかわらず「阻止された」あるいは「見送られた」政策について見てみましょう。
- ガソリン暫定税率の廃止
- 基礎控除(所得税)の大幅引き上げ
どちらも、実現すれば私たちの手取りを直接的に増やし、物価高の負担を和らげる効果が期待された減税策です。しかし、自民公明政権は一貫して「代替となる恒久的な財源が確保できない」として、その実施に慎重な姿勢を崩しませんでした。
お米の価格高騰と政府の対応
また、私たちの食卓に直結する問題として記憶に新しいのが「お米の価格高騰と品薄問題」です。 当初、政府は「流通の問題」と説明していましたが、消費者感覚とのズレが指摘され後に総理が陳謝。最終的には「コメの増産」へと政策を転換し、備蓄米の放出を行うという事態になりました。私たちの生活実感と、政策決定の間に距離があったことを示す出来事だったかもしれません。
振り返って見えてくるもの
こうして総括してみると、石破政権は、最低賃金の引き上げや防災庁の設立など特定の課題に対しては実行力を発揮する一方で、国民全体の負担を軽くする「減税」という選択肢には、最後まで「財源の壁」を理由に抵抗を貫いた、と言えるのではないでしょうか。
経済政策の評価は、立場によって様々です。 しかし、どのような政策が実行され、どのような政策が見送られたのか。その理由は何だったのか。それを知ることは、これから新しいリーダーを選ぶ私たちにとって非常に重要な判断材料となります。
政治の動きは、遠い世界のドラマのようにも見えますが、その一つ一つの決定が私たちの生活設計や会社の経営に直接影響を与えます。
ハンズバリュー株式会社としても、皆様が社会の動きを正しく理解し、賢明な判断を下すための一助となるよう、これからも情報提供を続けてまいりたいと考えております。
それでは、次回もお楽しみに! 今週もどうぞよろしくお願いいたします。
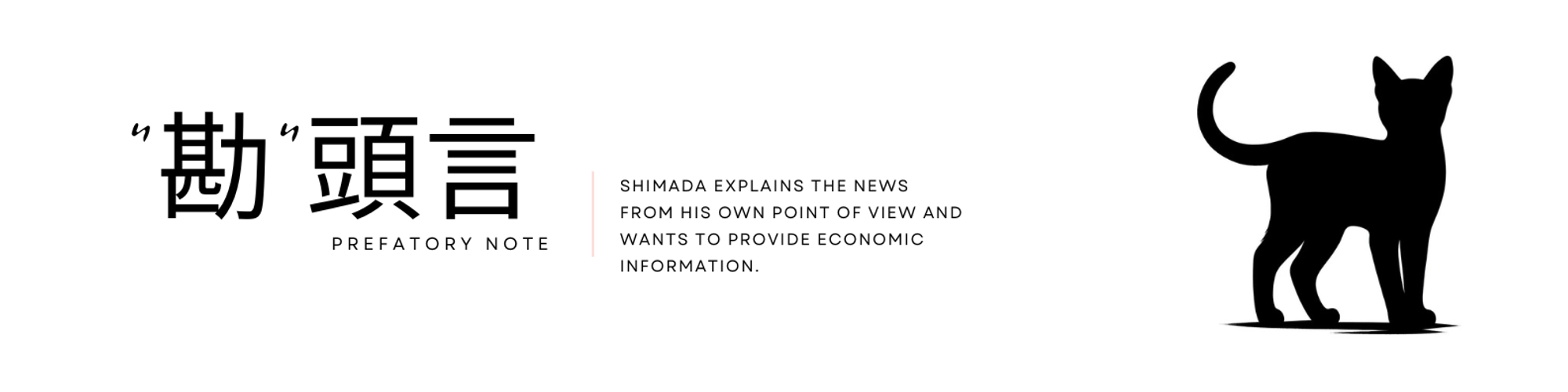 【“勘”頭言】「理不尽」と「合意」の狭間で、金融機関交渉の現場から学ぶべきことは?
【“勘”頭言】「理不尽」と「合意」の狭間で、金融機関交渉の現場から学ぶべきことは?
皆様、こんにちは。 ハンズバリュー株式会社の変革者・作家、島田慶資です。
お客様の事業再生をご支援する中で、金融機関との交渉が最後の最後で行き詰まる、という場面に何度も直面してきました。
もちろん、金融機関側にも社内調整や他の金融機関との協調といった事情があることは承知しています。
しかし、それでもなお「理不尽だ」と感じざるを得ない要求を突きつけられることがあるのです。本日は、そんな交渉の現場から見えてきた、厳しい現実について共有させてください。
金融機関との再生計画に関する面談は、常に流動的です。 しかし、一度「合意文書」として書面に残された計画は、絶対的な効力を持ちます。特に、利益計画や資金計画といった数字は、厳しい現実とは無関係に確定した事実として一人歩きを始めます。だからこそ、その策定には細心の注意を払わなければなりません。
金融機関もまた、自らの引当金をいくら積むのか、自己資本をどう守るのかという視点で交渉に臨んでいます。 そのため、時には観測気球を上げるように、実現困難なほど厳しい目標を要求してくることがあります。私たちは、事業者様が実行可能な範囲を必死で探り、修正案として粘り強く提案を続けます。
しかし、どうしても合意を得るために、当初の想定よりも高い目標を飲まざるを得ないケースも少なくありません。
具体的な事例を一つ、お話しさせてください。
ある製造業のお客様でのことです。数ヶ月にわたる厳しい交渉の末、ようやく再生計画の大枠が固まりました。その中で、返済原資については「税引後当期純利益に減価償却費を加えたキャッシュフローの70%を返済に充てる」という厳しいながらも何とか達成可能なラインで合意できる見込みでした。社長様も経営幹部様もようやく光が見えたと安堵の表情を浮かべていました。
しかし、最終合意のまさに土壇場でした。 メイン行の担当者から、一本の電話が入ります。「申し訳ありません。本店との最終調整の結果、返済額はキャッシュフローの80%でお願いすることになりました」。
一瞬、言葉を失いました。
「話が違うじゃないか」。
そう叫びたい気持ちを抑え、社長様は静かに受話器を置きました。たかが10%の違いと思われるかもしれません。しかし、この10%は、会社が未来のために再投資する資金であり、従業員の頑張りに報いるための原資であり、万が一の事態に備えるための最後の砦です。
それを失うということは、ただ自転車操業を続けるだけの未来のない経営を強いるに等しいのです。
ここで私たちが「初めに言っていたことと違う」とどれだけ訴えても、計画書に書いてしまえばテーブルが覆ることはありません。この調整に応じなければ、計画そのものが白紙に戻る。それが現実です。
このような理不尽とも思える状況の中で、どこに妥協点を見出し、お客様にとっての「最善の次善策」を確保できるか。それこそが、私たちコンサルタントの調整力が問われる瞬間なのだと痛感しています。
最終的に、そのお客様は80%という条件を飲むしかありませんでした。
しかし、この経験から私たちが学んだのは、ただ交渉の厳しさだけではありません。それは、一度交わした「合意」というものの絶対的な重みであり、経営者がその重みを背負う「覚悟」の大きさです。
金融機関との交渉は、数字のやり取りだけではありません。経営者自身の覚悟と事業の未来が試される、真剣勝負の場なのです。 その厳しい現実から目をそらさず、どう向き合っていくか。私たち支援者としも、その覚悟に寄り添い続けたいと考えています。
今週も皆様にとって、実り多き一週間となりますように。よろしくお願いします。
 【実店舗に効く話】「売って終わり」はもったいない!利益を安定させる“売った後”の稼ぎ方
【実店舗に効く話】「売って終わり」はもったいない!利益を安定させる“売った後”の稼ぎ方
皆さん、こんにちは。 ハンズバリュー株式会社のコンサルタント、津名久ハナコです。
9月も中旬に差し掛かり、朝晩はすっかり秋の空気になりましたね。先日、クローゼットの奥からお気に入りの秋物ジャケットを引っ張り出して、少し嬉しくなりました😊 一つのものを長く大切に使うって、なんだか素敵なことですよね。
実はこの「長く付き合う」という視点、ビジネスにおいても会社の利益を安定させるためのとっても重要なカギになるんです。
「売上は立つのに、利益が残らない…」工務店社長の悩み
先日、福島県で注文住宅を手掛けていらっしゃる腕利きの工務店・高島社長からご相談をいただきました。 「ハナコちゃんさぁ、うちは注文住宅だから、一軒一軒、お客様を集めるのが本当に大変でね。おかげさまで売上は立つんだけど、新規集客のコストがかさんで利益が圧迫されちゃってるんだよ…」
素晴らしい技術でお客様に最高の家を提供している高島社長。
そのお悩み、私も自分のことのように悔しくなりました。そこで私は社長にこうお伝えしたんです。 「社長様、ご相談ありがとうございます。ただ…もしかしたら、一つだけ、大事なことをお忘れではないでしょうか? あのスティーブ・ジョブズも、部下に絶対に忘れるなと言っていた『売った後のことを考える』という視点です!」
高島社長は、きょとんとした顔で「売った後…?」と呟かれました。
あなたの会社は「狩猟型」?それとも「農耕型」?
皆様の会社では、「売った後、何を売るか」を考えたことはありますでしょうか? 高島社長の注文住宅のように、一度きりの大きなお取引が中心の「売り切り」ビジネスだと、どうしても「納品して完了→また新しいお客様を探す」というサイクルの繰り返しになりがちです。これは、常に獲物を探し続ける「狩猟型」のビジネスと言えます。
しかし、統計データを見ても、新しいお客様を獲得するコストは、既存のお客様に再度購入していただくコストの、実に5倍から10倍もかかると言われています。 だとしたら、会社の利益を安定させるために一番効率が良いのは、一度ご縁があったお客様と、長く良い関係を築き、追加のご注文をいただく「農耕型」のビジネスへと考え方をシフトすることなんです。
お客様が次に困ることは?あなたの会社の「出番」です!
「じゃあ、注文住宅を建てたお客様に、次は何を売ればいいんだ?」 高島社長の疑問は、もっともです。
そこで、私はこうご提案しました。 「社長の会社は、腕のいい技術者集団ですよね!だとしたら、家に関する『アフターメンテナンス』でお客様の暮らしを末永くサポートするのはいかがでしょうか?」
家は、建てて終わりではありません。 エアコン、換気扇、水回り(お風呂やキッチン)など、暮らし始めると色々な場所でメンテナンスが必要になります。 腕のいい大工さんたちなら「いつ頃、どこが、どういう風に壊れやすいか」を経験則で把握しているはずです。
その知識を活かして「故障してから修理に駆けつける」のではなく「故障する少し前に、プロとして点検のご案内をする」のです。 例えば、「築5年、そろそろ水回りのパッキンが劣化してくる頃ですよ」「冬の前に、一度エアコンのクリーニングはいかがですか?」といった、先回りの情報提供やセミナーを行うのです。
それは、単なる「追加営業」ではありません。お客様の快適な暮らしを、建てた後もずっと見守り続ける「頼れるパートナー」としての大切な役割なんです。
「その視点はなかった!」社長の目が輝いた瞬間
このご提案に、高島社長は「なるほど…!その視点はなかったよ!お客様との関係が、家を建てた後も続くなんて考えただけでワクワクするな。よし、やってみよう!」と、パッと表情を明るくされました。
「売った後」にこそ、ビジネスチャンスの芽がある!
皆様の会社でも、お客様との関係が「売った時」で途切れてしまってはいませんか? お客様が、あなたの商品やサービスを使った後、次にどんなことで困るでしょうか? その時、あなたの会社がお手伝いできることは、きっと何かあるはずです。
「売った後」に何をするのか。お客様とどんな頻度で接触するのか。 その設計図をきちんと描けているか、ぜひ一度、確認されてみてはいかがでしょうか。
「うちのビジネスだと、“売った後”に何ができるだろう?」 「お客様と長く付き合うための、具体的な方法が知りたい!」 そんな時は、ぜひ私たちハンズバリューにご相談ください! 皆様の会社とお客様の間に、長く続く幸せな関係を築くための設計図を、一緒に描かせていただきます!
ぜひご参考ください。
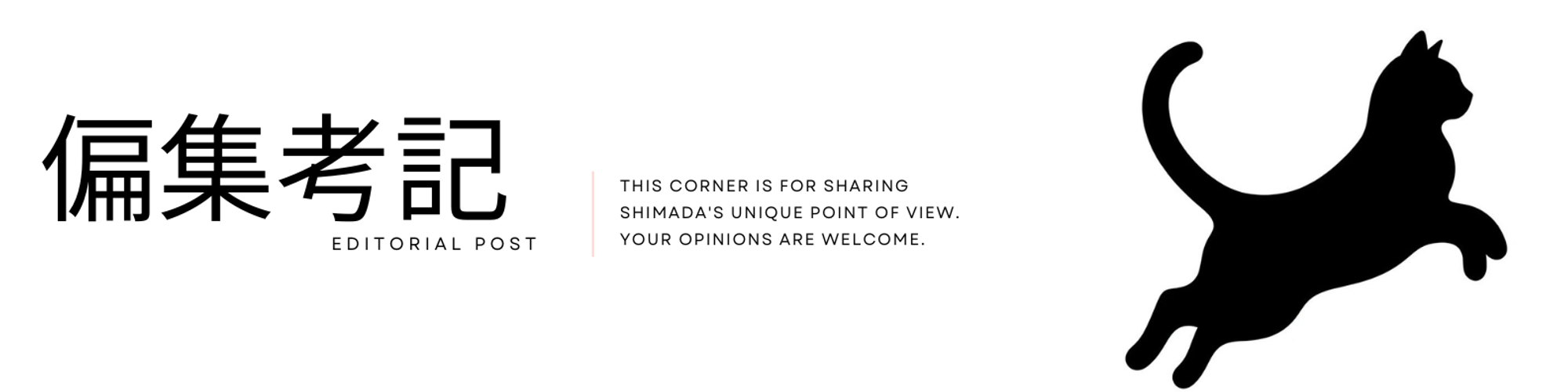 【偏集考記】「なぜ、あの人は分かってくれないのか?」の答えとは?一人ひとりの“世界観”を尊重する組織づくり
【偏集考記】「なぜ、あの人は分かってくれないのか?」の答えとは?一人ひとりの“世界観”を尊重する組織づくり
ハンズバリュー株式会社の変革者・作家の島田慶資です。
先日、過去に参加したセミナーの写真を整理していたところ、一枚の写真が目に留まりました。 写真に写っていたのは、組織づくりにおける非常に重要でありながら、私たちがつい忘れがちな原則でした。本日は、その学びを皆様と共有させていただければと思います。
大前提として、一人ひとりの「世界観」は違っていて当然
そのセミナーで深く頷いたのは「一人ひとりの世界観は違っていて当然」という言葉です。
私たちは、それぞれ異なる人生を歩んできています。生まれ育った文化的背景、受けてきた教育、大切にしている宗教や価値観、そしてこれまでの人生経験…。年齢や性別、性格やライフスタイルも、すべてが異なります。
これらの無数の要素が複雑に絡み合い、その人だけの個性的な「世界観」を創り上げています。
すれ違いは、なぜ起こるのか?
この「世界観」の違いこそが、日々のコミュニケーションですれ違いや対立が生まれる根本的な原因でしょう。
世界観が違えば、当然、物事の捉え方や考え方、何に価値を置くかも「十人十色」となります。知らず知らずのうちに持っている思い込みや先入観、思考の癖も、人それぞれです。
私たちは、自分自身の「世界観」というフィルターを通して物事を解釈しています。だからこそ「なぜ、あの人は分かってくれないんだ」「どうして、そんな考え方になるんだ」という不満が生まれてしまうのです。
目指すべきは「統一」ではなく「尊重」
ここで多くの組織が陥りがちな間違いは、全員の「世界観」を無理に一つに統一しようとすることです。異なる意見を封じ込め、同じ考え方を強要する組織は、一見するとまとまっているように見えるかもしれません。しかし、その内実是は、活気がなく、新しいアイデアが生まれない、もろくて弱いチームです。
真に強いチームを作るために必要なのは「違う世界観を尊重する」という姿勢です。
自分とは異なる意見や考え方の背景にある、相手の「世界観」に思いを馳せること。その違いを間違いとして断罪するのではなく、一つの個性的な視点として受け入れること。
「違い」を力に変える
社員一人ひとりが「自分の意見は尊重される」「自分とは違う視点も歓迎される」と感じられる組織では、活発に意見が飛び交うようになります。自分では気づかなかったリスクや、思いもよらなかった革新的なアイデアは、こうした「世界観の違い」の中からこそ生まれてくるのです。
この「違い」を対立の火種ではなく、組織を強くする力として活かすこと。それこそが、これからの時代を生き抜くリーダーに求められる最も重要な役割の一つだと、私は改めて確信しました。
読者の皆様に質問です。皆さんの会社では、一人ひとりの「世界観」は尊重されているでしょうか。その「違い」は、組織の力になっているでしょうか。
この問いに向き合っていただければ、何かヒントが見えてくるかもしれません。
それでは、またお会いしましょう。 今日も一日、良い学びを。


