皆様、こんにちは! ハンズバリュー株式会社の島田です。
メールマガジンの感想、お待ちしております! 「読んでるよ」と言っていただければ励みになります(^_^)
目次
補助金情報
①【中小企業全般】[1次公募]令和6年度補正予算
中小企業成長加速化補助金 100億円を目指す中小企業の補助金です。建物にも活用できる珍しい補助金です。
②【宿泊業のみ】宿泊施設サステナビリティ強化支援事業
5月30日まで。配管や空調、ボイラーに使える希有な補助金。観光庁のは短いんですよね。
③【宿泊業のみ】観光地・観光産業における人材不足対策事業
設備投資全般に使えます。省力化補助金よりも便利。
独り言コーナー
❶とある法人様で新入社員研修の講師を承りました。グループ討論とワークを挟んで気づきを得られるよう工夫をこらしました。素晴らしい人生を歩んでほしいと願っています。
❷SEO対策で検索順位1位を取ることが出来ていますが、最も寄与した打ち手は「外部リンク」。前向きに取り組めなかった期間は、まったく検索上位に表示することが出来ませんでした。きちんと向き合えば、結果は出る。そんなところでしょうか😌
❸補助金の情報が続々と出ております。お客様から期待していただいてお声をかけていただいております。感謝しています。しかしながら、6月頃まではまったく身動きできなくなりそうです。全社一丸体制で乗り切りたいです。
❹GoogleのAIモードにWEBマーケッターがざわついています。Googleの検索結果画面が、全部AI回答になるとのこと。 当然ではありますが、価値ある情報をどの程度ウェブに出しているかでお客様から選ばれる時代になりそうです。
❺坊やが押しているYouTuberの「ひげパパ」が絵本に登場したとのことで、おねだりされました。ある種、推し活ですね。
島田の気になるニュース
❶生成AIの進化が止まりませんね。南場社長が生成AIにオールインすると発表しています。バックオフィスは間違いなく生成AIに置き換わるんでしょうね。
SalesforceのCEOが「AI導入が成功したので今年はエンジニアを雇わない」と発言
❷続けて生成AI関連。ポイントは即時変換しているところ。近い将来は、Zoomなどでリアルタイム翻訳ができるかもしれませんね。(ユーチューブでは機械音声で翻訳してくれています)
世界最大のコールセンターがAIでインド人のアクセントを消している
❸もっと他にすることがあるだろう、というのが世論ではないでしょうか。
【SNS規制決定!】総務省ガイドラインが2025年4月1日施行へ 3.11の裏で密かに発表
❹今更感がありますが、追加報道です。責任取ってほしいですよね。どれほどの不幸をまき散らしたのか、想像もできません。
新型コロナウイルス、中国・武漢の研究所から流出可能性「80~95%」…ドイツ情報機関が極秘報告書
❺めでたいニュース。当初は2年間限定の暫定税率だったと記憶しています。それが約40年経過しています。税金はなくならない性質を持っているようです。新設する税金は、断固反対です。
【独自入手】ガソリン暫定税率の廃止を自民党執行部がほぼ決定!その背景とは?注目すべきは財務省の思惑【須田慎一郎】(クリックで動画が再生します)
【今週の経済入門】得意なことで勝負!『比較優位』って結局どういうこと?
皆様こんにちは、ハンズバリュー株式会社の秘書・勝頼ヒデコです。 いつもメールマガジンをお読みいただき、ありがとうございます。

先日、お客様の会社に後輩のハナコと訪問した際、なんと春らしい桜餅とお茶をいただきました!
「あぁ、もうそんな季節なのね…」と、しみじみしながら美味しくいただいていると、隣のハナコが一口でペロリ!あまりの豪快な食べっぷりに、お客様も笑って「たくさんお食べ」とお代わりの桜餅を3つも…!ハナコの胃袋は、まさに底なし沼です(笑)。
さて、本日はとても重要な経済学の概念「比較優位」について一緒に学んでいきましょう!
本日のテーマ『「比較優位」で、みんなハッピー?』
「比較優位」とは簡単に言うと「それぞれが得意なことをして、交換した方がみんなが得をする」 という考え方です。
「えっ、それって当たり前のことじゃないの?」とハナコ。でも、この「比較優位」実は奥が深いんです。
例えば、ハナコは桜餅を食べるのが、誰よりも得意です(笑)。一方、私は美味しいお茶を淹れるのが得意です。
もし、ハナコが美味しいお茶を淹れようとすると、時間がかかって桜餅を食べる時間も減ってしまいます。 逆に、私が桜餅をたくさん食べようとしても、ハナコにはかないません。
それならハナコは桜餅を食べることに専念し、私はお茶を淹れることに専念した方が二人ともハッピーになれますよね? これが、「比較優位」の基本的な考え方です。
「絶対優位」と「比較優位」の違い
さて、もう一歩踏み込んで考えてみましょう。「絶対優位」と「比較優位」の違いについて、整理しておきましょうか。
- 絶対優位: 他の人(国)よりも、少ない時間や資源で、より多くのモノやサービスを生産できること。
- 比較優位: 他の人(国)よりも、低い「機会費用」で、モノやサービスを生産できること。
「機会費用」とは、ある選択をすることで、諦めなければならない別の選択肢の価値のことです。ちょっと難しいので、例を挙げて説明しましょう。
日本とベトナムの例
| 国 | 自動車(1台生産するための労働時間) | 衣料品(1着生産するための労働時間) |
|---|---|---|
| 日本 | 10時間 | 5時間 |
| ベトナム | 50時間 | 10時間 |
この表を見ると、日本は、自動車も衣料品も、ベトナムよりも少ない時間で生産できます。つまり日本は両方の財で「絶対優位」にあります。
しかし、「機会費用」で比較すると話が変わってきます。
| 日本 | 自動車1台を作るために、衣料品2着を諦める必要がある。(10時間 ÷ 5時間 = 2着) |
| ベトナム | 自動車1台を作るために、衣料品5着を諦める必要がある。(50時間 ÷ 10時間 = 5着) |
つまり、日本は自動車を作る「機会費用」がベトナムよりも低いのです。これが「日本は自動車生産に比較優位がある」ということです。
同様に、衣料品1着を作る「機会費用」を計算すると…
| 日本 | 自動車0.5台 |
| ベトナム | 自動車0.2台 |
…となり、ベトナムは衣料品を作る「機会費用」が、日本よりも低いので「ベトナムは衣料品生産に比較優位がある」ということになります。
この場合、日本は自動車生産に特化しベトナムは衣料品生産に特化してお互いに貿易をすれば両国ともより多くの自動車と衣料品を手に入れることができるのです。
「比較優位」は、国際貿易の基本!
「比較優位」は、1817年に経済学者のデヴィッド・リカードによって提唱された、国際貿易の基本的な考え方です。それぞれの国が得意な分野に特化し、貿易を行うことで世界全体の経済が発展する、というわけですね。
(日本の自給率の低下も、根本的な原因はこの比較優位性の理論で説明することも可能なのです。 ただし、食料の安定供給は国家安全保障に直結するため欧米では強力な助成金・補助金を支給して比較優位性を無視しています。無策であるのは残念ながら日本だけです。)
しかし、この「比較優位」、あくまでも経済学上の理論的な話です。
現実の世界では、国の価値観の違いや、教育水準の違いなど、様々な要因が複雑に絡み合っています。 最近のロシアとウクライナの戦争を見ても、経済合理性だけでは国際関係を語れないことがよくわかります。
「比較優位」の考え方は、今後、アップデートされていく必要があるのかもしれません。
ハナコも、「経済学って、奥が深い…」と、感心していました。私も、まだまだ勉強不足です。もっと勉強したいです🥰
それでは、次回もお楽しみに! 今週もよろしくお願いいたします。
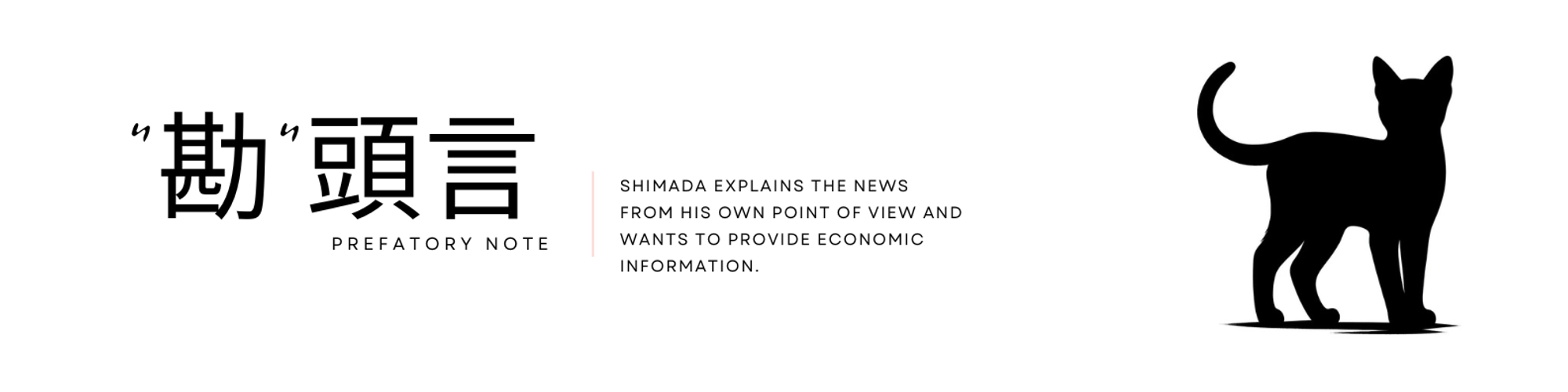 【“勘”頭言】バンクミーティングを通じて見えた個人資金と事業資金の境界— 役員借入金の正体
【“勘”頭言】バンクミーティングを通じて見えた個人資金と事業資金の境界— 役員借入金の正体
皆様、こんにちは。 ハンズバリュー株式会社の変革者・作家、島田慶資です。
先日、お客様である社長様と金融機関とのバンクミーティングに同席する機会がありました。会議そのものは融資条件や返済状況を確認する、ごく一般的な内容で進んでいましたが、金融機関の担当者が「返済さえしていただければ、そこはもう問題ありませんから」と言い放った瞬間、一瞬空気が変わりました。
表向きには穏やかなやり取りでしたが「返済原資がどこから来ているか」についての追及は深くなされないまま、ミーティングは淡々と終了。
ところが、担当者が退出した後、社長様にさりげなく「最近の資金繰りはどのような感じですか?」と確認すると、最初は「まぁ、何とかやっています」と曖昧な返答。具体的にはあまり言葉が出てこない様子でした。そこで私は、手元の決算書を開き、前年や前々年と比べて増えている“ある科目”に目を留めました。そう、役員借入金が毎年増えていたのです。
「社長、この役員借入金ですが、どのようにして調達されているのでしょうか?」
やんわりと尋ねると、一瞬間を置いて「いえ、まぁ…個人的に何とか用立てているだけで…」と、なおも口を濁されます。社長様も奥様の専務取締役もダブルワーク出来るほど楽な仕事ではありません。
さらに踏み込んで「もしかして、ご家族やご両親の支援も含まれたりしているのでしょうか?」と水を向けると、社長様はバツが悪そうにうつむき、ついに本音を打ち明けました。
「実は…両親の年金を少し預かって、それを会社に回していたんです。」
役員借入金の正体 — ご両親の年金が返済原資に
会社としての資金繰りに行き詰まったとき、足りない分を経営者個人がカバーする例は少なくありません。しかし、今回のケースでは社長様も奥様(専務)も他に収入源を持っておらず、手立てを考えても実質不可能な状態。途方に暮れた末、ご両親から毎月振り込まれる年金を会社の返済原資に回すようになってしまったというのです。
私は「これはやはり健全ではありません」とお伝えすると同時に、社長様も「分かってはいるけど他に方法がなかった」と肩を落とされました。金融機関とのやり取りが一見スムーズに見えていた裏で、こうした苦肉の策が用いられていたわけです。
個人資金と事業資金の線引きが曖昧になる理由
小規模事業者や個人事業主では、どうしても“社長=会社”という捉え方をしてしまいがちです。 売上規模が小さいほど、わずかな資金ショートでも社長のポケットマネーを補填しなければ事業が回らないケースも多いでしょう。
しかし、ご両親の年金など、本来は老後の生活を支えるための資金まで取り崩してしまうのは、家族全体にとって大きなリスクを伴います。しかも金融機関の視点では「返済が滞らなければ問題ない」とのスタンスも現実としてあります。このような構造的な無理が見えにくいまま放置される危険があるのです。
会計事務所との連携 — リスケジュールと事業計画の再構築
今回のケースでは、社長様に「このままではいつかご家族も生活できなくなる」という危機感を共有し、会計事務所の先生も交えて以下のアクションプランを取りました。
- 決算書を再精査し、現実的な事業の損益とキャッシュフローを可視化する
- 事業上の収益で返済できるギリギリのラインを想定し、リスケジュール(返済条件変更)を金融機関に相談する
- 今後の売上計画やコスト削減策など、現実的で具体的な事業計画を作り直す
- 個人資産に依存しない資金繰りを確立できるよう、金融機関との話し合いを粘り強く続ける
幸い、金融機関も「数字の根拠」が示されれば前向きに協力してくれました。無理のない返済スケジュールを敷くことで、ご両親の年金に頼ることなくキャッシュフローを回す道筋を作ることができたのです。
銀行との関係性 — “返済”という本質を忘れない
金融機関は、あくまで「お金を貸す」ビジネスです。返済が滞りなく行われる限り、大きな問題として表面化しづらいのは事実でしょう。しかし、経営者としては「返せているから大丈夫」という安易な考えにとどまらず、その返済原資がどこから来ているのかを常に意識する必要があります。
実際、社長様も「返済は遅れずにできている」という自負があったために、バンクミーティングでも深く追及されることはありませんでした。ところが、決算書をじっくり見れば、年々増えている役員借入金は“個人と事業の境界が曖昧”である証拠となります。
健全な企業経営に向けて — 個人を犠牲にしない仕組みづくり
バンクミーティング自体は、一見“無事に”終わるかもしれません。しかし、そこでごまかしが通ってしまうと、経営者自身が本質的な解決策を先延ばしにし、家族を巻き込んでしまう危険性が高まります。
本来であれば、会社の借入金は会社の利益から返済すべきもの。どうしても事業資金が回らない場合は、金融機関と正面から交渉し、返済計画を見直す努力が不可欠です。ご家族や個人の貴重な資産を守るためにも、専門家の協力を仰ぎながら健全な経営構造を再構築していくことが、結果的に最善策となるでしょう。
まとめ
バンクミーティングの後、濁されていた資金繰りの実情が決算書を通じて明らかになる――そんな場面に直面すると、あらためて“個人と事業の区分”の大切さを痛感します。
金融機関が「返済さえしてもらえれば構わない」と言うのは、彼らのビジネスの本質。私たち中小企業側としては、そのスタンスを踏まえた上で、無理のない返済計画を組み立て、会社としてしっかりキャッシュを生み出す仕組みを作り上げることが求められます。
「借りるときは簡単でも、返すときは苦しい」とよく言われますが、その“苦しさ”が経営者やご家族の人生まで脅かさないよう、今一度、事業と個人の資金の線引きを見直す必要があるのではないでしょうか。
今週もよろしくお願いします。
 【実店舗に効く話】ホームページ、見て満足されてない?!
【実店舗に効く話】ホームページ、見て満足されてない?!
~アクセスを「問い合わせ」に変える!魔法の導線設計~
皆さん、こんにちは。 ハンズバリュー株式会社のコンサルタント、津名久ハナコです。
すっかり暖かくなって、春爛漫!ですね!🌸 山形や福島の事業者様も、雪解けとともに、前向きな気持ちがムクムクと湧き上がってきているようで、私も、たくさんご相談をいただいております!
私の食欲も負けじとムクムク…!春の美味しいものを満喫しすぎて、体重計に乗るのが怖い今日この頃です…(;^_^A
さて、今回は、皆様からよくいただくご相談「ホームページからの問い合わせ」について、一緒に考えてみたいと思います!
先日、専門家の先生からご相談をいただきました。 「ハナコさん、ホームページを作って運用しているんだけど、全く問い合わせがないの…。どうすれば良いかしら?」
アクセスはあるのに、問い合わせがない?!~その原因は…?~
先生のホームページは、当社で設計させていただいたものでブログ機能も搭載されています。先生も、こまめにブログを執筆されていてホームページの情報量は非常に充実していました。
アクセス数を分析してみると…なんと、月に1,000人以上ものアクセスがあることが判明!地方の専門家のホームページで、しかも見込みのお客様がアクセスしていることを考えると…かなりのアクセス数です。
…にも関わらず、問い合わせがない。
問題は「アクセスはあるのに、問い合わせに繋がっていない」という点にあるのではないか、と私は考えました🧐
「ブログ記事」が最大の集客ポイント!…しかし…?
さらに詳しくアクセス状況を分析していくと、驚くべき事実が判明しました!
最もアクセスが多いのは、当然トップページ…と思いきや、なんと、先生が毎週執筆されている「ブログ記事」だったのです!
私も実際にブログ記事を拝見しましたが、先生が作成されたExcelやWordファイルの無料ダウンロードなどもあり読者にとって有益な情報が満載でした。
…しかし、ここに落とし穴があったのです!
ブログ記事を読んだお客様はそこで満足してしまい、問い合わせをしてこないのではないか?…私は、そう仮説を立てました。
「ブログ記事」から「問い合わせ」へ!~魔法の導線設計~
そこで、私は先生に提案しました。「ブログ記事から、問い合わせフォームへの、明確な導線を設置しましょう!」
具体的には、相続に関する雛形を提供しているブログ記事に…
- 全国対応可能であること
- Zoomで相談できること
- 「今、このブログ記事を読んだ方限定!30分無料相談受付中!」
…という特典を明記し、お問い合わせフォームへのリンクを設置しました。
つまり、「ブログ記事を読んで満足する」だけでなく、「もっと詳しく知りたい!」「相談したい!」と思ったお客様が、スムーズに問い合わせできるよう「魔法の導線」を設計したのです。
結果は…?
この施策を実行した結果…なんと、運用開始から1ヶ月で問い合わせを獲得することに成功しました!
「ブログ記事を読んで、すぐに相談できるのが良かった」「無料相談があるなら、気軽に問い合わせできる」…そんなお客様の声が、続々と届いています。
当社でホームページ制作を頼んでいただけているわけですから、結果に繋がって良かったです!
ホームページは、「見せる」だけでなく、「行動させる」!
ホームページは、単なる「情報提供の場」ではありません。お客様に「見てもらう」だけでなく「行動してもらう」ための重要なツール。
まだまだブログ記事は多くのお客様を集客できる強力なコンテンツです。しかし、ただ情報を発信するだけでなく、そこから「問い合わせ」という具体的な行動に繋げるための「導線設計」が不可欠でしょう。
「自社のホームページ、アクセスはあるのに問い合わせがない…」とお悩みの方は、ぜひホームページの導線設計を見直してみてください。
「どこを改善すれば良いか分からない」「効果的な導線設計の方法が分からない」という方は、ぜひハンズバリューにご相談ください!私たちと一緒に、ホームページを「最強の営業ツール」に変身させましょう!
ぜひご参考ください。
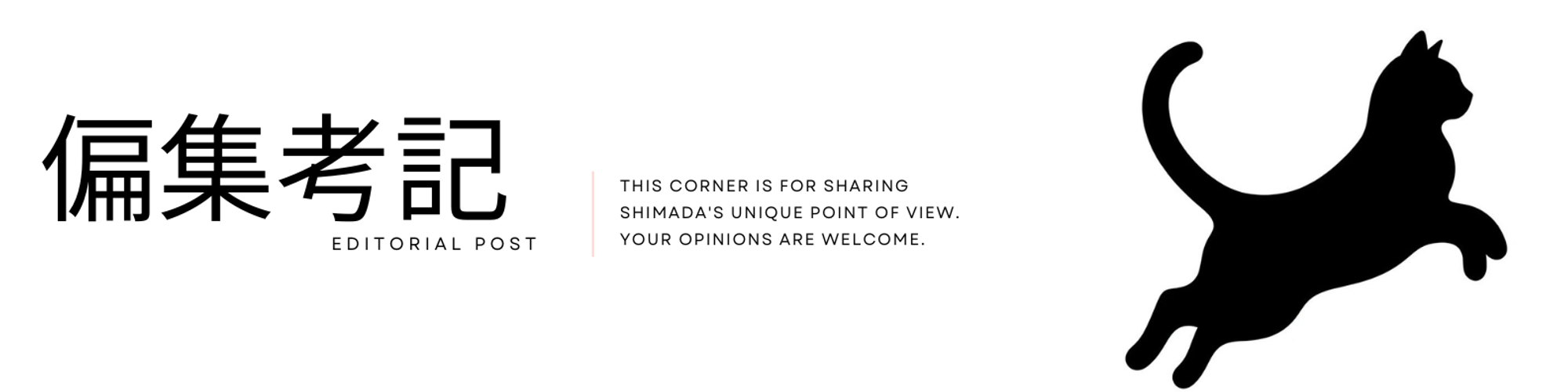 【偏集考記】やり方とあり方と
【偏集考記】やり方とあり方と
ハンズバリュー株式会社の変革者・作家の島田慶資です。
先日、お客様の経営支援に携わらせていただく機会がありました。そのお客様は、長年にわたり素晴らしい経営手腕を発揮され、数々のヒット商品を生み出してきた尊敬すべき社長です。過去の経験と実績は目覚ましく、まさに経営のプロフェッショナルと言えるでしょう。
今回の支援では、お客様と共に数値計画の策定に取り組んでいたのですが、その過程で、計画の根幹となる「何を目指したいのか」という問いに対して、明確な答えを見出すことができませんでした。
キャンペーンの実施や新商品の開発といった具体的な「やり方」は次々と出てくるものの、「会社としてどのような未来を描きたいのか」「お客様や地域、従業員さんとどのような関係性を築いていきたいのか」といった「あり方」が見えてこないのです。
そのため、社長から提案される個々のアイデアや計画には、一貫性が感じられず、それを本当にやり遂げようとする強い覚悟も伝わってきませんでした。
もしかすると、金融機関はそのような社長の姿勢を敏感に察知しているのかもしれません。 表面的なやり方ばかりに目を向け、会社の根幹となる「あり方」を深く追求できていないのではないかと感じました。
「自社としてどうありたいのか」を探求することは、具体的な経営数字に直接反映されるものではありません。
しかし、この根幹がなければ、社長自身の覚悟は定まらず、そこから生まれる事業の一貫性や熱意も曖昧なものになってしまいます。本来であれば、まず「あり方」を明確にし、その上で「やり方」を検討していくべきなのでしょう。
この社長は、間もなく後継者の方にバトンタッチされる予定です。
その時、後継者の方には、親から引き継いだ大切な会社を「これからどうしていきたいのか」、自社が地域社会やお客様にとってどのような存在でありたいのか、そして「自分自身はどうありたいのか」を深く見つめていただきたいと願っています。
先代から受け継いだ資産、お客様との信頼関係、その他全ての繋がりへの感謝を胸に、夢のある未来を自らの手で切り拓いていってほしい。そう願いながら、今回の経営支援を終えました。
それでは、またお会いしましょう。 今日も一日、良い学びを。


