皆様、こんにちは! ハンズバリュー株式会社の島田です。
メールマガジンの感想、お待ちしております! 「読んでるよ」と言っていただければ励みになります(^_^)
目次
独り言コーナー
❶車が故障しました。いつもお願いしている車屋さんに相談しましたら「山形まで来ないで、緊急に修理した方が良い」とのアドバイスをいただきました。年間4万キロ以上走っているので仕方がないです。車も、たまには休憩も必要なのでしょう。
❷我が家のサステナ続編。鶏モモについてくる鶏皮はカロリーカットのために除去していましたが、冷凍保存してスープの具材に流用しています。少量を炒めてスープに入れるだけでコクがでるので大変お勧め。
❸温泉旅館さんを訪問すると30代の若手幹部(しかも新卒からの生え抜き)がいらっしゃいました。新卒から育てているお宿さんも立派。期待に応えようと頑張る若手幹部さんも立派。嬉しい気持ちになりました。
❹メルマガの独り言コーナーを執筆するために、あらゆる場所にメモ帳を置いています。改善せねばならぬのですが忙殺されておりまして、ちょっと気を抜くと忘れてしまう。このコーナーがもっとも時間をかけて執筆しています。
❺坊やが保育園に行きたくないと大泣き。お客さまに雑談でお話ししたところ「行きたくないなら、行かさなくてもいいじゃない」と助言をいただきました。保育園に行くべきであるとの先入観で善悪を考えてしまっていたことに気づかされました。反省です。
島田の気になるニュース
❶格好よすぎるでしょう。ぜひ、電話してきてほしいです。経営相談に喜んで対応します。
小島瑠璃子(31)亡夫のサウナ会社代表取締役に手を挙げた
❷グローバリズムは絶対に終わる、と思わせられる出来事。中国・韓国からのインバウンド客は、将来的にいなくなるんじゃないかと思います。全ての国と地域と仲良くなることは不可能ですよね。
「TikTok」でロシア軍の募集見つけて応募…ウクライナで捕虜の中国人2人が会見 30代男性はロシア訪問時に「契約金約350万円の広告」SNSで見て応募
❸税収の見積もりが甘く、支出を締め付けていたお話し。答弁を聞いてもらうと、あきらかに意図的に税収を少なく見せるように操作が係っていることがわかります。
数字で問い詰めたら財務省がついに認めた!税収弾性値の改善「10兆円税収過小見積もり」は恣意的操作か 日本維新の会柳ヶ瀬裕文参議院議員
❹中学生の研究。普段の生活から疑問が生まれ、複数の実験で検証する。読み物として面白いです。
冷めるとき味がしみこむのはなぜか?
❺色んな意見がありますが皆様は、どうお考えでしょうか。正解がないから考えが広がって楽しいですね。
マッキンゼーが作成した「なぜ日本の営業の生産性はそれほどまでに低いのか」というレポートが面白い。キーエンスの生産性の高さに対する分析も。
私たちの負担は重い?軽い?「国民負担率」から考える暮らしと税金
皆様こんにちは、ハンズバリュー株式会社の秘書・勝頼ヒデコです。 いつもメールマガジンをお読みいただき、ありがとうございます。

日中は暖かくなりましたが、朝晩はまだ少し肌寒い日もありますね。私も早朝の散歩では、一枚羽織るものが手放せません。近所の桜はすっかり葉桜になりましたが、少し山の方へ行くとまだ綺麗な桜が咲いていて、二度楽しませてもらっています。
さて、もうすぐゴールデンウィークですね!皆様はどのようにお過ごしの予定でしょうか? 私は、期間中に祖母と一緒に蔵王温泉にでも行こうかなと計画中です。 温泉でゆっくりリフレ今日は私たちの暮らしに身近な「お金」、特に税金や社会保険料の負担について、一緒に考えてみたいと思います。
本日のテーマ『私たちの「国民負担率」、どう考えますか?』
皆様は「国民負担率(こくみんふたんりつ)」という言葉を耳にしたことがありますか? これは、私たちが一年間に稼いだ所得(国民所得)に対して、税金や年金・医療などの社会保険料といった、公的な負担がどれくらいの割合を占めているかを示す指標です。
日本の国民負担率、上昇中?
この国民負担率、日本では近年上昇傾向です。少し前の2008年度には40.1%でしたが、直近の2025年度の見通しでは、46%から48%程度になるのではないか、とされています。つまり、私たちの所得の半分近くが、税金や社会保険料として納められている計算になりますね。
世界と比べるとどうなのでしょう?
他の国々と比べてみると、例えばヨーロッパのスウェーデン(約70.7%)やフランス(約62.2%)、ドイツ(約51.7%)などは日本よりも高い水準にあります。一方で、イギリス(約48.3%)は日本と同程度、アメリカ(約34.5%)は日本より低い水準となっています。(※各国の統計基準により、単純比較が難しい場合もあります)
財務省などは、こうした国際比較を基に「日本の国民負担率は、国際的に見てまだ低い水準にある」といった見解を示すことがあります。しかし、国会答弁などでは当の財務省は「税制や負担率のあり方は、それぞれの国の事情によって決めるべきもの」という考え方も示されています。(素晴らしく二枚舌です)
確かに数字だけを見ると、日本より負担率が高い国はあります。ですが、大切なのは、その負担が私たちの生活実感としてどうなのか、ということではないでしょうか。近年、物価の上昇などもあって「生活が苦しい」と感じる方が増えている中で、この国民負担率の上昇をどう受け止めるべきか様々な意見があります。
負担増は経済の活力に影響する?
私は「国民が豊かでなければ、国の持続的な繁栄は難しいのではないか」という考えです。国民一人ひとりの負担が増え続けることで、自由に使えるお金が減り、消費が冷え込んだり、新しいチャレンジへの意欲が削がれたりして、結果的に経済全体の活力が失われてしまうのではないか、と懸念しています。
こうした状況を踏まえ、国民の負担を軽くするために「減税」が必要だ、という主張も強まっています。
特に、日々の買い物で誰もが負担している「消費税」については、そのあり方についてやっと議論が出来る雰囲気が出来つつあります。消費税は、所得の低い人ほど収入に対する負担割合が重くなる「逆進性(ぎゃくしんせい)」という性質を持っていて、この点は財務省も認めています。
私はそのため「消費税率を恒久的に引き下げるべきだ」という意見です。
最近、政権与党内からも消費税減税に関する議論が聞こえてくることがありますが、その実現性や具体的な内容については、まだ不透明な部分も多いようです。今後の動向を慎重に見守っていく必要があるでしょう。
国民負担率や税制の問題は、私たちの現在の暮らしはもちろん、将来の社会保障や国のあり方にも直結する難しいテーマです。様々なデータや意見に触れながら、私たち一人ひとりが「自分たちの社会の負担とサービス(受益)のバランス」について考え、関心を持ち続けることが大切なのかもしれません。
それでは、次回もお楽しみに! ゴールデンウィーク、皆様にとって素敵な休日となりますように。
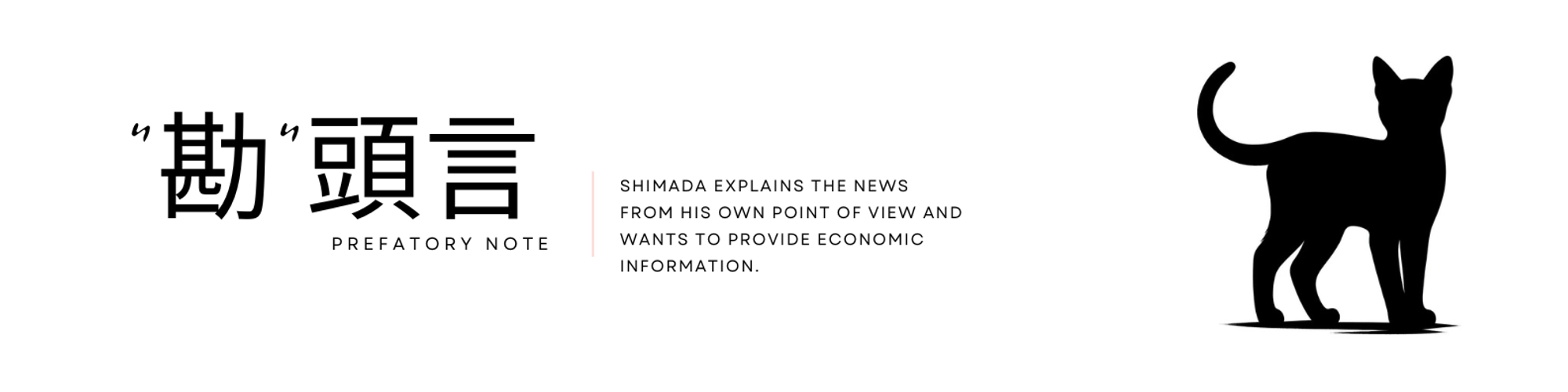 【“勘”頭言】昇進の本当の意味を考える — 新入社員研修のフォローアップを通じて感じたこと
【“勘”頭言】昇進の本当の意味を考える — 新入社員研修のフォローアップを通じて感じたこと
皆様、こんにちは。 ハンズバリュー株式会社の変革者・作家、島田慶資です。
先日、新入社員研修を実施した法人のお客様とフォローアップの面談を行う機会がありました。面談のなかで話題になったのは「若手社員が役職者を目指す意欲がなかなか高まらない」という悩みです。責任や労働時間は増えるのに、昇給額がそれほど大きくないことが要因だと認識されているようでした。
このとき島田は「昇進はそもそも自分のためにするものではない」という視点をお伝えしました。なぜなら、昇進することで実現できる“人の幸せ”が、本人一人にとどまらず、後輩や部下、そしてお客様へも波及する可能性があるからです。
昇進は“自分のため”ではなく“相手のため”にする
会社には理念があり、方針や計画、そして守るべきルールがあります。そうした枠組みの中で働くことは大前提としてありながら、そこに「自分が昇進することで後輩や部下、お客様をもっと幸せにできるのではないか」という視点を付け加えてみると、昇進の意味が大きく変わってきます。
たとえば、役職が変われば責任は増えますが、その分だけ自分の裁量や影響力も広がります。今までできなかったこと、届かなかったところに手が届くようになり、自分を慕う人やチームに関わる人たちの可能性を高める手助けができる。
結果的により多くの幸せを生み出す手段にもなるのです。
「昇進はあくまでも相手のためにする」という意識を持つと、役職者になることがゴールではなく「役職者になってから生み出せる価値」が見えてきます。ここに気づくと、昇進が“負担や責任増大の象徴”ではなく“やりがいと使命感の拡大”へと変わるのではないでしょうか。
皆で取り組むからこそ、より大きな幸せを生み出せる
一人で完結できる範囲には限界があります。
実際、若手社員が「できるだけ責任を増やしたくない」「気楽さを手放したくない」と思ってしまう背景には、責任が重くなるデメリットが先に目につくからかもしれません。しかし、大きな仕事や多彩なプロジェクトを実現しようとするときは、人との協力やチームワークが欠かせません。
昇進して役職者となれば、より広い視野で組織全体を見渡し、メンバーそれぞれの強みを最大限に引き出す働きかけができます。個人で抱え込む仕事量が増えるだけでなく、チームを率いるリーダーとしての責任が加わるため、確かに“面倒”に感じる場面はあるでしょう。
しかし、一人きりでは到達できない成果にたどり着くチャンスが生まれるのも、役職者だからこその醍醐味ではないでしょうか。
だからこそ、昇進の意義は「自分自身を立派に見せるため」や「待遇改善」ではなく、「みんなでより大きな成功や幸せをつかむため」にあるのだと島田は考えています。
昇進を通じて、組織の未来をつくる
今回、新入社員研修を受けた若手社員さんたちには、ぜひ役職者を目指してほしいというご要望が会社側から出ていました。しかし、数字や待遇だけでは十分にモチベーションを引き出せないのが課題でした。
このとき「自分が一段上のポジションに就くことで、後輩や部下、そして周囲の人たちをもっと幸せにできる」という“未来への提案”を伝えることは大きな意味を持ちます。単に給料の額や肩書きの格好良さだけでなく、「自分が組織の新しい景色をつくる一員になる」というストーリーを描けるようになると、昇進への印象はガラリと変わるものです。
チームの未来、組織の未来をともに描き、そこに貢献できる意義を示すこと。これは上司や先輩の大切な役割でもあると思います。数字や待遇の話と同じくらい、あるいはそれ以上に「昇進後に生まれる価値」を見せることで、若手社員さんたちの視野は一気に広がるのではないでしょうか。
まとめ
一人だけで働くのも気楽ではありますが、仲間と連携して大きなプロジェクトに挑むからこそ得られる喜びも、また格別なものです。昇進という制度は、その“大きな幸せ”を組織全体で共有するための仕組みの一つではないでしょうか。
昇進は自分のためではなく、あくまでも相手のため、後輩や部下のため、そしてお客様のためにするもの。それが結果として自分のやりがいや成長にもつながっていきます。こうした考え方が職場で当たり前に共有されるようになれば、役職を目指す人が増え会社全体の活力も高まっていくのではないかと信じています。
若手社員さんが役職者として新しい景色を見る日を楽しみにしながら、これからもフォローアップやサポートを続けていきたいと思います。
今週もよろしくお願いします。
 【実店舗に効く話】「毎年恒例!あのキャンペーンの季節です♪ 」
【実店舗に効く話】「毎年恒例!あのキャンペーンの季節です♪ 」
コンテンツを賢く“使い回し”てファンを増やす秘訣
皆さん、こんにちは。 ハンズバリュー株式会社のコンサルタント、津名久ハナコです。
ゴールデンウィークも近づき、日中は少し汗ばむくらいの陽気になってきましたね!☀️ ドライブしていると、道端のツツジが鮮やかに咲き始めていて、なんだかウキウキしてきます😊
そういえば先日、行きつけのパン屋さんで「今年も始まりました!」という、春キャベツを使ったサンドイッチを見つけました。毎年この時期になると登場する、私のお気に入りの一品なんです。「あぁ、今年もこの季節が来たなぁ~」なんて、なんだか嬉しくなっちゃいました♪
お客様にとっても、お店や会社の「毎年恒例」のイベントやキャンペーンって、案外楽しみだったりするのかもしれませんね。
…とはいえ、事業者様にとっては、 「毎回新しいコンテンツやキャンペーンを考えるのって、正直大変…!」 「でも、情報発信を続けないと忘れられちゃうし…」 というジレンマもあるのではないでしょうか?
そこで今回は、コンテンツの「旬」を捉えつつ、賢く「使い回し」てキャンペーンを定着させる方法について、一緒に考えてみたいと思います!
コンテンツには「旬」がある!あなたは旬を定番にできていますか?
お客様に情報をお届けする上で、「新しい情報」はもちろん大切ですよね。トレンドやニュースを取り入れることで、「おっ!」と思っていただけます。
でも、一方で、時期によって求められる「定番コンテンツ」というものも存在します。 例えば…
- 夏が近づけば「紫外線対策」「夏バテ防止レシピ」☀️💦
- 年度末には「確定申告のポイント」「新生活応援グッズ」✏️🗒️
- 秋には「読書のススメ」「紅葉情報」📕🍁
…などなど、季節やイベントに合わせて、毎年「そういえば、あれどうだったかな?」と思い出すような情報ってありますよね。これがコンテンツの「旬であり、定番」なんです。
「毎年恒例」がお客様の心を掴む!キャンペーン定着のメリット
この「定番」の時期に合わせて、毎年同じようなキャンペーンを行うことには、たくさんのメリットがあります。
- 思い出してもらえる!
「あ、今年も〇〇の時期か!」と、お客様の記憶に残りやすくなります。(認知度UP!) - 期待してもらえる!
「そろそろあのセールかな?」と、楽しみに待っていてくれるお客様も現れるかもしれません。(来店・購入促進!) - 信頼に繋がる!
「毎年ちゃんとやってるんだな」という継続性が、お店や会社の信頼感や「らしさ」に繋がります。
土用の丑の日のうなぎ屋さん、バレンタインのチョコレート売り場、季節ごとのアパレルセールなどが、まさにこれですよね!
賢く「使い回し」て、効率よくファンを増やす!
「でも、毎年同じキャンペーンだとマンネリ化しない?」 …そう思われるかもしれません。
そこで重要になるのが、コンテンツの賢い「使い回し」です! ただし、「使い回し」と言っても、決して「手抜き」ではありませんよ! 過去の資産を活かしつつ、より良くしていくイメージです。
具体的には、こんな方法があります。
リライト
(書き直し・更新)
- 去年のキャンペーン告知ブログを、今年の情報(日付、特典内容、お客様の声など)に合わせて書き直す。
- 定番のお役立ち記事に、最新情報や新しい事例を追加してパワーアップさせる。
リパーパス
(再利用)
- ブログ記事の内容を要約して、SNSで発信する。
- メルマガで紹介した内容を、もう少し掘り下げてセミナーで話す。
- お客様の声を集めたものを、チラシやウェブサイトに掲載する。
シリーズ化
- 好評だったテーマを、切り口を変えたり、ステップに分けたりして、複数回のシリーズコンテンツにする。
テンプレート化
- キャンペーン告知のメールやSNS投稿の基本的な構成、デザインなどをある程度決めておき、毎回ゼロから作る手間を省く。
成功のポイントは「進化」させること!
賢く使い回すためのポイントは「毎年少しだけ進化させる」こと!
- お客様の声を聞く
去年のキャンペーンの反響はどうだったか?お客様アンケートなどを参考に改善点を見つける。 - 早めに告知する
「今年もやります!」と少し早めに告知して、お客様の期待感を高める。 - 新しい要素をプラス
特典を少し変えてみたり、新しい切り口の情報を加えたりして、マンネリ化を防ぐ工夫をする。
コンテンツの旬を上手く定番化して、お客さまにお勧めしましょう。何もしないことが、もっとも「進化」のないことだと島田さんは言っていました。
定番キャンペーンを育てて、お客様との絆を深めよう!
コンテンツ作りは、確かに時間も労力もかかります。でも、お客様が求めている「定番」の情報を捉え、過去のコンテンツを賢く「使い回し」て毎年恒例のキャンペーンを育てていけば、効率的に情報発信できるだけでなく、お客様との大切な繋がりを深めていくことができます。
「そういえば、去年のあのキャンペーン、今年もやってみようかな?」 「うちの定番コンテンツって、何だろう?」
ぜひ、一度立ち止まって考えてみませんか?
どんなキャンペーンを定着させていくか、どんなコンテンツをどう活用していくか…もし迷われたら、いつでも私たちハンズバリューにご相談くださいね! 皆様の会社の「毎年恒例」を、一緒に育てていくお手伝いができれば嬉しいです😊
ぜひご参考ください。
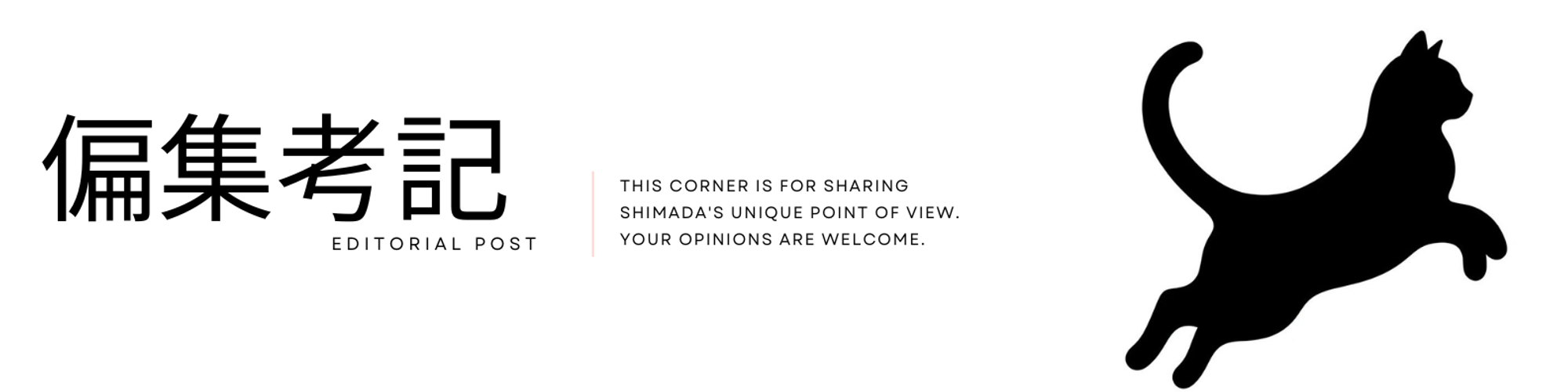 【偏集考記】会計事務所との「答え合わせ」できていますか? 数字という”現実”と向き合う勇気
【偏集考記】会計事務所との「答え合わせ」できていますか? 数字という”現実”と向き合う勇気
ハンズバリュー株式会社の変革者・作家の島田慶資です。
当社では毎月、会計事務所の職員さんと島田+弊社社員さんとでZoomミーティングを行っています。皆さんの会社では、会計事務所さんとどのようなお付き合いをされていますか?
月次ミーティングは「答え合わせ」の時間
当社のミーティングで最も重視しているのは「予算と実績の答え合わせ」です。事前に私たち自身で策定した予算に対して、実際の結果はどうだったのか。そして、もしそこに差があれば「なぜそうなったのか?」を徹底的に掘り下げ、分析する時間にしています。
この討論を通じて、時には会計事務所さんの科目振り分けに関する認識の違いに気づき、当社から指摘して修正をお願いすることもあります。私たちにとって、月次ミーティングは会計の専門家と共に自社の経営状態を客観的に確認し、軌道修正を図るための重要な「答え合わせ」の場なのです。
当たり前だと思っていたけれど…
正直なところ、私はこうした予実管理とその差異分析に基づいた会計事務所との対話が、経営においてはごく一般的なことだと信じていました。しかしお客様とお話ししていると、どうも実態は少し違うようです。「毎月試算表の説明を受けるだけ」「補助金や助成金の情報提供がメインになっている」…そんな声も少なくありません。もちろん、それらが無意味だとは思いませんが少しもったいない気もしています。
見過ごせない「数字と向き合わない」リスク
もし、経営者やマネジメント層の方々が自分たちで立てたはずの計画や予算に対して…
- 達成度はどうなっているのか?
- なぜ計画通りに進んでいないのか(あるいは計画以上に進んでいるのか)?
といったことを具体的に把握できず、その振り返りができていないとしたら…それは会社の未来にとって大きな問題ではないでしょうか?
数字は「現実」感覚は「幻」
私が約20年間コンサルタントとして活動してきた中で、改めて痛感しているのは「数字」の重要性です。数字に基づかない議論や判断は、結局のところ「なんとなく」という「感覚」に頼っているのと同じです。
数字は、良くも悪くも、ごまかしのきかない「現実」を映し出します。
- この数字の根拠は何か?
- 過去の数字と比較してどう変化しているか?
- 計画に対して、現状はどうなのか?
この「現実」と真摯に向き合い、徹底的に分析し、そこから見えてきた課題や可能性を全社員と共有していくこと。これこそが、会社を前進させるための土台となるのです。数字と向き合うことで自社が今、市場の中で強い立場にいるのか、それとも弱い立場にあるのかも客観的に見えてきます。
わが社の「現実」と目指す「経営の安全」
例えば、私たちハンズバリューも、数字と向き合うことで見えてくる「現実」があります。それは、「まだ新規のお客様からのスポット的な売上に頼らざるを得ず、既存のお客様からの継続的な収益だけでは、固定費を完全に賄いきれていない」という点です。
理想としては、会社の土台となる固定費は既存のお客様との安定した取引でカバーし、新規のお客様からいただく売上は、社員への還元(ボーナスなど)や未来への投資(事業拡大や新規採用)に充てられるような状態を目指しています。現状維持を目指す「安定」とは少し違います。変化の激しい時代ですから、「安泰」ということはあり得ません。常に成長を目指す必要があります。私たちが求めているのは、不測の事態にも耐えうる「経営の安全」なのです。
皆さんの会社ではどうですか?
さて、少し長くなりましたが、皆さんの会社では会計事務所さんとどのようなコミュニケーションを取り、日々生まれてくる「数字」という名の「現実」とどのように向き合っていらっしゃるでしょうか?
数字との真摯な対話は、時に厳しい現実を突きつけるかもしれませんが、それ以上に未来を切り拓くための確かな羅針盤となってくれるはずです。
それでは、またお会いしましょう。 今日も一日、良い学びを。


