皆様、こんにちは! ハンズバリュー株式会社の島田です。
※社内で回覧していただいているお客さまがいらっしゃいました。ありがとうございます!!著作を明記していただけるのであれば、自由に配布ください。
メールマガジンの感想、お待ちしております! 「読んでるよ」と言っていただければ励みになります(^_^)
目次
独り言コーナー
❶雨が降って稲穂が実っています。一方で、畑のネギは真っ白になってしまっています。今回の水不足は農作物に影響があるでしょう。食料品単体ではインフレとはならないでしょうが、お金があってもものがないという供給ショック型インフレもちらつきます。
❷続・中小企業成長加速化補助金の支援について。事務局から面接についての注意喚起のメールが届きました。フリップや補足資料はもちろん、プロジェクターの持ち込みなど禁止項目が追加されていました。質問があったのでしょうね。経営者の負担を減らすために理論武装させたい支援者がいたと思います。僕も一瞬だけ考えましたが、実力勝負で望んでいます。
❸山形県中小企業家同友会の経営指針を作る会にて、経営方針と計画の策定について報告する機会をいただきました。何度も経験していますが、報告することが一番勉強になります。準備の時間とストレスは相当かかりますが、自身の成長に繋がっています。このような機会をいただける場は貴重です。感謝しています。(詳細は編集後記で執筆しています)
❹福島同友会の合同会社のりぷろ・佐藤愼子代表とYouTubeを撮影しました。30本から40本投稿しないとYouTubeのアルゴリズムに評価いただけないとのことですから気長に投稿します。チャンネル名は「島田慶資のよい経営者になろう」です。同友会の第二の目的からいただきました。
❺家族と一緒に山形県の遊園地「リナワールド」を訪れました。坊やの身長でも遊べる遊具はあるものの「怖い」といってほぼ乗らずに終わりました。まだ遊園地は早かったのかもしれません😂
島田の気になるニュース
❶給与から所得税+住民税+社会保険料を抜かれて手取り。その手取りから10%の消費税を払わされると思うと、減税しろと言いたくなるでしょう。 そもそも子育てに必要なオムツやミルク等に10%の税率をかけておいて少子化は当然の結果。まともなリーダーが登場することを望んでいます。
なぜ若者は消費減税を好む? 元国税局職員の吉本芸人の答えと提案
❷公共事業みたいなものだから大いに歓迎です。日本国民にとって優秀な人材のためにより増額しても良いと思います。 ただ、財源論が全くないことに違和感。減税のみ財源論を出してくる政府は邪悪と言わざるを得ないでしょう。
給与上げ、人件費1兆円増 財務、総務省
❸経済成長したら税収増えることは確認済み。国の一般会計税収は75.2兆円程度に達し、5年連続で過去最高を更新しています。経済成長させるつもりがないのでしょうか?なお、来年度は税収の上振れがないように国債償還を6兆円上積みしています。
政府 ガソリン暫定税率廃止の試算 年度内6000億円程度財源不足
❹継続するためのコツは、ハードルを下げること。資格試験の勉強していたときも、やる気が起きない時は「5分だけ勉強する」とハードルを下げて継続しました。
「習慣化は意志の強さ」という大ウソ、脳科学でわかった「続ける人」の共通点
❺この報道、あなたは知っていましたか?なぜ日本国民に謝罪しないのかが疑問です。特に、農家やJA、卸売りさんに真摯に謝って欲しいです。
「コメ足りている」→「誤った前提」 農水次官、自民党農林族に謝罪
また、過去の記事になりますが、そもそも生産が足りていないことを指摘している記事になります。
残念ながら来年秋まで「5㎏4200円」が続きます…農水省とJA農協がいる限り「コメの値段は下がらない」そのワケ
【今週の経済入門】最低賃金アップ、本当に中小企業は耐えられるのか?
皆様こんにちは、ハンズバリュー株式会社の秘書・勝頼ヒデコです。 いつもメールマガジンをお読みいただき、ありがとうございます。

さて、先日、来年度の最低賃金が全国平均で6%以上引き上げられるというニュースが話題となっています。 後輩のハナコも「お給料が上がるのは嬉しいニュースですけど、なんだか手放しでは喜べないような…そんな複雑な気持ちになりますね」と話していました。
確かに、賃金が上がることは、物価高に悩む庶民にとって基本的には歓迎すべきことです。 その一方でこの大幅な引き上げが、私たちの暮らしや日本経済全体にどのような影響を与えるのか立ち止まって考えてみる必要がありそうです。
本日は、この「最低賃金の引き上げ」というテーマについて、その背景や様々な懸念点を皆様と一緒に勉強していきたいと思います。
本日のテーマ『最低賃金アップの光と影~私たちの手取りは本当に増えるのか?~』
今回の最低賃金の引き上げ幅は、過去にさかのぼってもかなり高い水準です。
政府は「2020年代に全国平均1500円」という目標を掲げており達成するためには、今後も過去に例のないペースでの引き上げが必要になります。
懸念点1:社会保険料や税金の壁~手取りは思ったより増えない?~
まず、ハナコが感じた「複雑な気持ち」の理由の一つが社会保険料や税金の問題です。 最低賃金が上がり、額面のお給料が増えても伴って所得税や住民税、社会保険料の負担も増えます。
特に重たい社会保険料の減免といった対策が同時に行われなければ、せっかく賃金が上がっても実際に手元に残る「手取り額」の増加は、ほんのわずかになってしまいます。
「物価の上昇に追いつくための賃上げのはずなのに、これでは実感が湧きにくいですよね…」とハナコも心配そうです。
懸念点2:中小企業の負担増と雇用の未来
次に、より深刻な問題として懸念されているのが中小企業や小規模事業者への影響です。 原材料費や光熱費が高騰する中で、さらに人件費と社会保険料(事業主負担分)の負担が増えることは、多くの企業にとって大きな経営課題となります。上昇したコストを商品やサービスの価格に適切に転嫁(価格転嫁)できれば良いのですが、それが難しい企業が圧倒的多数でしょう。
そうなると企業は厳しい選択を迫られます。
雇用の抑制 ⇒新規採用を控えたり、現在働いている方の労働時間を短縮したり、最悪の場合、雇い止め(解雇)に踏み切らざるを得ないケースも出てくるかもしれません。
倒産のリスク ⇒コスト増に耐えきれず、事業の継続を断念する企業が増加する可能性も。
このまま急激な最低賃金の引き上げが続けば今後数年で失業者が増加し、特にパートタイマーとして働く女性や地方の雇用環境が深刻な打撃を受けるのではないか、と悲観的な予測をしています。
なお、お隣の韓国では最低賃金の大幅な引き上げをしたときに失業率が数%引き上がったという事実もあります。なぜ、政府は学ばないのか疑問でなりません。。。
懸念点3:物価上昇に賃金が追いつかない?
そしてもう一つ。賃金の上昇率と物価の上昇率の競争です。 第一生命経済研究所レポートによると、日本では食料品価格の上昇が全体の物価上昇を牽引する「食料偏重型インフレ」が続いています。今回の賃上げ率をもってしても、日々の生活に欠かせない食料品などの値上がりペースに追いついていない、という研究結果です。
もし「賃金は増えたけれど、それ以上に物価が上がってしまい実質的に買えるものが減ってしまった」となれば、消費はかえって冷え込み経済全体が停滞してしまう悪循環に陥る危険性もはらんでいます。
求められる総合的な対策
このように見てくると、最低賃金の引き上げは単に「賃金を上げる」という一点だけで解決する問題ではないことが分かります。
例えば…
- 消費税の減税など、国民の可処分所得を直接増やす施策
- 住民税、所得税、社会保険料の負担を軽減する措置
- 中小企業が賃上げの原資を確保できるよう事業者負担の社会保険料を助成する施策
…など、賃上げとセットでこうした対策を進めていくことが本当の意味で国民の生活を豊かにし、経済を好循環させていく鍵となるのではないでしょうか。 ただ、自民・公明・維新が国民民主の基礎控除引き上げ(減税)を潰しましたから、私は別勢力に減税を期待しています。
私たち経営者や働く者一人ひとりが経済政策に関心を持ち、その影響を見極めていくことがより重要になっていることは決定的です。既存勢力を惰性で応援していては、苦しい現実は変えようがありません。しっかりと自身で考えることが大事になっていると強く思います。
それでは、次回もお楽しみに! 今週もどうぞよろしくお願いいたします。
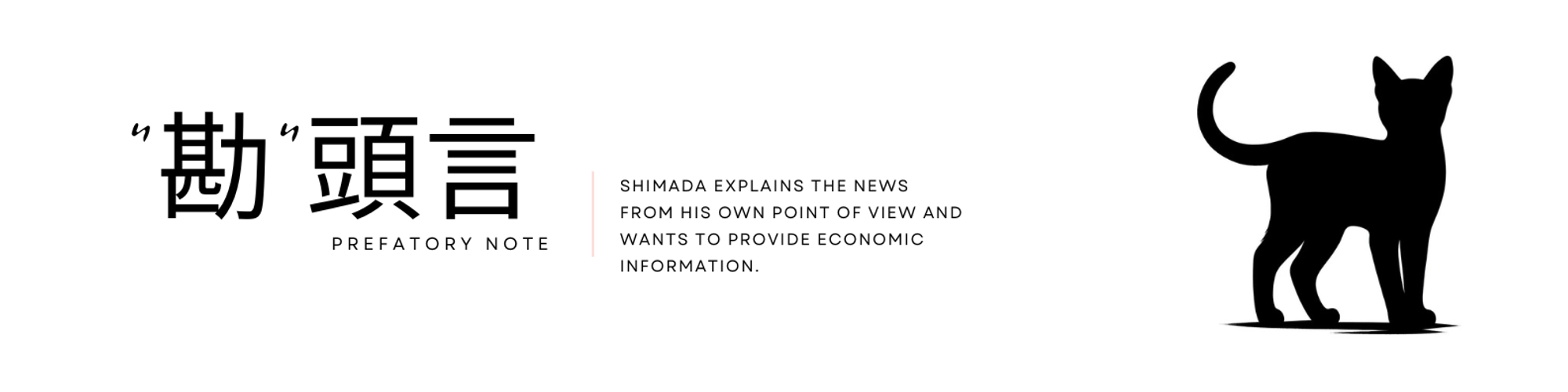 【“勘”頭言】会社のゴールはP/Lにはない?
【“勘”頭言】会社のゴールはP/Lにはない?
貸借対照表に眠る「本当の体力」の見つけ方
皆様、こんにちは。 ハンズバリュー株式会社の変革者・作家、島田慶資です。
さて、夏休みの研究課題として島田と一緒に「貸借対照表」を勉強してみませんか。
なぜ、黒字なのに会社は倒産するのか?
皆様が大好きな「損益計算書」。もちろん黒字経営は会社存続の大前提です。しかし、黒字であれば全て良し…というわけではないことを、私たちは知っていますよね。「黒字倒産」という言葉があるように、業績が良くても会社の経営が危うくなることは珍しくありません。
また、損益計算書上の赤字が、必ずしも悪いことだとは限りません。
例えば、事業承継をスムーズに進めるため役員退職金を支払って意図的に赤字にする戦略もあります。災害や、コロナ禍のような特殊な状況下で、赤字が避けられない年もあるでしょう。
つまり、損益計算書はあくまで「一期間の成績表」に過ぎず、会社の本当の強さや存続可能性を示すものではないのです。
本当の体力は、貸借対照表にこそ表れます。しかし、この最も重要な貸借対照表を「どうすれば強くできるのか」を具体的に教えてくれる会計事務所には、私はまだ出会ったことがありません。
会社のゴールを「オーナー残存資金」に設定するという提案
そこで島田からのご提案です。
会社の成長を示すゴールとして「オーナー残存資金」という指標を追いかけてみるのはどうでしょうか。資金会計理論で提唱されている指標で、会社の「本当の体力」を可視化するものだと考えています。
少し計算が必要ですが、自社の貸借対照表を見ながらぜひ一緒に考えてみてください。
【オーナー残存資金の計算方法】
資金会計理論では、貸借貸借表の右側は資金のプラス。左側は資金のマイナスと考えます。それを踏まえて、①から順番に見てみてください。
①損益資金(会社の本当の貯金)を出す
まず、貸借対照表の右側下にあるに自己資本の部の資本金以外を「繰越利益準備金等」として足し合わせます。 また長期負債に「退職給付引当金」などいずれ支払うが現金として会社に残っているものがあれば追加で足します。
こちらが会社が創業以来、利益として蓄積してきた「損益資金※」です。※厳密にはもう少し計算が必要ですが、わかりやすさを優先して省きます。
②継続損益資金(事業を回すための体力)を出す
次に、先ほどの「損益資金」から、まだ回収できていないお金である「売掛金」を引き、まだ支払っていないお金である「買掛金」を足します。 これで、日々の運転資金を差し引いた「継続損益資金」が分かります。
③実質損益資金(在庫を差し引いた体力)を出す
さらに「継続損益資金」から「商品」や「仕掛品」などの在庫の金額を引きます。 これで、現金化しにくい在庫の影響を除いた「実質損益資金」が見えてきます。
④オーナー持分資金(経営者本来の資金力)を出す
この「実質損益資金」に会社の元手である「資本金」を足します。 借入に頼らない、経営者自身が持つ本来の資金力、つまり「オーナー持分資金」です。
⑤オーナー残存資金(最終的に残る自由な資金)を出す
最後に「オーナー持分資金」から、土地や建物、機械などの「固定資産」の金額を引きます。 こうして算出されたのが会計上のゴールにしたい「オーナー残存資金」です。
この指標が教えてくれること
この「オーナー残存資金」を毎年増やしていくこと。これこそが、会社のゴールになるのではないかと島田は考えています。
この指標は、運転資金(売掛金や在庫)や設備投資(固定資産)を、会社の利益の蓄積と資本金で、どのくらい賄えているかを示しています。
もし、この数値がマイナスであれば、それは自社の実力以上に借入金に頼って事業を回している、という危険なサインかもしれません。もちろん、前向きな設備投資をすれば一時的にマイナスは大きくなりますが、そのマイナスを毎年どれだけ利益で埋め戻せているか、という視点が極めて重要になります。
どうでしょうか。
このように会社のゴールを設定してみると、日々の経営判断が非常にすっきりしてくるのではないでしょうか。
今週もよろしくお願いします。
 【実店舗に効く話】「頑張ってるのに成果が出ない…」を解決!営業活動を”宝の山”に変えるExcel管理術
【実店舗に効く話】「頑張ってるのに成果が出ない…」を解決!営業活動を”宝の山”に変えるExcel管理術
皆さん、こんにちは。 ハンズバリュー株式会社のコンサルタント、津名久ハナコです。
お盆休みも間近ですが、うだるような暑さが続いていますね!🍧
先日、少し前に先輩たちとトレッキングに行った場所に「熊が出没した」というニュースを見て以来、すっかりインドア派に拍車がかかっている今日この頃です(笑)。皆様も、夏のお出かけの際はどうぞお気をつけくださいね。
さて本日は、「うちの製品は良いものなのに、どこに営業すればいいか分からない…」「営業活動が、なんだか場当たり的になってしまって…」という、切実なご相談をいただいたお話です。
お相手は、素晴らしい技術を持つ製造業の女性経営者、ショウコ社長です。
「営業活動が“ブラックボックス”になっていませんか?」
「ハナコちゃん、うちは技術には自信があるの。でも、営業となると、誰がどこに電話して、どんな話をしたのか、さっぱり分からなくて。成果が出なくても原因が不明だし、たまに上手くいってもどうして成功したのか分からないの…」
ショウコ社長様のお悩み、痛いほど分かります。
多くの会社で、日々の営業活動が記録・共有されず、担当者の頭の中にしかない「ブラックボックス」になってしまっているんです。
今回は、ショウコ社長様と実践した営業活動を「見える化」し「財産」として蓄積する管理術をご紹介します!
営業を「宝探し」に変える!3つのステップ
ポイントは、全ての行動を記録し「数字」で追いかけること。そうすることで、今まで見えなかった宝の地図が浮かび上がってきます!
STEP1:アプローチ先を「リスト化」する
まずは、アプローチしたい会社のリストを作成します。 どんな業種で、どんな担当者宛に、どんな切り口で自社の製品をアピールできるか、仮説を立てて書き出していきましょう。これが冒険の始まりの地図になります!
STEP2:全ての行動を「進捗記録」に残す
- 「〇月〇日、A社に電話→担当者不在」「B社にメール→資料送付を依頼された」「C社に訪問→今は必要ないが、半年後なら可能性ありとの事」など全ての行動とその結果を時系列で記録します。
- ここで一番のお宝は、実は「断られた理由」です。「価格が高い」「機能が合わない」「タイミングが悪い」…その一つ一つが、次へのアプローチ方法を改善するための、めちゃくちゃ重要なヒントになるんです!
STEP3:結果を「数字」で追いかける
行動を記録したら、それを客観的な「数字」で見てみましょう!
- アプローチ数(行動量):
今月、何社にアプローチできたか? - コネクト数(手応え):
ここが重要です!ただ電話やメールをするだけでなく担当者とちゃんと話せた、返信がもらえた、という「コミュニケーションが取れた数」を数えます。 - 担当者連絡先ゲット数(未来への財産):
これが増えれば増えるほど、今後の営業活動が格段に楽になります!まさに会社の「財産」です。 - 商談化数(ゴール):
実際に商談に繋がった数。ここを目指して、上の3つの数字を改善していきます。
【ハナコ’s Point!】高価なシステムの前に社長の「覚悟」!
「なるほど、でもそんな管理、専用のシステムとかないと無理じゃない?」…いいえ、そんなことはありません!
多くの中小企業では、高価なCRM(顧客管理)システムを導入しなくても、身近なExcelで十分に管理が可能です。大切なのは、ツールの値段ではなく「管理の粒度」と「誰が責任を持つか」です。
どれくらいの細かさで行動を記録するのか?そして、出てきた数字に対して最終的に誰が責任を持つのか?…それは、社長であるショウコ社長様ご自身です。
「今月はコネクト数が少ないから、アプローチの切り口を変えてみよう」「商談化率が低いのはなぜだろう?」と、社長様が数字と向き合い、次の一手を考える覚悟を持つこと。それこそが営業を仕組み化する上で、何よりも重要なことなんです!
その結果…
この管理方法を導入したショウコ社長の会社では、営業活動が劇的に変わりました。
「今まで場当たり的だった営業に、狙いが持てるようになったわ!それに、断られても落ち込むんじゃなくて、『よーし、次のヒントゲット!』って、チームみんなが前向きになれたの!」と、嬉しいご報告をいただきました!
あなたの会社の営業活動、未来の「財産」に変えませんか?
日々の営業活動は、決して「やって終わり」の点ではありません。
一つ一つの行動を記録し、見える化することで、それは未来の成功に繋がる「線」となり、会社の貴重な「財産」へと変わっていきます。
皆様の会社の営業活動、ブラックボックスになっていませんか?
「うちの営業活動も見える化したい!」「具体的な管理シートの作り方が知りたい!」
そんな時は、ぜひ私たちハンズバリューにご相談ください!皆様の頑張りを無駄にしない、成果に繋がる営業の仕組みづくりを、全力でサポートさせていただきます!
【特別プレゼントのお知らせ】
今回ご紹介した営業管理、すぐに実践してみたいと思いませんか?このメルマガのブログにコメントいただいた方限定で、私が実際に使っているExcelの「営業管理テンプレート」を無料でプレゼントいたします!
ご希望の方は、コメント欄にメルマガの感想と「テンプレート希望」と書いてご返信くださいね😊
お待ちしております!ぜひご参考ください。
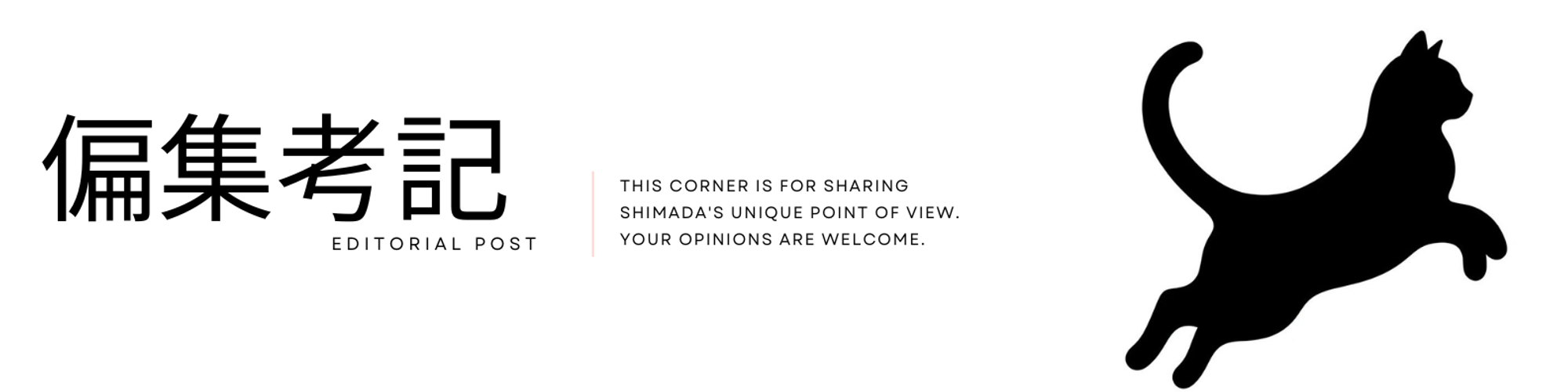 【偏集考記】「わくわくする経営方針」を描くための4つの視点。
【偏集考記】「わくわくする経営方針」を描くための4つの視点。
会社の未来は、誰と創りますか?
ハンズバリュー株式会社の変革者・作家の島田慶資です。
先日、山形県中小企業家同友会が主催する「経営指針をつくる会」で経営方針と計画の策定について改めて学ぶ機会をいただきました。本日は、その時に島田が改めて気が付いた学びを、皆様と共有させていただければと思います。
そもそも「経営方針」とは何か?
いざ「経営方針を策定する」となっても、そもそも経営方針とは一体何なのか、という根源的な問いに突き当たることはないでしょうか。
経営方針を「10年ビジョン達成のための道筋であり、その中間地点を示すもの」だと捉えています。 だからこそ、その表現方法は会社によって様々であってしかるべきです。10年後のありたい姿に向かう中で、各社が抱える経営課題や関心事は全く異なりますから「これを書かなければならない」という画一的な正解は存在しません。
羅針盤となる「質の高い経営」という視点
しかし、「視点が全く見つからない」というのもまた問題です。どこから手をつければ良いか分からない、という方もいらっしゃるでしょう。
そのような時、私たち中小企業家が目指すべき一つの方向性として、同友会が提唱する「質の高い経営」という考え方がヒントになろうかと思います。同友会が考える「質の高い経営」とは、主に以下の4つの視点から成り立っています。
- 経営理念の明確化 ⇒ 企業の存在意義や価値観を明確にし、社員と共有する。
- 社員の幸せの追求 ⇒ 社員が働きがいを感じ、成長できる環境を整える。
- 経営の透明性 ⇒ 経営状況を社員に開示し、共に考え、共に成長する。
- 地域社会との共存 ⇒ 地域社会に貢献し、地域と共に発展していく。
いかがでしょうか。この4つの視点から「5年後、自社はどのような姿になっているだろうか?」と考えてみるだけでもワクワクしてきませんか?
なぜ「みんなで」創る必要があるのか?
ここで重要なのは、経営方針、つまり10年ビジョンに至る道筋を、決して社長一人で考えてはならないということです。一人で考えた計画は、どうしても自分本位になり、客観性を失ってしまいます。
会社は一人では経営できません。 みんなの力が合わさって初めて、会社として成立します。 会社とは、単なる人の集団ではなく、共通の目的を持った集まりだからです。
この変化の激しい経営環境を生き残っていくためには、全員が納得し、同じ方向を向いて仕事をする以外に道はないと確信しています。だからこそ、全員が「せーの!」で力を合わせられる同じ方向に向かって一緒に綱引きができるような経営が、今まさに求められているのではないでしょうか。
当社では、現在進行形で自社の経営指針を刷新するプロジェクトを進めていますが、この作業の難しさ、そしてその目標の高さに、改めて身の引き締まる思いです。
皆様の会社では、未来への道筋は描けているでしょうか。
そして、その道筋を誰と共に歩んでいきたいでしょうか。この機会に、皆様の会社の経営方針や計画についても、ぜひ一度、深く検討していただければ幸いです。
それでは、またお会いしましょう。 今日も一日、良い学びを。


