皆様、こんにちは! ハンズバリュー株式会社の島田です。
※社内で回覧していただいているお客さまがいらっしゃいました。ありがとうございます!!著作を明記していただけるのであれば、自由に配布ください。
メールマガジンの感想、お待ちしております! 「読んでるよ」と言っていただければ励みになります(^_^)
目次
独り言コーナー
❶島田の所属しています山形県中小企業家同友会の40周年記念式典に参加しました。過去最高の506社の会勢で迎えることが出来ました。 過去には「入会数だけ追いかけてもしかたがないのでは」とも思っていました、会員それぞれが「学びの1ページ」。多様な参加者がいてこそ学びが深まります。僕も会勢に貢献できるように頑張ります。
❷東北中央道の除雪車の出陣式を見かけました。吾妻小富士の初冠雪も見ることが出来たので、そろそろ雪シーズンですね。タイヤ交換の予約をいれました。
❸久々にコストコのデリ商品を購入。地域のスーパーが値上がりしているので、相対的にコストコがより安く見えます。商品力や内容の充実に疑問を持ったので決算書を調べてみました。 コストコの損益計算書と貸借貸借表は秀逸なのはご存じですか?どこかで解説したいと考えています。
❹今期からの取組となりますが、島田主催で勉強会を始動します。考えてみれば商工会さん・金融機関さんからお題をいただいてセミナーで喋ることはあっても、主体的ではなかったなと反省しました。 まずは、同友会の限られたメンバーに秘密の招待状を送っております。招待状の届いた皆様、参加お待ちしております。
❺坊やの秋の遠足が河川敷から園庭に変更になりました。もちろん、クマ被害を避けてです。 先生達が園庭ながらも楽しい遠足になるようにホールで迷路を作ってくださったり、工夫を凝らしてくださっていました。本当に感謝しかありません。ありがとうございます!
島田の気になるニュース
❶前々から庶民を苦しめていた再エネ賦課金を見直すなんて感激。トップが変われば明確に変わることが証明されましたね。岸田・石破は、一体何だったんだと思います。無駄な時間を年単位で過ごしました。中国地方の方は、次回の解散総選挙はよく考えて投票してください。
再エネ賦課金の必要性「検証したい」赤沢経産相 支援対象見直し示唆
❷国債の利回りが上昇傾向にあります。金融機関の融資は国債の利回り以上になろうかと思います。いま、金融機関さんから借り入れしたら、利率いくらになるんでしょう。恐ろしや、恐ろしや。
3%超となった超長期国債利回り、「株式配当利回り<国債利回り」が意味すること
❸Facebookとインスタグラムでナチュラルにホリエモンの詐欺広告が表示されています。前々から噂されていましたが、ある種意図的だったんですね。
Metaが収益の10%を詐欺広告から得ていたと判明、詐欺広告への対応をわざと遅らせていたのではないかという指摘も
❹Web制作会社やデザイン会社にとってこの1週間は青天の霹靂となりました。Canvaが有償を無償で提供始めました。圧倒的シェアを持っていたAdobeのサブスク解約がとまらないとのこと。 もちろん、プロユースには限界があるので全てが乗り換えられることにはならないでしょうが、かなりの痛手になろうかと思います。島田もダウンロードしてみました。
6000円超えの画像編集ソフトが無料に。クリエイティブツールの根幹に変化の兆し
❺原文も確認しましたが、はじめから騙すつもりがあったのはIT導入補助金の全てと事業再構築補助金の一部が不正受給ですね。不正受給として処理されるのは、少しだけかわいそうな事例もありました。 ただ高額補助金は会計検査院の現地チェックがはいることを前提に取り組まなければならいコトを改めて認識しました。 (実務の運用も確認されるのは、ちょっと驚き。また、電通の隠れ蓑のサービスデザイン推進協議会がお叱りを受けてTOPPANに事務局を移されているのも面白ですね。)
中小企業向け補助金3.4億円超が不当 会計検査院が指摘
サービス等生産性向上IT導入支援事業の実施に当たり、実質的還元等により過大に交付された補助金について返還手続を行わせるよう適宜の処置を要求し、並びに同種同様の不正な事態の有無を調査して必要な場合には補助金の返還、IT導入支援事業者の登録取消しの手続等を速やかに行わせるとともに、各種審査等における不正防止策等が適時適切に行われるための指針等を整備し、また、事業主体がITツールを解約した場合に交付決定の取消しや残存簿価分の納付が適切に行われるための仕組みを整備するよう改善の処置を要求し、及び補助事業の効果を正確に把握できるような確認体制を整備するなどするよう意見を表示したもの
【今週の経済入門】国の借金は「お化け」だった?~国際60年償還ルールの正体~
皆様こんにちは、ハンズバリュー株式会社の秘書・勝頼ヒデコです。 いつもメールマガジンをお読みいただき、ありがとうございます。

先日、後輩のハナコが、テレビで見たという財政のニュースに、またもや頭を抱えていました。 「先輩、聞きましたか? 日本の国の借金が大変で、歳出(国の支出)の4分の1近くが『国債費』、つまり借金返済に充てられてるって…。 これじゃあ、私たちの生活を良くする政策なんて、できるわけないですよね…。将来世代へのツケが膨らむばかりで本当に不安です…」
確かに、そのように聞くと絶望的な気持ちになってしまいますよね。 しかし、もし、その歳出の多くを占める「借金返済」が、実は「返済したフリ」に過ぎない、いわば“お化け”のような存在だったとしたら、皆様はどう思われますか?
本日は、日本の財政議論の根幹にある、非常に奇妙な「カラクリ」について、専門家の分析を基に皆様と共有したいと思います。
本日のテーマ『財政破綻論の正体?「国際60年償還ルール」という“お化け”』
ハナコが心配していた「国債費」が膨れ上がる原因、それは「国際60年償還ルール」という、日本独自の“ガラパゴス”な財政ルールにあります。 「政府が発行した国債は、60年かけてゼロになるように返済していきましょう」というルールです。
「やっぱり、60年かけてでも返さないといけない、大変な借金なんですね…」とハナコは言いますが、ここにこそ専門家が指摘する「大きなカラクリ」が隠されています。
“お化け”の正体は、返済したフリをする会計操作
驚くべきことに、日本政府は財政赤字が続いているため、この「60年ルール」を守るための返済を実際には行っていません。
以下のようになります。
- まず、予算の「歳出(支出)」に、「債務償還費」(返済のためのお金)として例えば16兆円を計上します。
- しかし、財源(税収)はないので、その16兆円を賄うために「借換債(かりかえさい)」という名前で、そっくりそのまま新しい国債を16兆円発行します。(これが「歳入」になります)
- 結果として、16兆円を「返済したフリ」をすると同時に16兆円を「借りている」ため、国の借金(残高)は1円も減っていません。
「えええ!? それって、何の意味があるんですか? マッチポンプみたいじゃないですか!」 ハナコの言う通り、実態はただの「借り換え」です。
しかしかも、こんなルールを運用したり、変な予算を組んでいるの世界中で日本の財務省だけです。
なぜ、この有害な「お化け」が存在し続けるのか?
では、なぜこんな無意味な「お化け」の項目を、わざわざ国家予算に計上し続けるのでしょうか。「緊縮財政」を続けたい財務省の狙いだと指摘します。
- ① 財政が大変だと“誤解”させるため この「お化け」の債務償還費(実態はないのに)が歳出に計上されるため、予算の約4分の1が「借金返済」で埋まっているように見えます。「日本は借金返済で手一杯だから、国民を助ける(減税や給付などの)財源はない」という印象操作が可能になります。
- ② 「ワニの口」グラフを演出するため 財政破綻の象徴として使われる、歳出と税収の差が広がり続ける「ワニの口」グラフ。あれも、歳出側にこの「お化け」の債務償還費を含めることで、危機感をより大きく煽る道具として使われてきました。
- ③ 「将来のツケ」という“刷り込み”のため 「60年かけて税金で返さなければならない」という建前を維持することで、国民に「国債=将来のツケ」という誤った思い込みを刷り込み、増税や社会保険料の負担増を受け入れさせやすくする狙いがあったのではないか、というわけです。
諸外国(アメリカ)に「お化け」はいない
繰り返しになりますが、アメリカなど他の先進国の国家予算には「債務償還費」という“お化け”項目は存在しません。 国債は「永続的に借り換える」のが世界の常識であり、問題となるのは「利払い費※」だけだからです。 ※利払い費についても諸外国の事情と違い、日本は利払いを払っても結局巡り巡ってほとんどの利払い費が国庫(日本政府の手元)にもどってきます。
近年、ついに財務省も「(このルールは)文字通りの残高減少を目指すものではなかった」「節度ある姿勢を示すため」と、これが「建前(お化け)」であったことを実質的に認めています。
「ひどい…。私たち、実態のない“お化け”に怯えて、『財源がない』って言いくるめられてきたんですね…」と、ハナコもようやくカラクリを理解したようです。
この「60年償還ルール」というお化けを退治し、予算の実態を正しく国民に示すこと。 そして「将来のツケ」という嘘に惑わされず、今苦しんでいる国民生活を救うために、政府がためらわず財政出動(通貨発行)を行うこと。
それこそが、日本経済が復活する唯一の道だと、専門家の議論を聞いて強く感じました。 現行の高市早苗総理と片山さつき財務大臣は上記認識を持ってくださっています。期待しかありません。
それでは、次回もお楽しみに! 今週もどうぞよろしくお願いします。
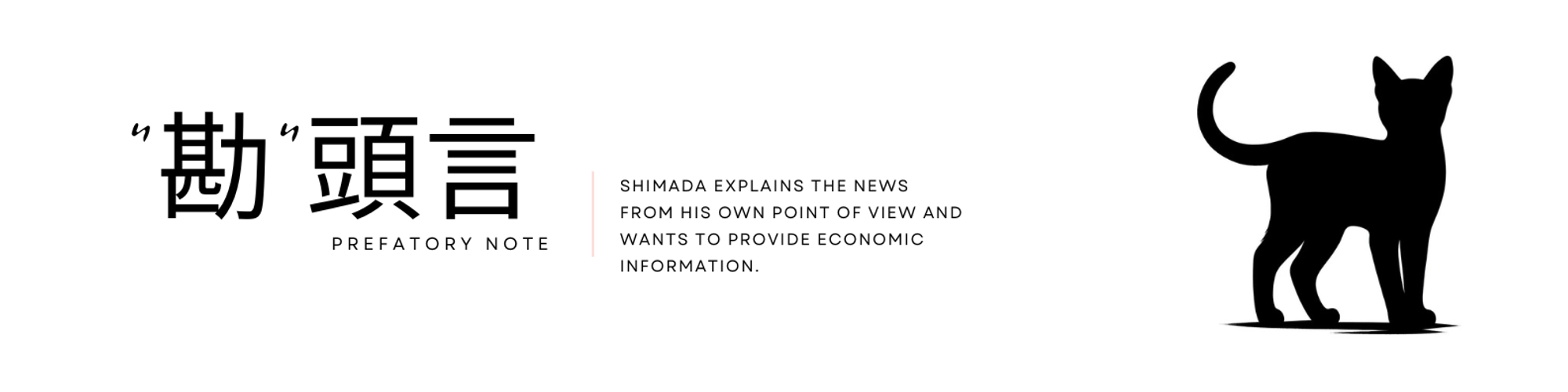 【“勘”頭言】「エコノミックガーデン」という発想?地域に“当てにされ、当てにする”関係性とは
【“勘”頭言】「エコノミックガーデン」という発想?地域に“当てにされ、当てにする”関係性とは
皆様、こんにちは。 ハンズバリュー株式会社の変革者・作家、島田慶資です。
先週、山形県中小企業家同友会の40周年記念式典が開催され、拓殖大学の山本尚史教授による「エコノミックガーデン」についての基調講演を拝聴いたしました。その後のグループ討論も含め、非常に多くの気づきがありましたので、改めて皆様と確認させていただきたいと思います。
エコノミックガーデンとは何か?
皆様は「エコノミックガーデン」という言葉をご存知でしょうか。 これは、地域を一つの「庭(ガーデン)」として捉え、その「土壌」を良くすることで、庭全体(=地域全体)が豊かになるというエコシステム(生態系)の考え方です。
これまで「エコシステム」というと、楽天ポイント圏のように自社の製品やサービスをお客様に囲い込んで使っていただく、という文脈で使われることが主でした。しかし、「エコノミックガーデン」の文脈は全く異なります。地域全体を一つの機能体として捉え、その土壌(経営環境)を皆で耕していく、という発想です。
この考え方に触れたとき、改めて「自社は、この地域(庭)にとって、どのような役割を担っているのか」を考えるきっかけとなりました。
「フロンティア」に足りなかった視点
私は以前から、今後10年の山形や福島が直面する人口減少・過疎化という現実を「フロンティア」だと申し上げてきました。 なぜなら、大手企業はSWOT分析の外部環境「機会」「脅威」を重視し、経済合理性が取れなくなれば、株主の手前もあり「撤退」という選択肢を取らざるを得ないからです。
その大企業が去った広大なフロンティアに残るのは、我々、地域に根ざした中小企業・小規模事業者しかいません。だからこそ、ここが我々の新たな活躍の場になると考えています。
しかし、現実問題として、需要の圧倒的な減少や働き手・担い手の不足という深刻な課題が横たわっています。この課題に対する明確な解決策を、私はこれまで皆様に提示できていませんでした。
解決の鍵は「当てにされ、当てにする関係性」
今回、「エコノミックガーデン」という考え方に触れ、その答えのヒントが見えた気がします。 それは、自社だけで生き残るのではなく「地域の方々や、他の中小企業に助けてもらう(頼る)」という側面と「自分たちも地域の一員として、相手から頼られる存在になる」という側面です。
要するに「当てにされ、当てにする関係性」です。 一方的な依存や奉仕ではなく、あくまで対等な立場で、相互に頼り合える関係性を築くこと。 それによって初めて、真の連携と発展が望めるのではないか、という気づきでした。
では、この真の連携は、どうすれば築けるのでしょうか?
「顔の見える関係性」という第一歩
そのヒントは、2024年の山形県中小企業家同友会・経営研究集会で、福島同友会の藤田元代表理事が教えてくださった「顔の見える関係性」というキーワードにあるでしょう。
藤田氏は、体験報告の中で「隣のお蕎麦屋さんの家族構成、何が得意で何が趣味かまで全て知っている」と発言されました。 私は、これこそが地域で「当てにし、当てにされる」関係性を築くための、重要かつ具体的な第一歩だと確信しました。
もちろん、地域にいるすべての人と、そこまで深く気持ちの良い関係性を持つことは難しいかもしれません。では、その関係性を築く相手を見極める「物差し」は一体何なのか。
それは、間違いなく「経営理念」です。
自分は何者で、何を目的に事業をしているのか。その経営理念を物差しとして、自分たちと価値観の合う方と手を携え、共に成長し、地域を守っていく。
ここで重要なのは、「理念が共感できる中小企業“だけ”と組めば良い」という排他的な話ではない、ということです。
今はまだ理念が明確でなくとも、学びへの意欲がある方々が同友会のような場で共に学び、自社の存在意義に気づき、仲間となっていただく。「自主・民主・連帯」「良い会社、良い経営者、良い経営環境をつくろう」という同友会の理念は、まさにこのエコノミックガーデンの考え方と深く結びついています。
地域にとって中小企業は不可欠な存在であり、絶対に生き残らなければなりません。この現実を前に、私たち中小企業家同友会が果たすべき役割は、ますます深まっていると感じています。
皆様は、ご自身の地域にとって、どのような中小企業でありたいでしょうか。ぜひ、考える時間を作ってみていただければと思います。
今週も皆様にとって、実り多き一週間となりますように。
 【実店舗に効く話】「その商品、尖りすぎ?」批判を恐れる社長様へ。“伝えたい幸せ”が最強の武器になる
【実店舗に効く話】「その商品、尖りすぎ?」批判を恐れる社長様へ。“伝えたい幸せ”が最強の武器になる
皆さん、こんにちは。 ハンズバリュー株式会社のコンサルタント、津名久ハナコです。
11月に入り、街も少しずつ冬支度ですね。 当社でも、毎年恒例の「クリスマス会」の準備に取り掛かっております! 当社のクリスマス会は、社員だけでなく、日頃お世話になっている制作パートナーの方々やご家族もご招待する社内唯一の公式宴会です。
日中から開催するので、お子様連れでも安心! 美味しいお料理と、ビール、ワイン、スパークリングワインなど様々なお酒が楽しめるので、スタッフ一同、今からワクワクしながら余興の準備を進めています(笑)
さて本日は、先日訪れた、ある素敵なパン屋さんでの出来事と、そこで学んだ「挑戦すること」の本当の意味について、皆様と共有させていただきたいと思います。
カランコロン、と音が鳴る、地域の宝物のようなパン屋さん
先日、先輩と一緒に、山形県の山あいにあるパン屋さん「ぐーちょきぱん」を訪問しました。 アンティーク調の古いドアを開けると「カランコロン」と優しい音が鳴り、店内には焼きたてのパン…小麦の、どうしてこんなに幸せな気持ちになるんだろう、という良い香りが満ちています。
工房から奥様のカナ様が「あ、ようこそいらっしゃい!いつも気にかけてくださってありがとうね」と、満面の笑顔で迎えてくださいました。 「いえいえ!ここのパン、本当においしくて、お土産で持っていくと社員もお客様もみんな大喜びするんです!」
そこへ、ご主人の小林社長様も出てこられて 「よくいらっしゃいました!新作のパンもあるんだけど…ちょっと、責めすぎたかなと思ってね。感想を聞かせてほしいんだ」 と、見せてくれたのは、想像の斜め上をいくパンでした。
- ブルーチーズ × 柿 × バルサミコ酢 のあんぱん
- 山菜とくるみとジビエのミンチで作ったハンバーガー
(…た、確かに、尖ってる!) 私は一瞬戸惑いましたが、社長にこうお話しさせていただきました。
批判の裏には、“叶えてあげたい幸せ”がある
「社長様、今日は少し、ビジネスの『挑戦』についてお話ししてもよろしいですか?」
皆様は、コンビニで初めて「500mlのペットボトルコーヒー」を発売したブランドを覚えていらっしゃいますか? そう、サントリーの「クラフトボス」です。
今でこそ当たり前ですが、発売当時「コーヒーを500mlも飲むわけがないだろう!」と、SNSでは批判的なコメントが溢れました。 しかし、サントリーのメッセージは違いました。 彼らが伝えたかったのは「500mlを一気に飲んでほしい」ではなく「デスクワークをしながら、ゆっくり1日をこのコーヒーと共に過ごしてほしい」という、新しい働き方に寄り添うメッセージだったのです。
私がここで学んだのは「挑戦するときには、必ず批判的な声が上がる。けれども、その挑戦の裏には、必ず“叶えてあげたい幸せ”がある」ということです。 そして、その「叶えたい幸せ(=想いや哲学)」をしっかりお客様に伝えることができれば、それは必ず響くんだ、という証明でした。
「僕は、パンでこの地域を表現したかったんです」
「社長様の今回の新作パンも、非常に尖った商品だと思います。でも、きっとこの裏側にも、社長様が“叶えてあげたい幸せ”があるんですよね?」
そう尋ねると、小林社長様は、堰を切ったように熱い想いを語ってくださいました。 「そうなんだよ!このあんぱんはね、近所のおばあちゃんが作っている、本当に美味しい『干し柿』を使っているんだ。この干し柿を、どうやったら今の若い子たちが喜んで食べてくれるか、発信力の高い女性たちが広めてくれるか…それを考え抜いた結果が、この組み合わせだったんだ」
「そして、この地域には昔から『マタギ(狩人)文化』があってね。山菜も、くるみも、ジビエも、昔から食べていた僕たちの誇りなんだよ。この地域がどれだけ素晴らしいか、子どもたちにもっと誇りを持ってほしい。だから僕はパンでこの地域を表現しようと思ったんだ!」
批判は、“評価”の始まり。想いのある挑戦を恐れないで
社長様、それは素晴らしい哲学です! これだけ尖った商品ですから、きっと批判も出てくると思います。 でも、批判されることがなければ、それは誰からも評価されていないのと同じです。「誰からも好かれる商品」なんて、この世に存在しません。誰かに強く好かれるということは、同時に、誰かにとっては「好みではない」ということ。 批判が来たということは、それだけ注目を集め、評価の土俵に上がった証拠なんです。
「そうか…!自分がやってきたことは、間違いじゃなかったんだな。確信が持てたよ!」 社長様の顔がパッと明るくなり、隣で聞いていた奥様も本当に嬉しそうでした。
皆様の会社では今、常識に挑戦していらっしゃいますか? もちろん、何でもかんでも逆張りをすればいい、批判を受けることが目的になってはいけない、と私たちは思います。 しかし、小林社長様のように「これを届けたい」「この人を幸せにしたい」という熱い想い(哲学)に裏打ちされた“尖った挑戦”は、絶対に恐れてはいけません。
その「想い」こそが、お客様の心を動かし、マスコミをも惹きつける、最強のストーリーになるのですから。
「うちの商品の“想い”、どうやったら伝わるだろう?」 「新しい挑戦をしたいけど、批判が怖くて踏み出せない…」 そんな時は、ぜひ私たちハンズバリューにご相談ください! 皆様の熱い「叶えたい幸せ」を、世の中に届けるための戦略を、一緒に考えさせていただきます!
ぜひご参考ください。
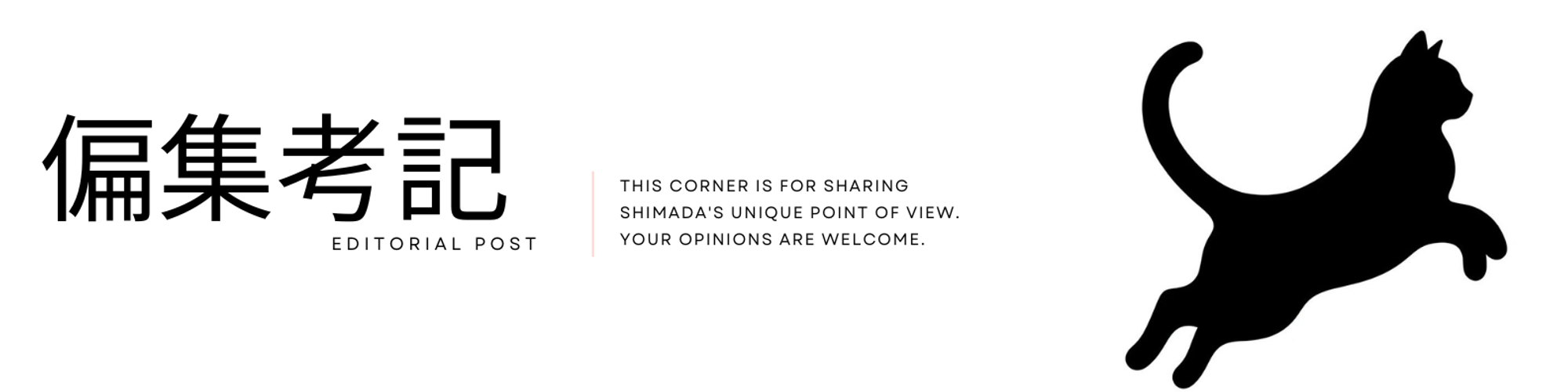 【偏集考記】なぜ私は、面倒な「天ぷら」を揚げたのか?
【偏集考記】なぜ私は、面倒な「天ぷら」を揚げたのか?
「求められること」が人を成長させる
ハンズバリュー株式会社の変革者・作家の島田慶資です。
最近、仕事が終わり保育園に子供を迎えに行くと「今日は天ぷらが食べたい!」「今日は餃子が良い!」とリクエストをいただくことが増えました。 正直、仕事で疲れているので、できるだけ手間のかからない料理で済ませたい、というのが本音です…。しかし、愛する我が子のオーダーですから、できる限り向き合っています。
独身だったら、絶対に作らなかった
先日も天ぷらをリクエストされ、YouTubeでレシピ動画を調べながら、なんとかそれらしいものを作りました。 その調理をしながら、ふと思ったのです。
「もし独身だったら、わざわざ家で天ぷらや餃子を作るだろうか?」と。
答えは、ほぼ間違いなく「No」でしょう。 おそらく、サイゼリヤのようなお店で外食した方が、圧倒的に安く、早く、手軽だからです。自分一人のためだけに、あの面倒な作業をしようとは、到底思わなかったはずです。
挑戦の源泉は「誰か」にある
では、なぜ面倒だと分かっているのに、私は天ぷらを揚げたのか。 それは、「求めてくれる人(子供)」が目の前にいたからです。
ここで私は、人の成長に関する一つの原理原則に気づかされました。 よく「人は挑戦があるから成長できる」と言われます。では、その「挑戦」の源泉は、一体どこにあるのでしょうか。
自分一人のためだけに成長できる範囲には、限界があります。 人は「誰かから求められること」によって、初めて自分の限界を超えた挑戦ができ、結果として成長できるのではないでしょうか。
お客様という「壁」が、私を成長させる
この気づきは、そのまま私たちの仕事にも当てはまります。 今回、新しく公募が始まった「中小企業成長加速化補助金」という大型の補助金。私もお客様のご支援をさせていただきましたが、最初はまさに手探り状態でした。
もし私一人の勉強のためだったら公募要領を読んで終わり。しかし、お客様が私に期待をかけ、信頼して「相談」という形で私に「求めて」くださった。 その期待に応えたい一心でやり遂げたからこそ、お客様を合格に導くことができ、同時に私自身の実力もまた、一段階引き上げられたのだと実感しています。
困難な「壁」に感謝する
「誰かに求められること」は、時には「困難なこと」「嫌なこと」「不安なこと」として、私たちの前に「壁」として立ちはだかります。 子供からの無邪気なリクエストも、お客様からの難しいご相談も、本質は同じです。
しかし、その「壁」があるからこそ、私たちはレシピを調べ、新しい制度を猛勉強し、成長します。そう考えると、困難な壁とは実は「成長の機会を与えてくれる、ありがたい存在」だと言えます。
その壁を乗り越えた時、私たちは成長できる。 そして、その「壁」を与えてくれたことに心から感謝することができれば、きっと、より大きな次の成長を描けるのではないか。 そんなことを、キッチンの油の音を聞きながら、考えていました。
今週も良い学びを。

