皆様、こんにちは! ハンズバリュー株式会社の島田です。
※社内で回覧していただいているお客さまがいらっしゃいました。ありがとうございます!!著作を明記していただけるのであれば、自由に配布ください。
メールマガジンの感想、お待ちしております! 「読んでるよ」と言っていただければ励みになります(^_^)
大型補助金の「新事業進出補助金」の2次公募がスタートしました。挑戦の原資にしてください!
目次
独り言コーナー
❶ユーチューブに初投稿した動画の再生回数が200PVを超えました。まだまだですが、当社にとっては挑戦の第一歩。上出来の成果です。まぐれのホームランより、狙った小ヒットを大事にしたいです。
❷当社の経営指針の刷新も佳境に向かっています。目標値の設定や道筋の設計など、みんなで意見を出し合って決めています。自分だけでは見落としていた課題も見つかりやすくなります。当社は中小企業変革支援プログラムの「企業プロフィールシート」から出発しました。シートを従業員さんと一緒に埋めるだけでも課題がしっかり見えてきました。(書籍でもオススメされていますが…)島田もオススメします😊
❸ヤマヤで輸入品のジェノベーゼソースを調達してきました。冷凍していた手製のソースと食べ比べ。(好みになろうかと思いますが…)手作りのバジル感にはかないません。ただ、油をめっちゃ使うから罪悪感があるんですよね…。
❹ついにグーグルにAIモードが実装されました。確かめられた方はいらっしゃいますか?今後のWeb集客のスタンダードが変わりますよ。ゲームチェンジが起こりました。興奮しています!
❺坊やが保育園で秋祭りを満喫してきました。昨年は先生方にご迷惑をおかけしておりましたが、今年はダンスできてお上手でした。彼の成長が感じられる瞬間でした。
島田の気になるニュース
❶山形県の補正予算が発表されました。観光業に対する予算が非常に少ない。補正予算なのでしかたないのですが、愚痴も出てしまいます。
令和7年度9月補正予算案 主要事業の概要
❷動画制作も受託しているので活用できないかと思って試してみましたが、おもちゃのレベルです。まだまだ実用化には遠いように感じました。
2秒以内に商業レベルの高品質音楽を生成できる音楽生成AI「Stable Audio 2.5」
❸実用化は世界で2番目。海洋国家である日本では夢ある発電システムですね。海水は売るほどあります。おそらく消耗品の浸透膜のコスト問題などあるでしょうが、エネルギー価格が高騰している時流ですから採算合うかもしれませんね。
「浸透圧発電」福岡の発電所が運転開始 実用化レベルで国内初
❹異常な最低賃金の引き上げは政治の介入が当然あったモノと認識しておりましたが、露骨に圧力かけていたんですね。社会保険料や消費税を減免もしくは廃止しない中での意味のない賃上げは国民が苦しむだけだと思います。選挙で勝つつもりがないのでしょうか。
最低賃金、強まる政治介入の「ガチ度」 弱まるエビデンス重視
❺豚肉は栄養価が高いので我が家では重宝しています。子供も大好きです。個人的には米粉などをつけて焼き揚げしたケチャップ炒めが得意です。眺めているだけで調理欲が湧き上がってきますね。
「豚ロース厚切り」50選|食べごたえ満点!
【今週の経済入門】旅行者が減っている?~データが示す地方経済の停滞感~
皆様こんにちは、ハンズバリュー株式会社の秘書・勝頼ヒデコです。 いつもメールマガジンをお読みいただき、ありがとうございます。

9月に入り、夏の賑わいも少し落ち着いて、秋の気配を感じる季節となりました。 先日、後輩のハナコと「今年の夏休み、どこか行った?」という話になったのですが、ハナコは「うーん、近場で済ませちゃいました。正直、物価高で旅行どころじゃなくて…」と寂しそうに話していました。
実は今、このハナコのような感覚が日本経済全体に広がりつつあることを示すデータが発表されています。 本日は、旅行の動向から見えてくる私たちの暮らしと経済の現状について皆様と一緒に考えてみたいと思います。
本日のテーマ『国内旅行の減少が映し出す、日本の“今”』
先日、観光庁から発表された7月の旅行状況に関する統計を見て、私は危機感を覚えました。データによると国内旅行の取扱人数が、前年の同じ月と比べて約10%も減少していたのです。
「えっ、10%もですか!?でも、観光地は結構混んでいるイメージでしたけど…」とハナコも驚いています。
確かに、旅行の取扱「額」を見ると減少幅は10%よりも小さくなっています。これは、旅行に行く一人当たりの単価が上がっていることを意味しており一部では高価格帯の旅行が好調なようです。 しかし、全体として「旅行に行く人の数そのものが減っている」という事実は、私たちの暮らし向きを考える上で、非常に重要なサインと言えるでしょう。
なぜ旅行に行く人が減っているのか?
その最大の理由は、やはりハナコが感じているように物価高による家計の圧迫です。 食料品やエネルギー価格の上昇が続き日々の生活を守ることで精一杯で旅行のような大きな支出を手控える世帯が増えている…これが、統計データに表れた現実だと考えられます。
国内旅行の減少が、地方経済に与える深刻な影響
「でも、旅行に行く人が少し減ったくらいで、そんなに大きな影響があるんですか?」
ハナコのこの問いに、私は「特に地方経済にとっては、見過ごすことのできない大きな問題です」と答えざるを得ません。
観光業は、大都市圏で生み出された付加価値(利益)を地方へと分配する、非常に重要な役割を担っています。
私たちが旅先で使うお金は、宿泊施設や飲食店だけでなく、そこにお土産を納入する農家の方々、商品を運ぶ運送会社、地域の小売店など、本当に多くの人々の暮らしを支えています。
では、国内の旅行消費が減ると、具体的にどれくらいのインパクトがあるのでしょうか。 私の試算によると、もし年間の国内旅行消費額がわずか5%減少しただけでも、以下のような影響が出るとされています。
- 観光業の直接的な付加価値(GDP)の減少:約6,000億円
- 関連産業を含めた経済全体への波及効果:約2兆円~2.4兆円の生産減少
- 雇用への影響:約11万人~12万人分もの雇用が失われる可能性
わずか5%で、これほど大きな影響が出るのです。 観光は、私たちが思う以上に多くの人々の雇用を支え、地方経済の血流を担っていることが分かります。旅行客が来なくなれば、地方の経済はあっという間に活力を失ってしまいます。
「観光立国」の掛け声と現実
政府は長年「観光立国」を掲げ、インバウンド誘致などに力を入れてきました。
しかし、その足元である国内の日本人が、物価高で旅行に行けなくなっているという現実があります。コロナ禍という長いトンネルを抜け、いよいよこれからという時に、なぜもっと直接的に観光業を支援し国民の旅行需要を喚起するような経済対策が実行されないのか。その理不尽さに強い危機感を覚えずにはいられません。
このままでは、日本の大切な観光資源や地方で頑張っている多くの方々の暮らしが衰退してしまう一方です。
政治・経済の大きな動きも大切ですが、まずはこの秋、近場の魅力的な場所に足を運んでみる。そんな小さな一歩も、私たちの愛する地域を支える力になるのかもしれない、とハナコと話していました。
ハンズバリュー株式会社としても、日本の素晴らしい観光業、そして地方経済の未来を真剣に考えて応援していきたいと思っております。
それでは、次回もお楽しみに! 今週もどうぞよろしくお願いいたします。
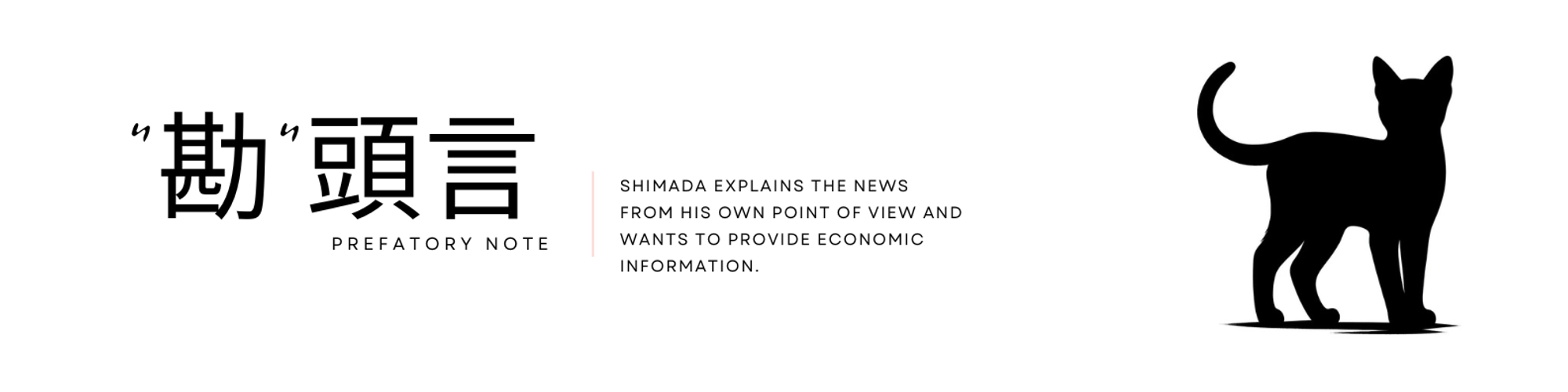 【“勘”頭言】会社の成長を加速させる「良い借金」失速させる「悪い借金」
【“勘”頭言】会社の成長を加速させる「良い借金」失速させる「悪い借金」
皆様、こんにちは。 ハンズバリュー株式会社の変革者・作家、島田慶資です。
「借金」と聞くと、多くの方がネガティブなイメージを抱かれるのではないでしょうか。しかし、会社が成長していくためには、多くの場合「借入」は避けて通れない、むしろ積極的に活用すべき手段です。一方で、その返済に苦しみ、倒産や廃業を選択せざるを得ない会社が存在するのもまた事実。
では、会社の成長を加速させる「良い借金」と、会社を失速させてしまう「悪い借金」は、一体何が違うのでしょうか。本日は、この本質的な違いについて、皆様と一緒に考えていきたいと思います。
返済の原資が見えているか?「良い借金」の正体とは
まず、「良い借金」とは、返済の原資が明確に見えている借入のことを指します。これは金融機関にとっても貸しやすく、事業者にとっても理にかなった、健全な借金です。
代表的な例は二つあります。
一つは、商品の仕入れなどに必要な「運転資金」です。例えば、100円の商品を仕入れる手元資金がない時に、銀行から100円を借ります。その資金で商品を仕入れ、120円で販売する。そして、売上から借りた100円を返し、利息を払い、残りを利益とする。このサイクルは、事業の基本であり、金融機関も安心して資金を供給できる領域です。
もう一つは、生産性を上げたり、売上を増やしたりするための「設備投資」です。例えば、新しい機械を導入することで、毎年100円以上の利益が新たに見込めるとします。その見込み利益の中から、借入の返済と金利を支払っていく。これもまた、未来の利益という明確な返済原資があるため、「良い借金」と言えます。
過去の穴埋めでしかない…「悪い借金」の罠とは
一方で、絶対に手を出してはならないのが、赤字を補填するための借金です。これが「悪い借金」の典型です。
なぜなら、この借金には返済の原資となるものが何も生まれないからです。商品の仕入れであれば、最悪売れ残っても「商品」という資産が手元に残ります。設備投資であれば「機械」という資産が残ります。これらは換金して返済に充てることも可能です。
しかし、赤字補填の借金は、過去に開けてしまった穴を埋めるためだけに使われ、後には何も残りません。 返済の道は、今後の事業利益から捻出するしかありませんが、そもそも赤字に陥っている会社にとって、それは極めて不確実です。
お金を貸す側の視点で見ても、これは当然です。
融資とは、基本的に「ローリスク・ローリターン」の金融商品です。 必ず返ってくるという信頼があるからこそ、低い金利で貸し出すのです。赤字の会社への融資は、返済されるか分からない「ハイリスク」な投資に他ならず、本来の融資の姿とはかけ離れてしまいます。
「良い借金」は成長のレバレッジ
会社を成長させていくためには、この「良い借金」を恐れず、戦略的に活用することが不可欠です。
小売業を例に考えてみましょう。手元資金だけで商品を仕入れていては、事業の成長スピードには限界があります。しかし、「売れる」という確信がある商品を見定めた上で、借入によって多くの商品を仕入れることができれば、成長のスピードは何倍にも加速します。
これは、借入を「レバレッジ(てこ)」として、自社の力を何倍にも増幅させている状態です。
しかし、忘れてはならないことがあります。
「良い借金」だからといって、いつでも金融機関が快く貸してくれるわけではない、ということです。そこには、これまでの取引の歴史や、経営者との信頼関係が大きく影響します。
「良い借金」と「悪い借金」を見極める目、そして「良い借金」を必要な時に調達できるだけの金融機関との良好な関係。この両輪があって初めて、会社は安定成長の軌道に乗ることができるのです。
逆説的に、赤字があったとしても良好な関係が出来上がっていれば金融機関さんは手を差し伸べてくれることも目にしています。
皆様は、金融機関さんとのコミュニケーションはできていますか?今一度、胸に手を当てて考えてみてください。
今週も皆様にとって、実り多き一週間となりますように。
 【実店舗に効く話】「暑いから売れるはず」は危険な思い込み?!お客様の“本当の気持ち”を読むヒント
【実店舗に効く話】「暑いから売れるはず」は危険な思い込み?!お客様の“本当の気持ち”を読むヒント
皆さん、こんにちは。 ハンズバリュー株式会社のコンサルタント、津名久ハナコです。
9月も半ばを過ぎ、山形の秋の風物詩、芋煮会のシーズンに突入しましたね!🍲 私も毎年、会社の先輩たちと一緒に芋煮会を開いています。お料理上手な神原先輩がいつも美味しい差し入れをたくさん持ってきてくださるので、私たちはもっぱら飲んで食べる専門です(笑)。本当にありがたい限りです!
さて本日は「こうなるはずだったのに、なぜ…?」という、ビジネスの予測の難しさについてお客様とのやり取りを交えてご紹介したいと思います。 お相手は、クリーニング店を営んでいらっしゃる女性経営者・本部(もとべ)社長様です。
「こんなに暑かったのに…なぜ売上が伸びないの?」
- 「ハナコちゃん、いつもメルマガ読んでるわよ!今日はちょっと教えてほしいことがあって…」
- 「社長様、ありがとうございます!もちろんです、何でしょう?」
- 「今年の夏、すごく暑かったじゃない?だから、汗をかいた洋服や浴衣のクリーニングがたくさん増えるかなって期待してたの。でも、待てど暮らせど思ったほど増えないのよ。なぜだと思う?」
なるほど…。「天候」と「売上」の一見すると単純に見える関係。本部社長が疑問に思われるのもよく分かります。 実は「AだからBになるはず」という単純な予測には、思わぬ落とし穴が潜んでいることがあるんです。
意外な事実!「暑すぎるとビールは売れない」
社長様、実は最近、こんなニュースがあったのはご存知でしょうか?
暑すぎて…ビールが売れない? 記録的暑さで外出機会減少 ビール大手4社が発表した8月のビールの販売は、去年の8月より9%減少。夏場に消費が増えるビールですが、最高気温が35℃を超える日が続くと、水などの清涼飲料に需要が移る傾向があるとのこと。特に今年は記録的な暑さでビアガーデンや居酒屋など業務用の売上が落ち込みました。
ー2025/9/10 TBS NEWS DIG より要約
本部社長様も、この記事のコピーを見ながらむむっと眉をひそめられました。 そうなんです。普通に考えれば「暑い=ビールが売れる」はずなのに、「暑すぎる」とお客様の行動やマインドが変化し、結果として売上が落ちてしまうことがあるんですね。
お客様の「心の声」を想像してみよう
このビールの話を、社長のクリーニング店に当てはめてみましょう。 社長様はきっと、夏祭りなどで着る「浴衣」のクリーニング需要も期待されていましたよね? でも、もしかしたらお客様の心の中はこうだったかもしれません。
- 「こんなに暑い中、人混みのお祭りに行く気力なんてないわ…」
- 「そもそも、浴衣を着て出かけるなんて、考えただけで汗だくよ…」
- 「出かけるとしても、家でジャブジャブ洗えるユニクロのTシャツで十分かな」
つまり、「暑いから汗をかく→クリーニングが増える」という単純な図式だけでなく「暑すぎてお客様の行動や気分(マインド)が変わってしまった」という可能性を考える必要があるのです。
「事実」と「気持ち」両方の視点を持とう!
ここで大事になってくるのが2つの情報です。
-
デモグラフィック情報
気温や天候、季節といった、お客様を取り巻く「事実」や「環境」のことです。
-
サイコグラフィック情報
お客様の気分や価値観、ライフスタイルといった「心の中」や「気持ち」のことです。
これからのビジネスでは、この両方の視点をバランス良く持つことがますます重要になってきます。
「なるほど…。単純に暑いからどう、というわけではないのね…」
そうなんです、社長様! お客様の気持ちを完全に理解するのは難しいですが「もし自分だったらどう思うかな?」と考えてみたり、日々来店されるお客様の様子や仕草、お持ちになる洋服の種類などを今まで以上によく観察してみることで、そのヒントが見えてくるはずです。
「常識」を疑いお客様の「心」に耳を傾けよう
「〇〇だから、きっとこうなるはず」
私たちが当たり前だと思っている「常識」や「過去の経験則」が、通用しなくなってきているのかもしれません。 大切なのは、データや事実といった情報だけでなく、その裏側にあるお客様の「本当の気持ち」に常にアンテナを張っておくこと。
皆様のビジネスでも、「そんなはずじゃなかったのに…」という思い込みで、大切なチャンスを逃してはいませんか?
「うちのお客様の“本当の気持ち”って、どうやったら分かるんだろう?」 「データとお客様の気持ち、どう結びつければいいの?」
そんな時は、ぜひ私たちハンズバリューにご相談ください! 数字の分析はもちろん、その先にあるお客様の心の声に耳を澄ませるお手伝いを一緒にさせていただきます!
ぜひご参考ください。
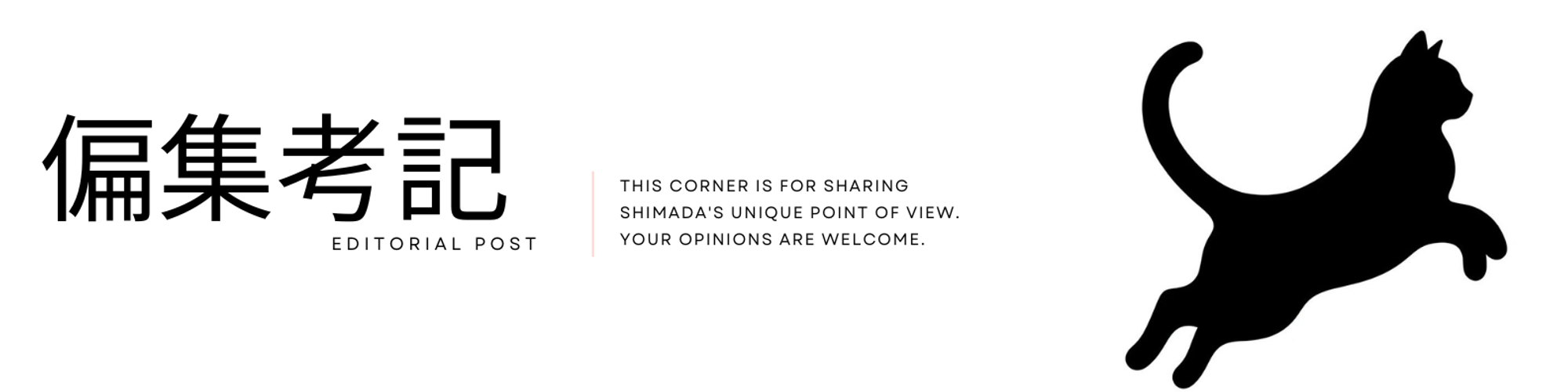 【偏集考記】「違いは尊重、でも目的は一つ」
【偏集考記】「違いは尊重、でも目的は一つ」
~寓話が教えてくれた、強い組織の作り方~
ハンズバリュー株式会社の変革者・作家の島田慶資です。
先日、山形県内で尊敬するベテラン経営者の方から朝礼などで使えるいくつかの「寓話」を頂戴するという大変ありがたい機会をいただきました。 一つひとつの物語に気づきや学びがあり「この寓話を社員さんと一話ずつ共有し、それぞれの感想を語り合ったらどんな意見が出るだろう」と、今からワクワクしています。
物語が示す一つの共通点
いただいた寓話は三つあり、それぞれテーマは異なります。
しかし、あえてその三つの物語に共通するものは何かと考えてみたとき、私の中に一つの気づきが生まれました。 それは「人はそれぞれの立場、能力、知識、経験によって、考え方や物事の見方が全く異なってくる」という、至極当然でありながら私たちが日常で忘れがちな真実です。
私たちがこれまで生きてきた中で培われた人生観や価値観は、育った環境や時には偶然の出来事によって大きく左右されます。その土台の上に、さらに個々の技術や専門的な経験が加わるのですから、一人ひとり考え方が違うのは当たり前なのです。
「違いの尊重」と「目的の一致」
では、この気づきを会社経営に置き換えると、どうなるでしょうか。 まず大前提として、社員さん一人ひとりの価値観や人生観は、最大限に尊重されるべきだと私は考えています。こちらが相手を尊重するからこそ、相手もこちらを尊重してくれる。この相互尊重の関係こそが、健全で建設的な人間関係の基本です。
しかし、組織である以上、そこには一つだけ譲れない条件が加わります。 以前、茨城県で開催された「第9回 経営労働問題全国交流会」で学んだ言葉です。
「人それぞれ違いはあってもいい、でも目的は一つ」
そうなのです。私たちは、その会社の「目的」に共感し、その実現に貢献するために集まっているはずです。 だからこそ、個々の世界観や個性は豊かさとして尊重しつつも、向かうべきゴール、つまり会社の目的は全員が一致していなければなりません。
会社とは、単なる人の「あつまり」ではなく、「目的を持った集団」です。そして、その目的達成のためにお互いがそれぞれの強みを活かして貢献し合う関係性があって初めて、組織として機能するのだと私は考えます。
寓話がくれる「考えるきっかけ」
今回いただいた寓話は、こうした組織の原理原則を私たちに改めて考える「きっかけ」や「ヒント」を与えてくれる素晴らしいツールだと感じています。 頭ごなしに「目的を一つにしろ」と言うのではなく、物語を通じて、違う角度から物事を捉え直す機会をくれる。そのことに感謝しています。
皆さんの会社では、多様な個性が尊重されていますか? そして、その多様な力は一つの目的に向かってベクトルが合わさっているでしょうか。
今週もどうぞよろしくお願いします。 良い学びを。

